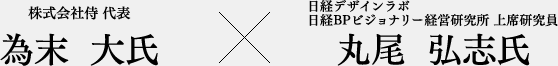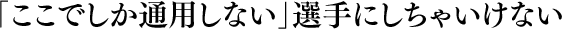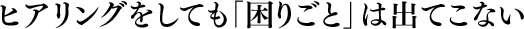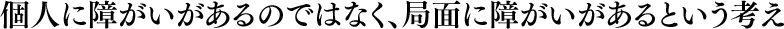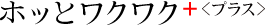
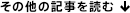


vol.48 対談企画健常者と障がい者が共に練習する風景を当たり前のものに。スポーツ施設のUDを考える
「誰もがスポーツやアートを楽しむ」ことをコンセプトに掲げ、
2016年末にオープンした新豊洲Brilliaランニングスタジアム。
全天候型60メートル陸上トラックに、競技用義足開発ラボラトリー、ランニングステーションが併設された
バリアフリーのスポーツ施設です。
館長を務めるのは、400mハードル日本記録保持者(2017年7月現在)で、
2020年東京オリンピック・パラリンピックをサポートする為末大氏。
どんな工夫が施された施設なのか、根底にはどんな哲学が流れているのか、
日経デザインラボの丸尾弘志氏がお話を伺います。
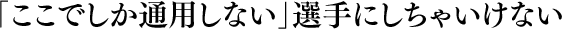
「ここでしか通用しない」選手にしちゃいけない
丸尾弘志 氏(以下、丸尾)
為末 大 氏(以下、為末)
- 丸尾:
- まず、障がいのある方がスポーツ施設を利用する際に、ぶつかりがちな壁や困りごとがあれば教えてください。
- 為末:
- 新豊洲Brilliaランニングスタジアムは健常者も障がいのある方はもちろん、老若男女だれでも使用できる施設です。義足ユーザーも多いのですが、話を聞くと「ほぼ不便はない」と言います。
- 丸尾:
- 不便はない。それは、当ランニングスタジアムで不便はない、ということでしょうか? それとも、既存の施設で?
- 為末:
- 後者です。なぜかというと、ずっと義足でこなしてきたから、何とかなってしまうんです。みなさん共通して、「環境は変えられないので自分を変えよう」という姿勢を持っていますね。だから、不便なことや不満を尋ねても、なかなか出てきません。
当ランニングスタジアムでは、「パラリンピアンとそうではない人が一緒に練習している風景を当たり前のものにすること」を意識しました。実は、スポーツ界でそういう風景が見られるようになったのはここ数年のことです。「健常者」と「障がい者」がくっきりと分かれていた。だから、施設を運営している人たちが障がいのある人のことをよく理解していない。どんなことに悩んでいるかわからない。その分断こそが一番の課題だと感じます。

丸尾弘志 氏
日経デザインラボ 日経BPビジョナリー経営研究所上席研究員。1998年国際基督教大学卒。同年日経BP社に入社、日経システムプロバイダ記者。2001年に日経デザインに配属後、パッケージデザインのリサーチやブランディング、知的財産、新素材開発にまつわる取材を行う。2016年より現職。主な著書に「パッケージデザインの教科書」「売れるデザインの新鉄則30」など

為末 大 氏
1978年広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得。3度のオリンピックに出場。男子400メートルハードルの日本記録保持者(2017年7月現在)。現在、スポーツに関する事業を請け負う株式会社侍を経営するほか、一般社団法人アスリートソサエティの代表理事を務める。主な著書に「走る哲学」(扶桑社新書)、「諦める力」(プレジデント社)など
- 丸尾:
- 当ランニングスタジアムは、障がい者と健常者が共に練習できる施設ですね。具体的には、どんな工夫をされたのでしょうか。先日見学してきたのですが、トラックの幅を広げたり、床面を強化したり、といったことはされていないようですね。
- 為末:
- ええ。ほかの施設とは違った特別な環境にしてしまうと、日常や試合のときに適応できなくなってしまいますから。途上国での試合も多いですし、そこで普段の力が発揮できない、ということになるほうが問題です。ですから、ハード面は通常のスポーツ施設と同じようにつくりました。
重視したのは、「ぎょっとしない空気」をつくることです。パラリンピアンの選手が義足を外すと、ひざ下が欠損しているので、初めて見る人はびっくりしてしまうんです。空気が一瞬凍るというか…。と言っても、戸惑う人が悪いわけではありません。ただ慣れていないだけなんですよ。 だから、とにかく慣れること。ほかの選手や子どもたちが走っている横で、普通に義足を脱いでいる。それが当たり前の風景になればいい。そうやって慣れて友達になると、何か困っていたら自然と助けますよね。障がいのあるなしには関係なく。
- 丸尾:
- 確かにそうですね。
- 為末:
- 障がいには「ハード」「モノ」「意識」という3つのカテゴリーがあります。たとえば車いすで段差にぶつかったとき、「なんで段差があるんだ」と考えることもできるし、「なんでこの車いすは段差を超えられないんだ」とか、「なんで誰も助けないんだ」と考えることもできます。僕は、3番目がいちばん本質的で解決に結びつくアプローチではないかと思っています。
もちろん、大きな視点で見たらハード面も変えていく必要があります。でも、ひとりの選手人生の長さを考えると、世界中のハードが変わるまで待っていることはできません。だから、「そこでしか通用しない」選手にしてはいけないんです。


毎週開校している、子どもたちを対象としたTRACかけっこスクールの様子(写真提供:侍)
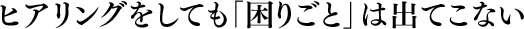
ヒアリングをしても「困りごと」は出てこない

建物は薄くて丈夫なフィルム膜につつまれている

建物はトンネル状で長さ108メートル、高さ8.5メートル、幅16.27メートルの規模。骨組みにはカラマツの集成材を使用(写真提供:侍)
- 丸尾:
- そうすると、同ランニングスタジアムには、ハード面の工夫はあまりないということでしょうか?
- 為末:
- いえ、現段階でやれることはやっています。段差はありませんし、車いすのまま使用可能なミストサウナ付きシャワールームとユニバーサルデザインのトイレを設置しています。まだ、シャワーはあまり使ってないようですね(笑)。高齢者の方が施設を使いはじめたら活躍するかもしれません。
義足の選手がシャワーを浴びるときは片足で跳ねながら入るので、滑って転倒する危険があります。幸い、滑りにくい床材を採用していたのでほっとしています。
- 丸尾:
- 事前のヒアリングなどで「ここはこうして欲しい」といった希望は出てこなかったのでしょうか。
- 為末:
- 出て来ませんでした。それは、普段も片足で入っているから慣れてしまって不便だと認識していないという側面と、本当に困っていないという側面と、両方あると思います。
ヒアリングで「困っていない」と言われたときに、僕たちはどうしても「でも本当は困ってるんじゃないですか」と言いたくなります。でも、「困っていない」と言ってるんだから、それは押しつけじゃないかという気もするんですよ。実際、食い下がって質問すると選手はとても嫌がります。「健常者には聞かないのになんで我々にだけ」と。障がい者は必ず何かに困っている存在だ、という思い込みから放たれることが、双方が一緒に使える施設をつくるときの第一歩なのかもしれません。
- 丸尾:
- 「健常者」「障がい者」という分け方に拘らず、誰にとっても使いやすい施設であることが大事なのでしょうね。
- 為末:
- 後から設備などを加えることもできますからね。既にあるものを省くのは難しいけど、使っていくうちに不便そうなポイントを見つけたときに、「ここに手すりがあったら便利じゃない?」と足していく。
- 丸尾:
- 都度都度考えて改善していきましょう、と。

ハードではなく、意識に問題がある
- 為末:
- 僕は、日本の競技場の問題はハード面よりも運用面にあると思っています。予約するのも一苦労だし、とても決まり事が多いんですよ。床が傷つくので義足や車いすの選手は使ってはいけませんとか、安全が確保できないので利用を許可できませんとか。
競技場のあり方をあらためて考えてみると、大事なのは根底にある哲学なのですね。「2020年にパラリンピックが開かれるからユニバーサルデザインの施設にしましょう」といった表層的な考えでは、真に使いやすい施設にはなりにくい。「社会はどういう風にあるべきか」からスタートして、「そのためにどのような施設をつくろう」と落とし込んでいかないといけないんです。
- 丸尾:
- 哲学がないと、ハード面はバリアフリーでも、そこにいる人の心はバリアフリーではない施設になってしまうんですね。
- 為末:
- 当ランニングスタジアムでは、誰が来てもいいということを大事にしています。重度の障がいのある方が来て、いまの設備では利用が難しかったとしたら、一緒に考えて改善していけばいい。みんなで育てる競技場という位置づけなんです。
- 丸尾:
- 少し話は変わりますが、トラックのすぐわきに競技用の義足開発ラボがありますね。どんな意図で併設したのでしょうか。
- 為末:
- 義足の調整をするんです。たとえば、走る度に少し右に寄る傾向があるなら、「じゃあネジをゆるめて角度を整えてみましょう」ですとか、アジャストがひざの裏に当たって痛いのであれば「少し削って小さくしてみましょう」ですとか。そんな風に、走って違和感のある箇所をすぐに変えられます。
最大の利点は、義足製作の技術を持ったエンジニアとアスリートが同じ場にいて、すぐにコミュニケーションできること。いままで驚くほど交流がなかったんですよ。エンジニアやアスリートに限った話ではなく、人はどうしても自分と同質の人と集まりやすいやすいものですよね。同ランニングスタジアムでは、それがふわっと崩れて、交流が始まります。
さまざまなバックグラウンドの人が集まって、意味のある話もない話も混ぜこぜに自然と交流している。なかなかない風景ではないかと思います。
- 丸尾:
- いい風景ですね。

競技用義足開発のラボ。専門のエンジニアが常駐し、競技用義足の開発・調整とともにトップ障がい者アスリートの強化訓練も運営(写真提供:侍)

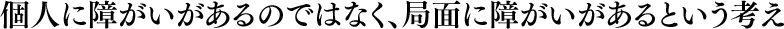
個人に障がいがあるのではなく、局面に障がいがあるという考え
- 為末:
- 考え方は非常にシンプルです。全てをフラットにしよう、と。気を使いすぎて逆差別になってしまうのも良くない。足が不自由でもできることはあるし、もしかすると学習障がいの子どものほうが困っているかもしれない。それなら逆にボランティアしてもいいんじゃないか、とか。
たとえば、日本語が話せないスペイン人と、日本語しか話せない健常者と、スペイン語と日本語を話せる義足の人がいたとして、その局面で障がいがあるのは一体誰なのか。そこではスペイン語の通訳ができる義足の人が一番役立つわけですよね。障がいは個人に帰属するものではなく、局面に障がいがあるのだと考えています。
もうひとつ、好きな話があって。車いす使用者が盲目の人と出かける話です。車いすの人が進む方向を伝えて、盲目の人が車いすを押して進むんです。人間は凸凹があって、貰うばかりの人も与えるばかりの人も存在しない。できることを差し出し合って、補い合うのが理想の社会ではないでしょうか。
新豊洲Brilliaランニングスタジアムも、「何か困っていることがあったらサポートするけど、逆に僕らが困っていたらサポートしてね」というスタンスを取っています。僕が弱者になる局面だってあるだろうし、そのときは助けてもらおうと思っています。
- 丸尾:
- 本当に、フラットなんですね。
- 為末:
- 何というか、障がいというとシリアスになっちゃうんですよね。力みすぎてしまう。こう、99%は「唐揚げ好き?」みたいな他愛ない話をしていて、何か困ったことがあったら話し合う位でいいんじゃないかと。障がいって、その人の個性のうち数%もないと思うんですよ。
僕の好きなアメリカのドラマには脇役に義足の人が出てくるんですが、最初から最後までなぜ彼が義足なのかという説明はなくて、ただ普通に義足で登場するんです。その空気感がすごく好きで。血液型や星座が何だって関係ないのと同じで、障がいのあるなしよりも大事なことがあるでしょう、と思っています。

新豊洲Brilliaランニングスタジアムは、分断をつなぎ直す場
- 丸尾:
- そういう空気や意識を浸透させる秘訣はあるのでしょうか。
- 為末:
- 色々試して、結局は「慣れ」だなと思うようになりました。子どもたちを見ていると、耳の聞こえない人と接するとき自分なりに手話をつくっていたりするんですよ。あっちに競技用ハードルがあってね、と指でハードルを描いたりして、身振り手振りで(笑)。どこまで通じるかわからないけど、そうやって何とかコミュニケーションを取ろうとするその感じがいいなと。
- 丸尾:
- 柔軟ですね。確かに、コミュニケーションの基本だという感じがしますね。
- 為末:
- 別に社会が悪いわけでも誰が悪いわけでもなくて、ただ今まで少し分断が大きかっただけなんじゃないかな、と思っています。必要なのは、分断されていた人たちを混ぜるようなきっかけ。だから、そういう場をつくりたいんです。その過程で改善できそうなことを見つけたら、ハードのデザインとして落とし込んでいけばいい。
とにかく、「力みを取ろうよ」「困っていたら助け合おうよ」というのが僕の哲学で、スタッフのみんなにもそう話しています。
- 丸尾:
- 2020年のパラリンピックに向けて、社会全体がそうした空気になっていくといいですね。本日はありがとうございました。
編集後記「力みをとろうよ」という為末さんの言葉には、取材メンバー一同がハッとしました。障がいに限らず、自分と異なる個性を持つ人と接するときには、何をどう話したらいいのか、何に気を付けたらいいのかと、つい身構えてしまいがちです。困ったときに自然体のままで助け合うということを、ひとりひとりが、さまざまな局面で積み重ねると社会は少しずつ変わっていきそうです。為末さんの発する言葉の深みと温もりに、走る哲学者たる所以を感じた取材です。日経デザインラボ 介川 亜紀
写真/*KEICO PHOTOGRAPHY(特記以外) 取材・文/飛田恵美子 構成/介川亜紀 監修/日経デザインラボ 2017年8月28日掲載
※『ホッとワクワク+(プラス)』の記事内容は、掲載時点での情報です。

- vol.49 は、車いすテニスプレーヤーの二條実穂さんの第44回国際福祉機器展 H.C.R.2017のTOTOブース体験記です。
2017年9月末日公開予定。
![]()