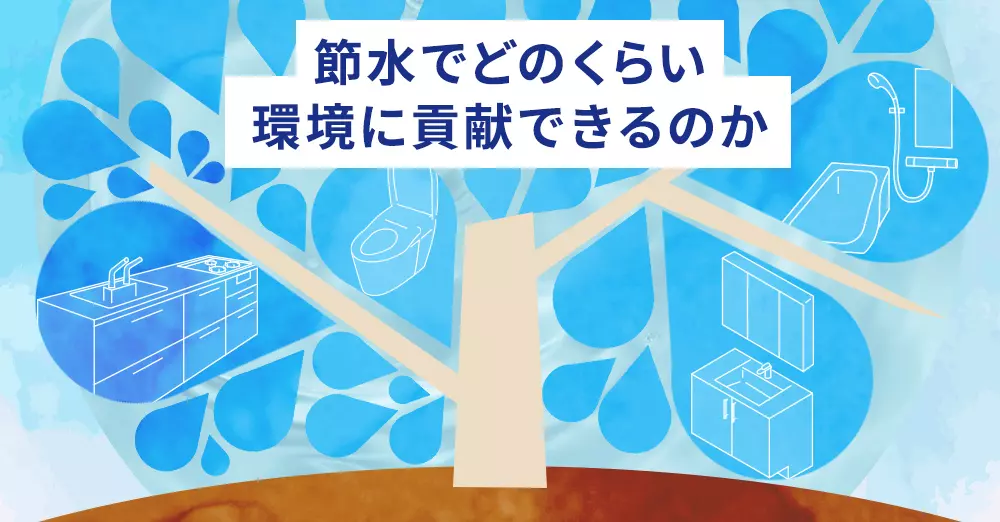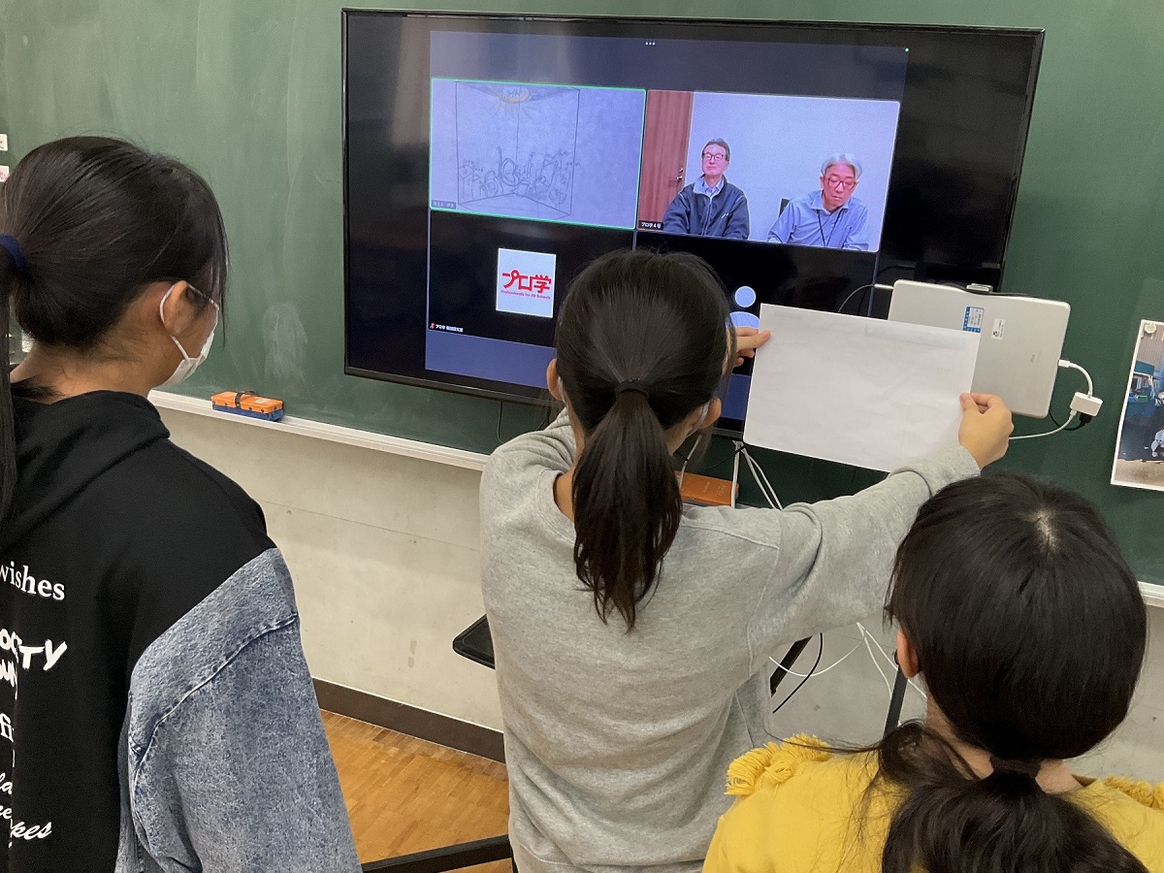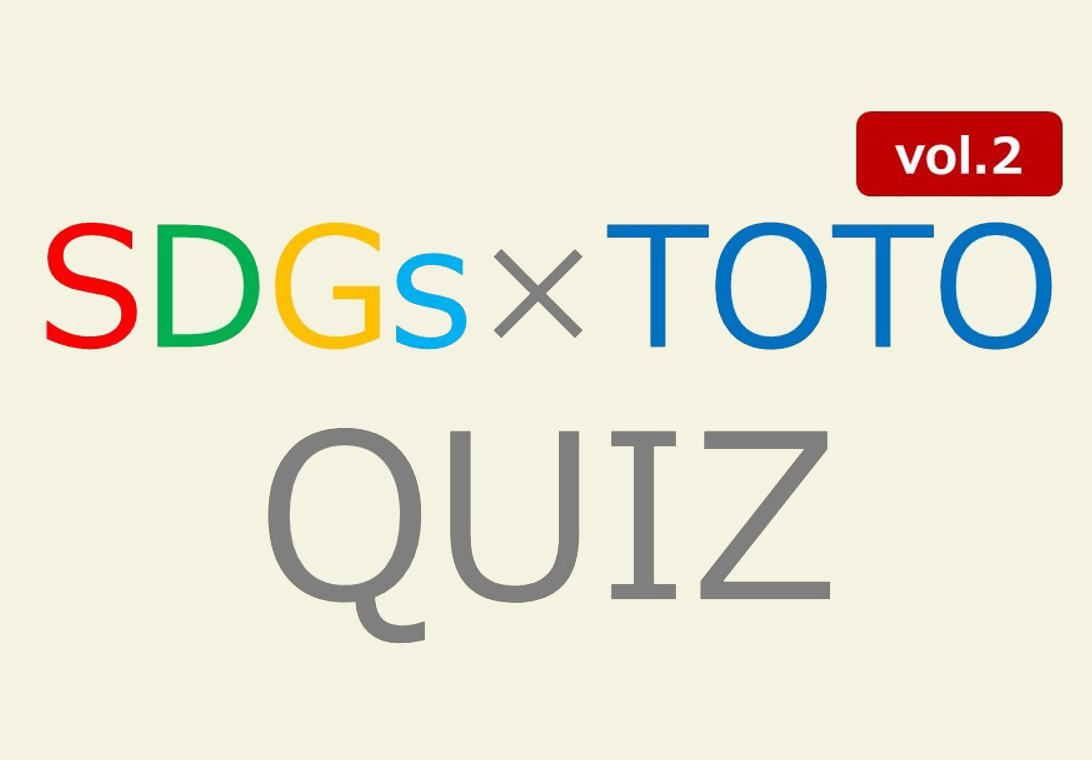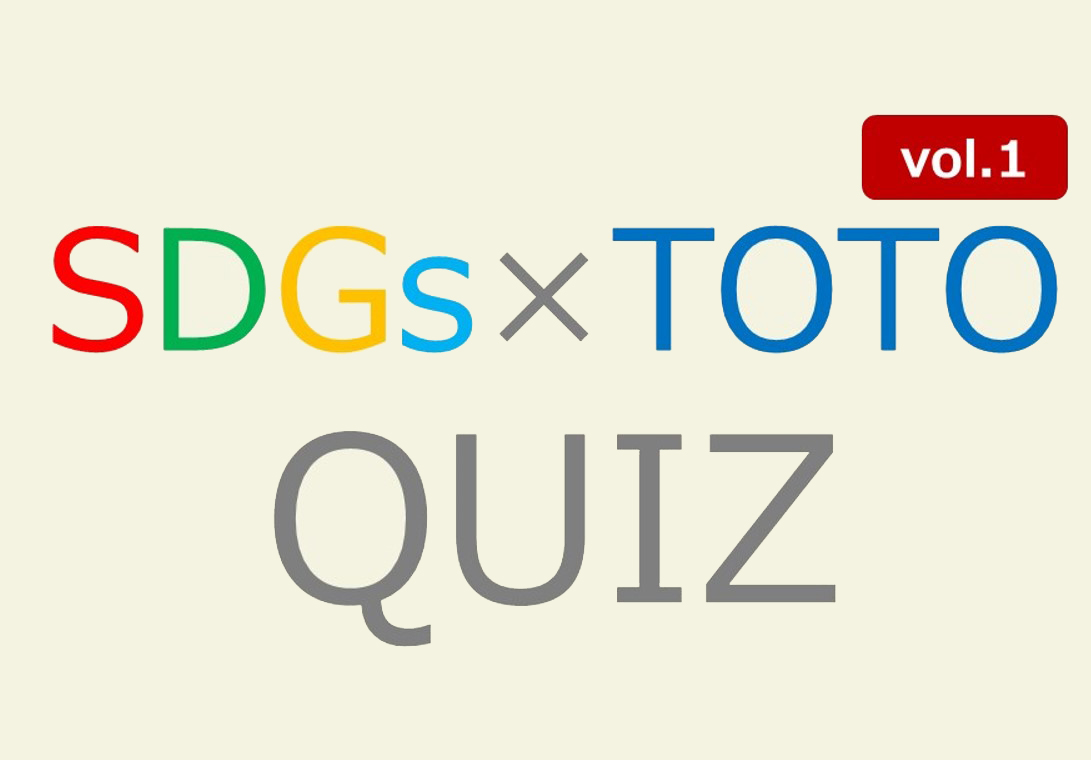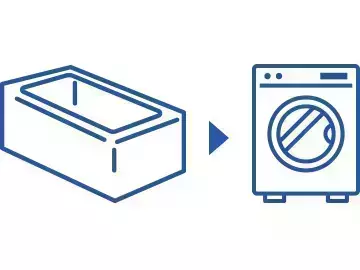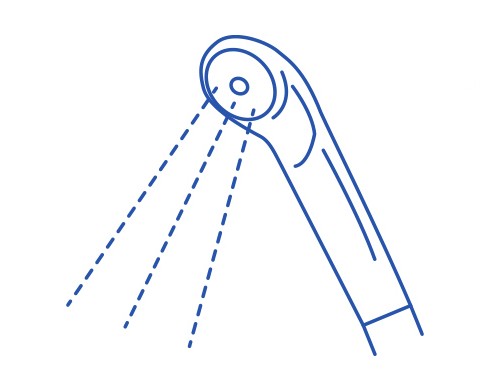水と地球の、あしたのために。
#地球にやさしい・SDGs
#水
#環境貢献

SDGs×TOTO
TOTOは、さまざまな活動を通じて、国連が採択した
「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標達成に貢献しています。
TOTOが取り組む3つのテーマやSDGsに対する社員のインタビューをお届けします。
水まわりから環境を考える
水まわりからできる環境活動をQ&A でわかりやすく説明します。
TOTOのグリーン商品
TOTOのグリーン商品は、節水・節ガス・節電になる環境に配慮した商品です。
グリーン商品に替えた場合の光熱費のお得をご紹介します。
PICK UP








学校教育
お役立ち情報
TOTOの環境や社会への取り組み
環境省との取り組み
関連リンク
お気に入りに保存しました