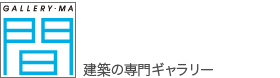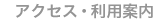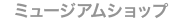- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

特別対談
TOTOギャラリー・間で開催中の「スミルハン・ラディック展 BESTIARY:寓話集」。ひとつひとつの展示品に込められたラディック氏の考えを紹介したい。そんな思いから、ラディック氏の来日中に、『エル・クロッキース』などで知られる写真家で友人の鈴木久雄氏と、展覧会について語り合っていただく対談が実現しました。本展にご協力いただいた、建築家で模型職人のアレハンドロ・リューエル氏も加わり、模型が生まれるプロセスやおふたりのコラボレーションのやり方についてもお話いただきました。
対談日:2016年7月6日(水)
場 所:TOTOギャラリー・間
出演者:スミルハン・ラディック(建築家、本展出展者)
鈴木久雄(写真家)
アレハンドロ・リューエル(建築家・模型職人、本展協力者)
鈴木:日本への訪問はこれが何度目?
ラディック: 最初はTOTOギャラリー間の「GLOBAL ENDS」(2010年に開催されたTOTOギャラリー・間25周年記念展)の展覧会の時。2回目はTOTOギャラリー・間の運営委員でもあるエルウィン・ビライさんが招待してくれて……、3度目は銀座メゾン・エルメスの展示の時でマルセラ・コレア(彫刻家、ラディック氏の妻で共同製作者)も一緒に来て1ヶ月ほど滞在したよ。それから……今回で4度目ということになるかな。
対談日:2016年7月6日(水)
場 所:TOTOギャラリー・間
出演者:スミルハン・ラディック(建築家、本展出展者)
鈴木久雄(写真家)
アレハンドロ・リューエル(建築家・模型職人、本展協力者)
鈴木:日本への訪問はこれが何度目?
ラディック: 最初はTOTOギャラリー間の「GLOBAL ENDS」(2010年に開催されたTOTOギャラリー・間25周年記念展)の展覧会の時。2回目はTOTOギャラリー・間の運営委員でもあるエルウィン・ビライさんが招待してくれて……、3度目は銀座メゾン・エルメスの展示の時でマルセラ・コレア(彫刻家、ラディック氏の妻で共同製作者)も一緒に来て1ヶ月ほど滞在したよ。それから……今回で4度目ということになるかな。

▲スミルハン・ラディック氏
鈴木:日本への興味が、滞在の回数につれて増す、というようなことはある?
ラディック:それがとても不思議なんだ。日本を最初に訪れた2010年の少し前 、僕は旅行することにほとほと疲れていて、これからはなるだけ出張を控えようと思っていたんだ。でもそんな時に日本から招待を受けて、そうか、でも行き先が日本なら、ということで 決心をして、実際に日本へ行ってみたら……自分の中で再び旅をしたいという意欲が目覚めたんだ。そんな個人的な経験もあって、日本には特別な愛着を感じているよ。もちろん僕たちは日本が大好きだ。皆とても親切だし、まるで別世界に居るよう。もちろんここでは自分が異国人であることを自覚しないわけにはいかないけれど、とても歓迎されているということが心から感じられる。それはとても素敵なことだ。
ラディック:それがとても不思議なんだ。日本を最初に訪れた2010年の少し前 、僕は旅行することにほとほと疲れていて、これからはなるだけ出張を控えようと思っていたんだ。でもそんな時に日本から招待を受けて、そうか、でも行き先が日本なら、ということで 決心をして、実際に日本へ行ってみたら……自分の中で再び旅をしたいという意欲が目覚めたんだ。そんな個人的な経験もあって、日本には特別な愛着を感じているよ。もちろん僕たちは日本が大好きだ。皆とても親切だし、まるで別世界に居るよう。もちろんここでは自分が異国人であることを自覚しないわけにはいかないけれど、とても歓迎されているということが心から感じられる。それはとても素敵なことだ。

▲鈴木久雄氏
鈴木:チリと日本には似ているところがあると思う?
ラディック:チリと日本が似ているとはあまり思わない。でも一昨年ロンドンへ行った時に、ロンドンと東京の間に何かすごく共通するものを感じて、日本人スタッフのユウジに「何だろう、君はどう思う?」と聞いてみたんだ。ユウジの答えは「ロンドンは東京と似ているかもしれないけれど、もっとエレガントだ」というものだったけれど(笑)僕にはロンドンと東京は完全に離れていながらも似ているところがあるように見えるよ。
鈴木:今回の展覧会について、どんな風に準備を始めたか聞かせてもらえるかな。
ラディック:これらの模型をオフィスで作り始めたのは2010年のこと。最初は仕事というよりも遊びだったんだ。物語性のあるモデルを作りたいと思い、好きなだけ時間をかけて、特に完成を急いだりすることもなく、楽しんで作ることにした。これが将来何かプロジェクトとして形のあるものになるとは、その時は全く考えていなかったけれど、むしろそれがとても良かったんだ。後になって、これらの模型の多くは、実際のプロジェクトに発展していくことになったのだけれど、つまり非現実的な作業が、現実的な技術を必要とする、建設可能なプロジェクトに成長していってしまったんだ。すごいことだと思わないか?この調理時間というのが、だいたい6年間から8年間分くらいの仕事量になるのかな。その期間というのは、建築家で模型を作ってくれているアレハンドロ・リューエルが僕たちと一緒に仕事をするようになった時期と重なるわけだけれども、最終的にこれらの模型たちは「寓話集(Bestiary)」と呼ばれる奇妙な動物の家族のようなものになった。まるでおとぎ話の世界の中に住んでいる「獣(Beast)」たちの家族だ。空想だったものがここで現実のものになって現れたような。
「寓話集」と名付けたもうひとつの理由は、ここにある「獣」の多くが、半分が獅子でもう半分が鷲という架空の動物グリフィンのように、異質な物同士が組み合わさってできたものだ、というところにある。僕のプロジェクトの多くも、大空間の上にサーカスを置いたり、岩に何かを付加したりといったように、何か新しい物を発明するというよりは、異なる何かの部分同士を組み合わせて作ったところがあるからね。それは未来を見通すというよりも、過去の中に参照を探す作業とも言えるかもしれない。この展示を包括するアイディアは、そういった大きな家族を、個人的な寓話集として提示するということ。この展示室にはそういった多くの模型が展示してあって、上の展示室にはヒサオも前に撮影した、建設されたものを含む、実際のプロジェクトが展示してある。ここにある模型は、作品の最初のアイディア模型だったり、初期案の模型だったり、プロジェクトの最終案的な模型だったり、いろいろな種類のものがあるけれど、ちょうど家族、あるいは種族のように皆関係しあっているんだ。
鈴木:ここにあるものがみんな何かから生まれ出て、その模型自身が何者かに育っていって、アレハンドロの手を借りて少しずつ現実の建築プロジェクトに変身していく、という事実が本当に興味深い。
ラディック:ここには実際に建ったもの、クライアントに向けて作られた模型、コンペに提出した模型、初期模型、「遊ぶ」ために作った模型など、「建築のプレゼンテーション」という目的のためだけではないさまざまな種類の模型があるのだけれど、アレハンドロが本当に上手く作ってくれるものだから、どの模型にも、たとえそれが単なるプロセスの途中経過を示した模型であったとしても、何か決定的な、あるいはリアルな様相が現れてきてしまうんだよね。僕はそういう感じがとても気に入っている。
鈴木:その感じ、とても良く分かるなあ。そして模型の中に心や頭といった君の何かが現れて来るんだね。その一方で、例えばこの人形の模型のように、見る人を戸惑わせるような、何処へ向かっていくのか分からなくなるようなモデルもあるけれど……。
ラディック:チリと日本が似ているとはあまり思わない。でも一昨年ロンドンへ行った時に、ロンドンと東京の間に何かすごく共通するものを感じて、日本人スタッフのユウジに「何だろう、君はどう思う?」と聞いてみたんだ。ユウジの答えは「ロンドンは東京と似ているかもしれないけれど、もっとエレガントだ」というものだったけれど(笑)僕にはロンドンと東京は完全に離れていながらも似ているところがあるように見えるよ。
鈴木:今回の展覧会について、どんな風に準備を始めたか聞かせてもらえるかな。
ラディック:これらの模型をオフィスで作り始めたのは2010年のこと。最初は仕事というよりも遊びだったんだ。物語性のあるモデルを作りたいと思い、好きなだけ時間をかけて、特に完成を急いだりすることもなく、楽しんで作ることにした。これが将来何かプロジェクトとして形のあるものになるとは、その時は全く考えていなかったけれど、むしろそれがとても良かったんだ。後になって、これらの模型の多くは、実際のプロジェクトに発展していくことになったのだけれど、つまり非現実的な作業が、現実的な技術を必要とする、建設可能なプロジェクトに成長していってしまったんだ。すごいことだと思わないか?この調理時間というのが、だいたい6年間から8年間分くらいの仕事量になるのかな。その期間というのは、建築家で模型を作ってくれているアレハンドロ・リューエルが僕たちと一緒に仕事をするようになった時期と重なるわけだけれども、最終的にこれらの模型たちは「寓話集(Bestiary)」と呼ばれる奇妙な動物の家族のようなものになった。まるでおとぎ話の世界の中に住んでいる「獣(Beast)」たちの家族だ。空想だったものがここで現実のものになって現れたような。
「寓話集」と名付けたもうひとつの理由は、ここにある「獣」の多くが、半分が獅子でもう半分が鷲という架空の動物グリフィンのように、異質な物同士が組み合わさってできたものだ、というところにある。僕のプロジェクトの多くも、大空間の上にサーカスを置いたり、岩に何かを付加したりといったように、何か新しい物を発明するというよりは、異なる何かの部分同士を組み合わせて作ったところがあるからね。それは未来を見通すというよりも、過去の中に参照を探す作業とも言えるかもしれない。この展示を包括するアイディアは、そういった大きな家族を、個人的な寓話集として提示するということ。この展示室にはそういった多くの模型が展示してあって、上の展示室にはヒサオも前に撮影した、建設されたものを含む、実際のプロジェクトが展示してある。ここにある模型は、作品の最初のアイディア模型だったり、初期案の模型だったり、プロジェクトの最終案的な模型だったり、いろいろな種類のものがあるけれど、ちょうど家族、あるいは種族のように皆関係しあっているんだ。
鈴木:ここにあるものがみんな何かから生まれ出て、その模型自身が何者かに育っていって、アレハンドロの手を借りて少しずつ現実の建築プロジェクトに変身していく、という事実が本当に興味深い。
ラディック:ここには実際に建ったもの、クライアントに向けて作られた模型、コンペに提出した模型、初期模型、「遊ぶ」ために作った模型など、「建築のプレゼンテーション」という目的のためだけではないさまざまな種類の模型があるのだけれど、アレハンドロが本当に上手く作ってくれるものだから、どの模型にも、たとえそれが単なるプロセスの途中経過を示した模型であったとしても、何か決定的な、あるいはリアルな様相が現れてきてしまうんだよね。僕はそういう感じがとても気に入っている。
鈴木:その感じ、とても良く分かるなあ。そして模型の中に心や頭といった君の何かが現れて来るんだね。その一方で、例えばこの人形の模型のように、見る人を戸惑わせるような、何処へ向かっていくのか分からなくなるようなモデルもあるけれど……。

▲「マイ・ファースト・タワー」(2016)
ラディック:このキューピー人形のモデルはこの中で一番新しい模型なんだけれど、最終到着地点はないんだ。つまり、何処へ向かっていくのかはまだ僕にも分からない。けれども、テーマとしては塔のスタディなんだ。ある日、考えているうちにキッチン用品のおろし金、というのはかっこいい塔になりうるかもしれない、と思って、ニューヨークにあるマリタイム・ホテルを見たら、その美しいホテルにはちょうどこのおろし金のように幾つもの孔があいていた。そしてこの人形はもともとは去年娘のために購入したセルロイド製のコレクション・ドールで、1912年に作られたものなんだ。それはあまりにもデリケートな人形だったので結局僕の娘はそれを壊してしまったのだけれど、そこからこの「マイ・ファースト・タワー」というプロジェクトができたんだ。その後アレハンドロが、この人形が実は日本製で、キューピーという名前のとても有名なキャラクターだということ僕に教えてくれたんだけれど、そのことを僕はそれまで全く知らなかったんだ。なのでそれを知った後、この「マイ・ファースト・タワー」という模型に、このキューピーの人形を、モデルとして置いたんだ。ここではキューピーがゴジラのように、この塔を、まるで自分のおもちゃを見せびらかすように紹介しているだろう。人形を置くという行為は、スケールの提示と関わっていて、でないとこの塔がどのくらい大きいのか、またはどのくらい小さいのかわからないからね。それによって模型の意味が全く違ってくる。実際、ここに展示されている模型の多くには、ヒトの模型が添えられているけれど、それはスケールを示すためであり、模型にリアリティを与えるためなんだ。この模型は玩具みたいに見えるかもしれないけれど、人形のおもちゃそのもので遊ぶのではなく、スケール感で遊んでいる、そういう模型なんだよ。
鈴木:なるほどね、ありがとう。今の君の話でいろいろな事が良く理解できたような気がするよ。ではそろそろそれぞれのプロジェクトについて話をしたいのだけれど、その前に、『エル・クロッキース』の撮影の時に僕たちが会った時の思い出について話してもいいかな。
ラディック:『エル・クロッキース』の出版は僕にとって、本当に大事な出来事だったよ。『エル・クロッキース』にとって、僕の号はラテンアメリカでの最初のモノグラフだと聞いていて。その頃僕は『エル・クロッキース』を巨大な出版社だと思い込んでいて、ここにディレクターや社長を携えた大きな取材班チームがやってくるのかと緊張して待っていたら、そこへ君たちが、つまり家族のような友達のような風情の三人組がやって来たんだもの(笑)。あの時はとても不思議な感じがしたなあ。と同時に君たちがとても魅力的に見えたんだ。
そのことはさておき、『エル・クロッキース』のモノグラフを作った時に、僕は、はじめて自分の仕事をグローバルに、包括的に理解するということ、あるいは少なくとも理解し始めようとつとめることを意識させられたんだ。普段の雑誌などの取材では、それぞれのケースでひとつひとつの作品を説明すれば良いだけだけれど、『エル・クロッキース』の時は、モノグラフとして、自分のすべてをここに集約しなければならないという状況に置かれて、自分の仕事をもう一度全体的な視野で捉え直して自分で理解しなければならなかった。それはとても良い経験になった。
そして同時に、君たちが僕のプロジェクトをどう「読む」のかを知ることができたことがとても素晴らしかった。君が撮っていたのは、美しい写真、というだけではなくて、その写真がプロジェクトの何を読んでいるのか、そしてその写真を通して読者にプロジェクトの何を読ませたいのか、ということが全部含まれていた。そういう事を僕はそれまで意識したことがなかったものだから。
いずれにしてもあれはものすごいストレスだったなあ。マルセラにも聞いてごらんよ(笑)。思えばサーペンタイン・ギャラリー・パヴィリオンのプロジェクトの時も同じような心境だった。パヴィリオンを作ってほしいという依頼を受けて、「何故ここにパヴィリオンを建てなければならないのか。彼ら(クライアント)は自分にどんなことを、何を置くことを望んでいるのだろうか」ということを強く考えさせられる。どちらも難しく複雑で、同時にとても素晴らしい経験になった。
鈴木:あの取材の時は、何日もの間、君という建築家、つまり建築作品の作者とずっと一緒に居ることができて、そのうちに徐々に君の人柄が伝わってきて、それは僕たちにとってもとても居心地がいい素敵な経験だった。おかげで、リラックスして落ち着いていい仕事ができたと思うんだ。君の住む土地についてもいろいろ深く理解することができたし……。そうだ、覚えている?「直角の詩に捧ぐ家」で君が僕に青い卵を見せてくれたのを。
ラディック:もちろん。
鈴木: 終日の撮影の後、着いたのは夕暮れ時でもう薄暗かった。みんながお腹を空かせてキッチンに集まってくると、ありがたいことにそこには大きな鍋が湯気をあげていて、中に大きめに切られたニンジン、トウモロコシ、ジャガイモ、ブロッコリーといった野菜が、彩りよくコトコト煮えていて。視線を移すと調理台のバスケットの中に青い塊が重なり合っているのが見えたので驚いて君に聞いたんだ。「スミルハン、これは何?」って。そしたら君は「卵だよ、うちの鶏が生んだんだ。」って。
君が閉じた掌を開くとそこにはモデルがあって、冗談とも真剣とも取れる言葉はまるで魔法のようだった。そして次の朝、君は朝食にその不思議な青い卵で目玉焼きを作ってくれて(笑)。それは一見、見慣れた白と黄色の目玉焼きだったけれど、僕らにとっては森の聖と山の神にもてあそばれているような気がした。僕らは君の生き方をそういうところに感じることができたんだ。
ラディック:なかなかいい演出だったでしょう?でもあのニワトリたち、そのあと犬に食べられてしまって一羽も残っていないんだ(笑)。あれをもう一度再現しようと思ったらまたあの鶏を調達しないとならないな。
鈴木:じゃあ、そろそろひとつひとつの模型を見ながら話をしようか。
(次ページへつづく)
鈴木:なるほどね、ありがとう。今の君の話でいろいろな事が良く理解できたような気がするよ。ではそろそろそれぞれのプロジェクトについて話をしたいのだけれど、その前に、『エル・クロッキース』の撮影の時に僕たちが会った時の思い出について話してもいいかな。
ラディック:『エル・クロッキース』の出版は僕にとって、本当に大事な出来事だったよ。『エル・クロッキース』にとって、僕の号はラテンアメリカでの最初のモノグラフだと聞いていて。その頃僕は『エル・クロッキース』を巨大な出版社だと思い込んでいて、ここにディレクターや社長を携えた大きな取材班チームがやってくるのかと緊張して待っていたら、そこへ君たちが、つまり家族のような友達のような風情の三人組がやって来たんだもの(笑)。あの時はとても不思議な感じがしたなあ。と同時に君たちがとても魅力的に見えたんだ。
そのことはさておき、『エル・クロッキース』のモノグラフを作った時に、僕は、はじめて自分の仕事をグローバルに、包括的に理解するということ、あるいは少なくとも理解し始めようとつとめることを意識させられたんだ。普段の雑誌などの取材では、それぞれのケースでひとつひとつの作品を説明すれば良いだけだけれど、『エル・クロッキース』の時は、モノグラフとして、自分のすべてをここに集約しなければならないという状況に置かれて、自分の仕事をもう一度全体的な視野で捉え直して自分で理解しなければならなかった。それはとても良い経験になった。
そして同時に、君たちが僕のプロジェクトをどう「読む」のかを知ることができたことがとても素晴らしかった。君が撮っていたのは、美しい写真、というだけではなくて、その写真がプロジェクトの何を読んでいるのか、そしてその写真を通して読者にプロジェクトの何を読ませたいのか、ということが全部含まれていた。そういう事を僕はそれまで意識したことがなかったものだから。
いずれにしてもあれはものすごいストレスだったなあ。マルセラにも聞いてごらんよ(笑)。思えばサーペンタイン・ギャラリー・パヴィリオンのプロジェクトの時も同じような心境だった。パヴィリオンを作ってほしいという依頼を受けて、「何故ここにパヴィリオンを建てなければならないのか。彼ら(クライアント)は自分にどんなことを、何を置くことを望んでいるのだろうか」ということを強く考えさせられる。どちらも難しく複雑で、同時にとても素晴らしい経験になった。
鈴木:あの取材の時は、何日もの間、君という建築家、つまり建築作品の作者とずっと一緒に居ることができて、そのうちに徐々に君の人柄が伝わってきて、それは僕たちにとってもとても居心地がいい素敵な経験だった。おかげで、リラックスして落ち着いていい仕事ができたと思うんだ。君の住む土地についてもいろいろ深く理解することができたし……。そうだ、覚えている?「直角の詩に捧ぐ家」で君が僕に青い卵を見せてくれたのを。
ラディック:もちろん。
鈴木: 終日の撮影の後、着いたのは夕暮れ時でもう薄暗かった。みんながお腹を空かせてキッチンに集まってくると、ありがたいことにそこには大きな鍋が湯気をあげていて、中に大きめに切られたニンジン、トウモロコシ、ジャガイモ、ブロッコリーといった野菜が、彩りよくコトコト煮えていて。視線を移すと調理台のバスケットの中に青い塊が重なり合っているのが見えたので驚いて君に聞いたんだ。「スミルハン、これは何?」って。そしたら君は「卵だよ、うちの鶏が生んだんだ。」って。
君が閉じた掌を開くとそこにはモデルがあって、冗談とも真剣とも取れる言葉はまるで魔法のようだった。そして次の朝、君は朝食にその不思議な青い卵で目玉焼きを作ってくれて(笑)。それは一見、見慣れた白と黄色の目玉焼きだったけれど、僕らにとっては森の聖と山の神にもてあそばれているような気がした。僕らは君の生き方をそういうところに感じることができたんだ。
ラディック:なかなかいい演出だったでしょう?でもあのニワトリたち、そのあと犬に食べられてしまって一羽も残っていないんだ(笑)。あれをもう一度再現しようと思ったらまたあの鶏を調達しないとならないな。
鈴木:じゃあ、そろそろひとつひとつの模型を見ながら話をしようか。
(次ページへつづく)
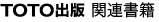
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。