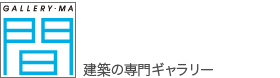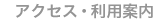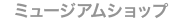- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

講演会レポート
文明の彼岸のビーチ・コーミング
レポーター=中山英之
スクリーンに大きく映し出された、半身鷲、半身ライオンの想像上の獣「グリフォン」を描いた一枚のドローイングを背景に、建築家は静かに語りだしました。
「これはコラージュです。特に絵が上手でなくても、それはできます。だから、神でなくとも、あなたにも、グリフォンを産み出すことができるのです。これから、私のグリフォンをお見せしましょう。そして、そのファミリーについてお話ししましょう。」
自らの仕事を想像上の獣になぞらえて、それを「コラージュ」と説明するのなら、彼の〈コラージュ=グリフォン〉にとっての鷲やライオンとは何でしょう。1時間弱の講演を通じて登場したそれらのメモを、ここにざっと書き出してみます。マッシモ・スコラーリの描いた、未来都市に流れ着いた方舟の絵。セドリック・プライスの「ファン・パレス・プロジェクト」を俯瞰するヘリコプター。ピラネージのエッチングやコルビュジエのリトグラフに描かれた洞窟。フラーやロトチェンコ、コンスタントによる、建築的な構造模型たち。建築家だけではありません。ブリューゲルの描いたバベルの塔。デイヴィッド・ホックニーのユーモラスなエッチング。オスカー・ワイルドが残した不思議な物語。マーチン・パーヤーの木製彫刻。テレビドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のイメージへの言及までありました。そのほかにも、誰かが道端に置いた小さな慰霊碑のスナップ。古いファッション誌の付録についていた洋服の型紙。壊れた安物のヴァイオリン。石ころや岩。さらには、それらを貼り合わせるための、少し黄ばんだマスキングテープまで…。
スクリーンに大きく映し出された、半身鷲、半身ライオンの想像上の獣「グリフォン」を描いた一枚のドローイングを背景に、建築家は静かに語りだしました。
「これはコラージュです。特に絵が上手でなくても、それはできます。だから、神でなくとも、あなたにも、グリフォンを産み出すことができるのです。これから、私のグリフォンをお見せしましょう。そして、そのファミリーについてお話ししましょう。」
自らの仕事を想像上の獣になぞらえて、それを「コラージュ」と説明するのなら、彼の〈コラージュ=グリフォン〉にとっての鷲やライオンとは何でしょう。1時間弱の講演を通じて登場したそれらのメモを、ここにざっと書き出してみます。マッシモ・スコラーリの描いた、未来都市に流れ着いた方舟の絵。セドリック・プライスの「ファン・パレス・プロジェクト」を俯瞰するヘリコプター。ピラネージのエッチングやコルビュジエのリトグラフに描かれた洞窟。フラーやロトチェンコ、コンスタントによる、建築的な構造模型たち。建築家だけではありません。ブリューゲルの描いたバベルの塔。デイヴィッド・ホックニーのユーモラスなエッチング。オスカー・ワイルドが残した不思議な物語。マーチン・パーヤーの木製彫刻。テレビドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のイメージへの言及までありました。そのほかにも、誰かが道端に置いた小さな慰霊碑のスナップ。古いファッション誌の付録についていた洋服の型紙。壊れた安物のヴァイオリン。石ころや岩。さらには、それらを貼り合わせるための、少し黄ばんだマスキングテープまで…。

彼にとっての鷲やライオンがそれらなら、「グリフォン」とは何でしょう。講演の中で紹介された彼の〈グリフォン=コラージュ〉は、たとえば2010年にTOTOギャラリー・間で催された展覧会のために作成された、「フラジャイル」と題された小さなオブジェです。4本のワイングラスを垂直に積み上げた危うげなタワーを、フラーやケネス・スネルソンのテンセグリティ構造を引用した金属とワイヤーで静止させたこのオブジェには、コンスタント、あるいはロトチェンコによるタワーのイメージがコラージュされている、という手短なコメントが添えられます。ただしこの立体コラージュが、デイヴィッド・ホックニーがグリム童話『あめふらし』を題材に描いたリトグラフに登場する「世界を見渡す王女の住む塔」の再現である、との説明を除いては、その機能や目的についての言及は一切なされません。コンスタントとは、コンスタント・ニーヴェンホイスのこと。彼は、超軽量金属で組み上げられ、雲のように永遠にその姿を変化させ続ける架空の空中都市計画「ニューバビロン」で知られる、オランダの芸術家です。ただ、この芸術家の主題にまつわる思考を軸に、「フラジャイル」に込められた建築家の主題を読み解こうと考えても、そこに確かな答えなど、用意されてはいないのでしょう。むしろこの建築家にとってコンスタントやロトチェンコのイメージは、まるで誤配送された絵葉書に刷られていた知らない文明の産物への、妄想にも似た好奇心と憧れのような存在としてあるかのようです。彼のオブジェはさながら、そこに読み取った未知の知性を、別の知性体が身の回りの日用品を使って再現する試み、とでも考えたほうが、よほどしっくりくる。じっさい、今回の展覧会に合わせて刊行された作品集に収録されているの藤本壮介との往復書簡の中でも、自分の行為をビーチ・コーミング(漂着物を素材としたアート)になぞらえているように。
さて、講演の冒頭で、彼は自作を「私のグリフォン」と呼びました。そして同時に、そのファミリーの話をする、とも言いました。「フラジャイル」が身長1メートル足らずの「グリフォン」なら、たとえば彼の事務所の設計によるサンティアゴのタワーは、身長150メートルを超えるそのファミリーである、ということになります。このアンテナ塔のコンペが事務所に舞い込んだとき、彼らは思考錯誤の中で、不意に、それをかつて制作した「フラジャイル」のファミリーとして構想すべきではないか、という確信に至ります。その確信とは何でしょう。塔とはふつう、建てられた場所にまつわる、何らかの知性を表象したシンボルであることを宿命づけられた存在です。ところがこの塔は、それとは全く異なる存在の仕方をすることに気づいた。それが、このプロジェクトにおける、彼らの「確信の瞬間」でした。「フラジャイル」のファミリーであること。それは、この塔の存在に、文明の彼岸の漂流物で組み上げられた、ビーチ・コーミングを眺めるような、あるいは、ある日郵便受けの中に、未来の消印の押された古ぼけた絵葉書を見つけるような、不可思議な印象を与えます。この世のどんな文脈に属することもない、けれども、私たち自身の存在が確かに投影された、既知と未知のあいだの領域に、このグリフォンの家系は棲んでいる。そんな存在の仕方を獲得した建築が、かつてあったでしょうか。
さて、講演の冒頭で、彼は自作を「私のグリフォン」と呼びました。そして同時に、そのファミリーの話をする、とも言いました。「フラジャイル」が身長1メートル足らずの「グリフォン」なら、たとえば彼の事務所の設計によるサンティアゴのタワーは、身長150メートルを超えるそのファミリーである、ということになります。このアンテナ塔のコンペが事務所に舞い込んだとき、彼らは思考錯誤の中で、不意に、それをかつて制作した「フラジャイル」のファミリーとして構想すべきではないか、という確信に至ります。その確信とは何でしょう。塔とはふつう、建てられた場所にまつわる、何らかの知性を表象したシンボルであることを宿命づけられた存在です。ところがこの塔は、それとは全く異なる存在の仕方をすることに気づいた。それが、このプロジェクトにおける、彼らの「確信の瞬間」でした。「フラジャイル」のファミリーであること。それは、この塔の存在に、文明の彼岸の漂流物で組み上げられた、ビーチ・コーミングを眺めるような、あるいは、ある日郵便受けの中に、未来の消印の押された古ぼけた絵葉書を見つけるような、不可思議な印象を与えます。この世のどんな文脈に属することもない、けれども、私たち自身の存在が確かに投影された、既知と未知のあいだの領域に、このグリフォンの家系は棲んでいる。そんな存在の仕方を獲得した建築が、かつてあったでしょうか。

「フラジャイル」(2010年) 「サンティアゴ・アンテナ・タワー」(2014年)の模型
「確信の瞬間(moment of conviction)」という言葉を、講演中、彼は何度が使いました。たとえば、先述の、『グリム童話』にまつわるデイヴィット・ホックニーの連作リトグラフを題材に、彼はいくつかの別のグリフォンたち、つまり「フラジャイル」のファミリーの系譜をコラージュしています。挿絵に登場する「卵に隠れた少年」や「魚に隠れた少年」といったイメージに形を与えるために、彼らはたとえば、動物の体の一部や、文字通りの漂着物である石ころを、壁紙やマスキングテープで型どりすることで、抜け殻のような薄い三次曲面のコラージュを制作していきます。こうして、目的や機能を想定せぬままに広がってゆくグリフォンの家系は、あるときにはチリ地震に遭遇した人々への思いを形にした、ヴェネチア・ビエンナーレのためのシェルターを構想する段階で、彼らに「確信の瞬間」をもたらし、またあるときには、オスカー・ワイルドの童話『わがままな大男』という新たな物語と交配することで、後に「サーペンタイン・ギャラリー・パヴィリオン」の構想に「確信の瞬間」をもたらすこととなる、また別のコラージュの素材へと転用されていく。そんなふうにして講演は、プロジェクトの詳細を、一体の獣にまつわる詳しい情報を掘り下げるように定義していくことをせぬまま、このグリフォンの子はこの獣であり、そしてその獣を親に持つこの獣は、また別の獣の抜け殻に棲みついたこの獣である、といった具合に展開していくので、私たちは、いつのまにかその眼前に、複雑で中心のない大きな家系図が、ゆらゆらと立ち上りつつあることに気づくことになるのでした。
たとえば、ある人の記憶の中の家系図には、もしかしたら「エンドレスハウス」(フレデリック・キースラー)の残像が一瞬、紛れ込んでいるかもしれません。あるいは、ボルヘスの短編『円環の廃墟』の一節が、渦巻いているかもしれない。じっさい僕の頭には、クルト・シュヴィッタースの名が、今もこだましています。もちろん、それらの名はきっと語られてはいないけれど、講演後、会場の質問からも、家系図の欠けた系譜を言い当てるように、それぞれの脳裏に浮かんだ名やイメージが建築家にぶつけられ、彼はそれらをひとつも否定することなく、丁寧に回答を試みる時間が続きました。
かつて、まだ世界中のほとんどの人々にとって、水平線のむこうがわが未開のフロンティアであった時代には、既知と未知のあいだのあいまいな領域に、グリフォンやケルベロスやペガサスや、つまりは既知のコラージュとしての獣たちが、ごく自然に棲んでいたのかもしれません。ただし、そこにあったかもしれない畏れや憧れを、彼らの蒙昧さを理由に笑うなら、今を生きる私たちは彼らより、何かを知っていると言えるのでしょうか。コラージュを、「現実で現実を超える術」と言ったのは、確かシュヴィッタースだったか。そうだとしたらスミルハン・ラディックとは、現代を生きる私たちにとっての未知の何かを、私たち自身の歴史とその内にもう一度、そして新たに築く術を照らす建築家なのかもしれません。
たとえば、ある人の記憶の中の家系図には、もしかしたら「エンドレスハウス」(フレデリック・キースラー)の残像が一瞬、紛れ込んでいるかもしれません。あるいは、ボルヘスの短編『円環の廃墟』の一節が、渦巻いているかもしれない。じっさい僕の頭には、クルト・シュヴィッタースの名が、今もこだましています。もちろん、それらの名はきっと語られてはいないけれど、講演後、会場の質問からも、家系図の欠けた系譜を言い当てるように、それぞれの脳裏に浮かんだ名やイメージが建築家にぶつけられ、彼はそれらをひとつも否定することなく、丁寧に回答を試みる時間が続きました。
かつて、まだ世界中のほとんどの人々にとって、水平線のむこうがわが未開のフロンティアであった時代には、既知と未知のあいだのあいまいな領域に、グリフォンやケルベロスやペガサスや、つまりは既知のコラージュとしての獣たちが、ごく自然に棲んでいたのかもしれません。ただし、そこにあったかもしれない畏れや憧れを、彼らの蒙昧さを理由に笑うなら、今を生きる私たちは彼らより、何かを知っていると言えるのでしょうか。コラージュを、「現実で現実を超える術」と言ったのは、確かシュヴィッタースだったか。そうだとしたらスミルハン・ラディックとは、現代を生きる私たちにとっての未知の何かを、私たち自身の歴史とその内にもう一度、そして新たに築く術を照らす建築家なのかもしれません。

中山英之 Hideyuki Nakayama
1972年生まれ。1998年、東京藝術大学建築学科卒業。2000年、同大学大学院美術研究科建築学専攻修士課程修了後、伊東豊雄建築設計事務所入所。「Bruges 2000 Pavillion」、「まつもと市民芸術館」、「多摩美術大学図書館」等を担当後、2007年に中山英之建築設計事務所設立。2014年より、東京藝術大学美術学部建築科准教授。
主な作品は、住宅「2004」(2006年)、「Yビル」(2009年)、「O邸」(2009年)など。主な受賞は、SD Review 2004鹿島賞(2004年 )、第23回吉岡賞(2007年)、六花の森Tea House Competition 最優秀賞(2008年)、D&AD Award、Red Dot Design Award best of the best(2014年)など。主な著書に『中山英之/スケッチング』。
主な作品は、住宅「2004」(2006年)、「Yビル」(2009年)、「O邸」(2009年)など。主な受賞は、SD Review 2004鹿島賞(2004年 )、第23回吉岡賞(2007年)、六花の森Tea House Competition 最優秀賞(2008年)、D&AD Award、Red Dot Design Award best of the best(2014年)など。主な著書に『中山英之/スケッチング』。
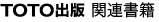
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。