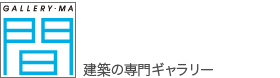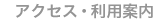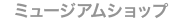- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

神戸講演会レポート
コラージュによるチリの新たなモダニティ
レポーター=谷 大蔵
2016年7月10日、TOTOギャラリー・間と神戸大学の共催プログラム、第40回神戸建築学スミルハン・ラディック神戸講演会「BESTIARY:寓話集」が神戸大学百年記念館六甲ホールで開催された。「神戸建築学」とは、第一線で活躍されている建築家や研究者の方々を招き、講演後には講師と神戸大学の大学院生・学部生との自由な討議の機会を設け、新たな環境創造における建築学の可能性を探る連続講演会である。有志の学生が主体となり、数か月前より運営や資料作成などの事前学習に取り組んできた。今回はスミルハン・ラディック事務所で働く日本人スタッフである原田雄次さんに日本語通訳を務めていただき、ラディック氏はスペイン語でレクチャーされた。
レクチャーが始まると、まずスクリーンに上半身がワシ、下半身がライオン、体の大きさが8倍もあるといわれる中世の幻獣「グリフォン」(『不思議の国のアリス』のジョン・テニエルの挿絵)が現れる。彼は寓話集のひとつとしてこのグリフォンを挙げ、彼のデザインはこのグリフォンと同じようにいくつかのグループごとのまとまり、すなわちコラージュからできていると語る。ゼロ・ベースから新しい概念を生み出すのではなく、過去にそこに在ったものを部分的にうまく組み合わせる、といった具合に。そのアイデアの根源は、ラディック氏の生きてきた時間の中での体験や発見であり、とかくデザインの引用元を秘密にしがちなわたしたち神戸大学の学生には斬新で、興味深い手法であっただろうとも感じる。
2016年7月10日、TOTOギャラリー・間と神戸大学の共催プログラム、第40回神戸建築学スミルハン・ラディック神戸講演会「BESTIARY:寓話集」が神戸大学百年記念館六甲ホールで開催された。「神戸建築学」とは、第一線で活躍されている建築家や研究者の方々を招き、講演後には講師と神戸大学の大学院生・学部生との自由な討議の機会を設け、新たな環境創造における建築学の可能性を探る連続講演会である。有志の学生が主体となり、数か月前より運営や資料作成などの事前学習に取り組んできた。今回はスミルハン・ラディック事務所で働く日本人スタッフである原田雄次さんに日本語通訳を務めていただき、ラディック氏はスペイン語でレクチャーされた。
レクチャーが始まると、まずスクリーンに上半身がワシ、下半身がライオン、体の大きさが8倍もあるといわれる中世の幻獣「グリフォン」(『不思議の国のアリス』のジョン・テニエルの挿絵)が現れる。彼は寓話集のひとつとしてこのグリフォンを挙げ、彼のデザインはこのグリフォンと同じようにいくつかのグループごとのまとまり、すなわちコラージュからできていると語る。ゼロ・ベースから新しい概念を生み出すのではなく、過去にそこに在ったものを部分的にうまく組み合わせる、といった具合に。そのアイデアの根源は、ラディック氏の生きてきた時間の中での体験や発見であり、とかくデザインの引用元を秘密にしがちなわたしたち神戸大学の学生には斬新で、興味深い手法であっただろうとも感じる。

通訳をする原田氏(左)とラディック氏
今回のレクチャーは、彼のここ数年のプロジェクトをオブジェのようなものから巨大なタワーまで13体の「グリフォン」について、そのプロジェクトごとの関係性という点から語られた。彼はその中でスケールを変えながらコラージュの素が転用されていくことで、それぞれの寓話が<ファミリー>という繋がりをつくり出すとも語る。はじめは、<ファミリー>という表現には違和感を感じていたのだが、彼の関係性の物語が展開されていくにつれて、わたしの中で紐解かれていった。
例えば、2010年の第12回ヴェネチア・ビエンナーレで発表されたインスタレーション「魚に隠れた少年」は、その年にチリであった大地震に対するシェルターとしての役割をもつのだが、これはデイヴィッド・ホックニーがグリム童話『あめふらし』の挿絵として描いた同タイトルのイメージをコラージュしたもので、作中での<隠れる>という行為をフィジカルなシェルターとして創出させるようにしている。
「フラジャイル」と名付けられたワイングラス製のタワー型のオブジェは、同じく『あめふらし』の作中に登場する王女の住む塔のイメージを表現したモデルである。ラディック氏は、これは建築的な根拠も背景も用途もない<ゲーム=遊び>でつくられたインスピレーションのモデルだと言っていたが、サンティアゴのタワーコンペではこのモデルを元に、60年前にバックミンスター・フラーが考案した「テンセグリティ」や、セドリック・プライスの「鳥かご」の安定した構造を用いながら、<フラジャイル=はかなさ>をもつデザインをしたという。
チリで「直角の詩に捧ぐ家」を設計した際は、ル・コルビュジエの詩画集『直角の詩』に収録されたリトグラフからシェルターの形や内外環境のあり方を見出す。これは、最初のビエンナーレのインスタレーション 「魚に隠れた少年」が異なるスケールをもって現れたものだと考えられており、両者には部分的に似た造形が施されている。
「サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2014」では、童話『わがままな大男』に出てくる大男の住む城のモデルと、ロマン主義時代のフォリーがもつ廃墟性を関連付けつつ、古いファッション誌の服の型紙から発見した窓の開け方など、内外の関係性は「直角の詩に捧ぐ家」と同じように考えている。
各々の作品の成り立ちはひとつに言語化されることなく、さまざまな題材から要素を結びつけて各々の寓話として完結させているのだが、このように彼の作品を羅列的に解釈していくと、コラージュの素が所々に転用されており、スケールが拡大・縮小され、それらがまるで血の繋がりのような家族関係を築いていることが<ファミリー>たる所以なのだと理解できた。またそれらは、仮設的な構造物やつかの間の隠れ家のような簡素で痕跡を残さないような作品たちを通して、移ろいゆく環境や人間の営みのはかなさを提案しているようであった。
例えば、2010年の第12回ヴェネチア・ビエンナーレで発表されたインスタレーション「魚に隠れた少年」は、その年にチリであった大地震に対するシェルターとしての役割をもつのだが、これはデイヴィッド・ホックニーがグリム童話『あめふらし』の挿絵として描いた同タイトルのイメージをコラージュしたもので、作中での<隠れる>という行為をフィジカルなシェルターとして創出させるようにしている。
「フラジャイル」と名付けられたワイングラス製のタワー型のオブジェは、同じく『あめふらし』の作中に登場する王女の住む塔のイメージを表現したモデルである。ラディック氏は、これは建築的な根拠も背景も用途もない<ゲーム=遊び>でつくられたインスピレーションのモデルだと言っていたが、サンティアゴのタワーコンペではこのモデルを元に、60年前にバックミンスター・フラーが考案した「テンセグリティ」や、セドリック・プライスの「鳥かご」の安定した構造を用いながら、<フラジャイル=はかなさ>をもつデザインをしたという。
チリで「直角の詩に捧ぐ家」を設計した際は、ル・コルビュジエの詩画集『直角の詩』に収録されたリトグラフからシェルターの形や内外環境のあり方を見出す。これは、最初のビエンナーレのインスタレーション 「魚に隠れた少年」が異なるスケールをもって現れたものだと考えられており、両者には部分的に似た造形が施されている。
「サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2014」では、童話『わがままな大男』に出てくる大男の住む城のモデルと、ロマン主義時代のフォリーがもつ廃墟性を関連付けつつ、古いファッション誌の服の型紙から発見した窓の開け方など、内外の関係性は「直角の詩に捧ぐ家」と同じように考えている。
各々の作品の成り立ちはひとつに言語化されることなく、さまざまな題材から要素を結びつけて各々の寓話として完結させているのだが、このように彼の作品を羅列的に解釈していくと、コラージュの素が所々に転用されており、スケールが拡大・縮小され、それらがまるで血の繋がりのような家族関係を築いていることが<ファミリー>たる所以なのだと理解できた。またそれらは、仮設的な構造物やつかの間の隠れ家のような簡素で痕跡を残さないような作品たちを通して、移ろいゆく環境や人間の営みのはかなさを提案しているようであった。

レクチャーを聴き終わって気づいたことは、わたしたちが事前にリサーチしていたときの解釈は間違えていた、というよりも、彼のデザインについて勘違いをしていたということであった。講演に向けてグループで事前学習に取り組んだが、その段階ではこの展覧会のテーマである「寓話集:BESTIARY」とは、例えば『あめふらし』や『わがままな大男』といった童話と彼の作品がリンクしていることを表すと捉えていた。しかし彼はマニュフェストを貫くことに興味はなく、たくさんの出発点、手段、方向性をつくり出すことの方が大事だと語っていたように、彼はもっと広く世界を見つめ直し、チリという国土において今、どのような建築が考えられるのかを示そうとしているようであった。
チリの現代建築は、太古からの歴史や文化と新しい技術や素材との融合を目指しており、海外からの影響とチリ独自の文化の間でどうあるべきかを模索しているようである。それは文化を守りながら現代的な生活を創造することへの挑戦であり、すなわちチリの建築家たちが、単純性、経済性、機能性に重きを置いていることの現れである。それぞれの建築家がチリの異なる文化に身を置くことによって生じる建築的多様性もチリ現代建築の特徴となっている。レクチャー後の質疑でもあったが、チリの著名な建築家のひとりであるアレハンドロ・アラヴェナ氏との関係性もまるで外国の建築家とのようだと語っていたように、チリという国の一般解をつくろうとしているのではなく、その多様性のひとつとしての個人の世界観を表しているようであった。
チリの現代建築は、太古からの歴史や文化と新しい技術や素材との融合を目指しており、海外からの影響とチリ独自の文化の間でどうあるべきかを模索しているようである。それは文化を守りながら現代的な生活を創造することへの挑戦であり、すなわちチリの建築家たちが、単純性、経済性、機能性に重きを置いていることの現れである。それぞれの建築家がチリの異なる文化に身を置くことによって生じる建築的多様性もチリ現代建築の特徴となっている。レクチャー後の質疑でもあったが、チリの著名な建築家のひとりであるアレハンドロ・アラヴェナ氏との関係性もまるで外国の建築家とのようだと語っていたように、チリという国の一般解をつくろうとしているのではなく、その多様性のひとつとしての個人の世界観を表しているようであった。

ラディック氏は、講演の中で何度か<ゲーム>や<遊び>という表現を用いて、グリム童話やデイヴィッド・ホックニーの挿絵のモデル(建築的な根拠も背景も用途もない模型)をいくつか紹介する。マスキングテープなどの日用品を素材に用いてつくられた模型たちは、「色あせたかけらを拾い集めて、再構築する」と藤本壮介さんとの往復書簡(TOTO出版から同時発行された作品集『スミルハン・ラディック 寓話集』に収録)でも述べているように、彼の前では、テンセグリティも、有名なリトグラフにこめられた空間も、チリにある原始的な仮設テントや石ころと同列に、過去という時間を背負いながらも、形骸化した素材に還元されているようだ。そしてそれらが、建築史のメインストリームとは遠く離れた、辺境の地であるチリに流れ着く。本来の時間の流れとは異なるが、そこに近代が打ち捨ててきた時間の価値が発生し、それがはかなさともつながるように感じる。他国の価値観や技術を、遠く離れた場所から時間をかけて「流れ着いた何か」であると捉え、ある意味遊びのようにそれらを組み立てて建築をつくる彼のデザインには、いずれチリを代表するかもしれない新たなモダニティの獲得が垣間見られるようである。

谷 大蔵 Daizo Tani
1993年、大阪生まれ
2016年、神戸大学工学部建築学科卒業(遠藤秀平研究室)
現在は、同大学大学院工学研究科の遠藤秀平研究室にて、デジタルファブリケーション等のコンピューテーショナルデザインを用いた設計手法に関する研究活動を行っている
2016年、神戸大学工学部建築学科卒業(遠藤秀平研究室)
現在は、同大学大学院工学研究科の遠藤秀平研究室にて、デジタルファブリケーション等のコンピューテーショナルデザインを用いた設計手法に関する研究活動を行っている
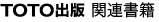
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。