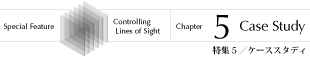
ところで「house I」は夫婦の日常の住まいである。住まわれていない状態の写真(今回掲載写真)から判断する限り、住まいとして本当に機能するのか、不安がよぎる。バラバラな壁の向きが落ち着きを奪うのではないか。定まらぬ視線の方向が不安感を増幅するのではないか。
訪れてみると、まったく逆であった。決して平行にならない壁は、内外のあちこちに不定形の小さなアルコーブ、小さな路地を生み、空間はよどみなく流れて停滞することがない。視線は壁の隙間を縫って、あるいは壁に斜めにあたってそれ、さらに先へと進み、遮られることがない。気配も同様、どの場所にいても気配が室内のすみずみまで届く。
ここでL字型の壁ユニットは遮断という働きから遠く離れ、壁が包むコーナーのそれぞれに、生活の営みの断片をおだやかに受け入れようとしている。ユニット相互の関係によって、受け入れ方の濃度は異なり、その濃度の分布が空間を染めている。
加えて現実の住み心地を高めているのが、内外の植物群である。屋外には小さな葉の形と細い幹をもったさまざまな樹木や野菜類が植えられ、屋内には葉肉の厚い、あるいは羊歯のような多種の植栽が配され、住まいとしての環境に潤いを与え、細やかな表情の変化をもたらしている。
こうして「house I」は、幾何学の遊戯に陥ることなく、日常の住まいとしての快適さを保証し、実現している。




