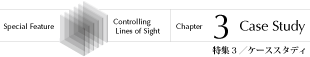
踊り場のないまわり階段を時計まわりに上っていく。途中、書庫、寝室、子ども室の扉を過ぎる。さらに上る。上昇感とともに、ますます明るさが増す。すると左手にキッチンが広がる。ここで初めて視線が窓から外へと延びていく。キッチンからは階段と同様の時計まわりに空間が上昇しつつ連続的につながっていく。ダイニング、リビング、和室、さらには洗面室、そして屋外の中庭へ。この一連の流れはみごとに自然である。この流れ、じつは下方の事務所として使われている部分までつながっている。つまりひとつの直方体の中に階段を介し、必要とされた14のスペースがひとつながりのらせん状に展開する構成になっているのである。そのつながりのなかで、視線はどこまでも途切れることなく斜めに延びる。バロック建築の特性としていわれる「視覚の斜方向性」。さらに階段室の開口、外壁の窓、トップライト。これらが視覚を枠取り、多様な変化をもたらしている。
図面からは、やや図式的な操作ではと思ったが、それはまったくの杞憂。部屋それぞれの用途への細やかな配慮があり、それが床レベルの微妙な設定に反映されている。型板ガラスとポリカーボネイト板の壁面は、外観以上に内部において効果的。四周にせまる建物の圧迫感が消されている。キッチンや洗面室など、北向きの場所の不利が解消されている。何より、ふわっとした浮揚感が室内を支配していて快適。
プラハの立体迷宮には洞窟のような奥深さがあり、コーナーのそれぞれに闇が宿っている。一方、東京の立体迷宮のほうは、開放と閉鎖の適度な中和があり、コーナーは明るさに満ちている。このふたつのラウムプランの住宅は、そのような違いを含みつつ、時空を超えて確かに響き合っている。




