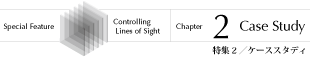
広さを感じさせるこの建築のもうひとつのセオリーは視線の貫通だ。
玄関扉を開くと視線はリビングを抜け、「屋外の家」の間庭を抜けて、その先の隣家の庭先を抜けていく。これが意識的に慎重に操作されている。
階段の踊り場に設けられた大きめの木の窓は、ガラスなしだから視線は通さない。開閉ふたつの役割しか果たさない。しかし、開け放ったときの開放感はガラス窓のもつ開放感の比ではない。あらためてガラス窓の意味が問われている気がする。
もうひとつ、くっきりと景色を切り取る窓枠の効果も大きい。
およそ6年前、保坂さんはガラスを木枠に外から張り付けることによって、景色をくっきりと切り取る窓がほしいと望んだという。窓メーカー「キマド」の社長と6時間かけてディテールを描き、やがて製品化された。その窓が全面的に採用され、ここに生きている。景色が一枚の絵でもあるかのように見えてくる。
窓を操作するこのふたつの手法によって、視線へのこだわりが形になっていると言えばいいだろうか。
「屋外の家」のふたつの部屋のひとつ、最大内法1200mmという2畳程度の書斎(自転車室)のテーブルに座ってみる。左手のサッシを開ければ間庭2の空間が隣室としてそこにある。母屋の家族の雰囲気も直接的に伝わってくる。
狭小をクリアした新しい世界が見える。東孝光さんの「塔の家」(1967)以来の狭小へのさまざまな挑戦の歴史、建築家の試みがあらためて思い起こされてくる。




