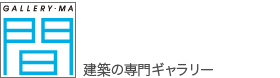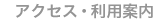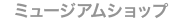- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

予習コラム
「建築のすそ野を広げたい」という想いで設立された編集事務所Office Bungaの磯達雄さんの視点から、「アンサンブル・スタジオ展 Architecture of The Earth」をより深く楽しむのに役立つ情報をお届けします。
アンサンブル・スタジオ展をより深く楽しむためのガイド(3)
今回、展示されているアンサンブル・スタジオの作品は、石やコンクリートの素材感や、雄大な環境に対峙するスケール感といった、誰にでもストレートに伝わる魅力を備えている。その一方で、発注者の機能的要求にこたえて設計するといった通常の建築設計のプロセスを経ていないため、設計者の意図が見えにくいという面ももっている。展覧会の会場を訪れれば、それなりに納得がいくのだが、関連する動画コンテンツも公開されているので、理解を補助するものとして、これらを見ておくのもよいだろう。
ひとつは、アンサンブル・スタジオを主宰するアントン・ガルシア=アブリルとデボラ・メサの二人による講演だ。TOTOギャラリー・間の展覧会では、通常、ホールで聴講者を集めて行うが、今回は新型コロナウィルスの感染拡大により、出展者の建築家も来日がかなわず、オンラインでの開催となった。肉声を聴けないのは残念だったが、アンサンブル・スタジオの二人がレクチャーをしている場所として映し出されるのは、展覧会でも取り上げられている彼らの活動拠点「カン・テラ(大地の家)」である。採石場の跡地を改造した無類の空間を背景として、語られる内容はいっそう説得力を増しており、これはオンラインならではの良さもあると感じられた。動画には、彼らの実作品やプロトタイプ(展示されているものは模型というより、この言葉のほうが的確だろう)を制作するプロセスも挟み込まれているので、これを見れば、彼らがそれぞれのプロジェクトで何を企てたのかが丸わかりだ。
アンサンブル・スタジオ講演会「Architecture of The Earth」
またTOTOギャラリー・間の展覧会では、期間中に数度、展覧会場でのギャラリートークも行なっている。これも今回は無観客のオンライン開催として2回が実施された。
1回目は、ナビゲーターに建築史家のセン・クアン氏を迎え、アンサンブル・スタジオの二人と建築家の藤本壮介氏がリモートで語り合った座談会だ。興味深い論点は、両者の作品の共通性だ。藤本氏によれば、人間の意図を超えた何かに空間を見出すことによって建築を生み出そうとしているところが似ているという。一方、アンサンブル・スタジオのアントン・ガルシア=アブリルは、TOTOギャラリー・間で2015年に開催された「藤本壮介展 未来の未来」に触れ、身の回りのさまざまな物が建築へと置き換えられた展示に共感を寄せる。そして、そこに見られるスケールレスの状態が、建築の新たな可能性を開くのだとする。刺激的なディスカッションだ。
ギャラリートークの第2回は、建築家の山道拓人氏(ツバメアーキテクツ)の進行により、建築家の澤田航氏(Sawada Hashimura)と橋村雄一氏(同)、デザイナーの狩野佑真氏(studio yumakano)が、アンサンブル・スタジオのさまざまな側面を語り合う。通常の建築設計とまったく違うのは、コンセプトがないままいきなり具体的な形が生み出されている点だという。また「宇宙人がつくった建築みたい」との評言も印象的だ。
いずれの動画コンテンツも、アンサンブル・スタジオの作品について学べるだけでなく、建築を設計する行為とはどういうことなのかを問い直す内容にもなっている。展覧会を鑑賞した後に、見返してもらうのもよいだろう。
アンサンブル・スタジオ展ギャラリートーク 「Form, Structure, and Space of Nature」
第1回テーマ:How Heavy? How Light?
出演:アントン・ガルシア=アブリル、デボラ・メサ(建築家/アンサンブル・スタジオ)
藤本壮介(建築家/藤本壮介建築設計事務所)
ナビゲーター=セン・クアン(建築史家/東京大学特任准教授、『a+u』誌チーフ・エディトリアル・アドヴァイザー)
第2回テーマ:テクトニクスのありか
出演:澤田航、橋村雄一(建築家/Sawada Hashimura主宰)
狩野佑真(デザイナー/studio yumakano 主宰)
ナビゲーター=山道拓人(建築家/ツバメアーキテクツ代表、法政大学山道拓人研究室主宰)
参考リンク)
■講演会「アンサンブル・スタジオ講演会 Architecture of The Earth」(動画有)
■ギャラリートーク「アンサンブル・スタジオ展ギャラリートーク Form, Structure, and Space of Nature」(動画有)
■展覧会「藤本壮介展 未来の未来」(動画有)
■講演会「アンサンブル・スタジオ講演会 Architecture of The Earth」(動画有)
■ギャラリートーク「アンサンブル・スタジオ展ギャラリートーク Form, Structure, and Space of Nature」(動画有)
■展覧会「藤本壮介展 未来の未来」(動画有)
アンサンブル・スタジオ展をより深く楽しむためのガイド(2)
連載2回目は、TOTO出版から発行した作品集『大地の建築 アンサンブル・スタジオ』の編集とブックデザインに協力いただいた、スペイン・バルセロナ在住の坂本知子さんへのインタビューをもとに構成します。コラボレーションを通じて坂本さんが体感したアンサンブル・スタジオのグローバルな空気や、彼らを読み解く際のヒントなどについてお話しいただきました。
ーーー坂本さんがアンサンブル・スタジオと出会うきっかけは何でしたか。
坂本:わたしがスペインに来たのは、建築家のエンリック・ミラージェスのところで修行するためでしたが、2年後彼が亡くなってしまって、その後アクタール(Actar Publishers)という建築出版社で書籍の編集とデザインの仕事をするようになりました。この出版社が2011年にミース・ファン・デル・ローエ賞のカタログを手がけた際、そこにアンサンブル・スタジオによる「トリュフ」が載っていたんです。これを見たときに、とても印象深かったのですが、それが彼らの作品との出会いですね。スペインで彼らの名前が知られるようになったのも、この作品がきっかけだったと思います。
今回、展覧会に合わせて彼らの書籍の出版プロジェクトに参加させていただくことになり、コロナ前でしたがたまたまバレンシアでアントン・ガルシア=アブリルさんのレクチャーがあったので、聴きに行きました。ご本人にお会いしたのは、その時が最初です。
今回、展覧会に合わせて彼らの書籍の出版プロジェクトに参加させていただくことになり、コロナ前でしたがたまたまバレンシアでアントン・ガルシア=アブリルさんのレクチャーがあったので、聴きに行きました。ご本人にお会いしたのは、その時が最初です。
ーーーアンサンブル・スタジオの作品は、実際に見ましたか。
坂本:「ヘメロスコピウム・ハウス」と、彼らの事務所である「アンサンブル・プレイス」を訪れました。これらの作品は工業製品的というか、理詰めで考えて精密に設計された作品です。一方で、「トリュフ」やレクチャーで最新作として紹介された「カン・テラ(大地の家)」は、非常にアート的な作品で、そこに機能をもった空間がつくり上げられている。両者はまったく分裂しているような印象なのですが、実は通じているところがあり、それが何なのかを、書籍をつくりながら学んでいったという感じです。

トリュフ(スペイン、コスタ・ダ・モルテ、2010)
TOTO出版『大地の建築 アンサンブル・スタジオ』より
TOTO出版『大地の建築 アンサンブル・スタジオ』より

カン・テラ(大地の家)(スペイン、メノルカ島、2010)
TOTO出版『大地の建築 アンサンブル・スタジオ』より
TOTO出版『大地の建築 アンサンブル・スタジオ』より
ーーーまずは今回、展示の中心となっている大地と対話するようなアート的な作品について、うかがいたいと思います。アメリカでも多くの作品を手がけていますね。
坂本:私が一番見てみたいのは、「ランドスケープの構造体」という一連のプロジェクトです。「トリュフ」を見たとあるクライアントが、これはいけるということで、似たようなことを、アメリカの雄大な風景の中、10倍くらいのスケールで建てるチャンスを彼らに与えたのです。岩や山のようなスケールのものが、影をつくって、集まってくる人や動物のシェルターになる。さらには、音響反射板にもなって、コンサートホールとしても機能するという。一見、ランド・アートのように受け取られそうですが、建築として成り立っている。限りなく計算されているな、と思います。
そして、現在これをさらにもっと大きくした「砂漠の岩」というプロジェクトをサウジ・アラビアで進めていて、これは高層建築並みのサイズが想定されています。小さなものから順に、スケールアップしながら実現させているのでこのような極端な建築も夢物語に聞こえないのです。それはさすがだな、と思います。
そして、現在これをさらにもっと大きくした「砂漠の岩」というプロジェクトをサウジ・アラビアで進めていて、これは高層建築並みのサイズが想定されています。小さなものから順に、スケールアップしながら実現させているのでこのような極端な建築も夢物語に聞こえないのです。それはさすがだな、と思います。

ランドスケープの構造体ドーモ(丸屋根)
(米国、モンタナ州、ティペット・ライズ・アート・センター、2016) ©Iwan Baan
(米国、モンタナ州、ティペット・ライズ・アート・センター、2016) ©Iwan Baan

「砂漠の岩」(サウジ・アラビア、アル・ウラー、2020)
TOTOギャラリー・間 「アンサンブル・スタジオ展 Architecture of The Earth」より
TOTOギャラリー・間 「アンサンブル・スタジオ展 Architecture of The Earth」より
ーーー書籍には、初期作品としてサンティアゴ・デ・コンポステラで手がけた作品も紹介されていました。
坂本:「音楽高等学校」と「スペイン著作権協会本部」ですね。これらの建物は、私も後から知りました。改めて見直すと、このふたつの建物に彼らの本質が既に現れています。「音楽高等学校」では、この地方で採れる石を切り出して使い、その石切場で出る余りの素材をもうひとつの「スペイン著作権協会本部」では使っています。図と地の関係で、対になっているわけです。彼ららしいのは、素材を探しに現地へ行って、そこにその事務所を構えてしまって、つくりながら考えるというやり方をしたところですね。
ーーーガリシア地方は石の産地ですから、地域と結びついた素材として石を使ったということでしょうか。
坂本:大西洋に面したガリシアは、荒々しい海に向かってゴツゴツした岩が連なる景色のところです。だから石を使うにしても、カタログに載っているきれいに切られた石でつくることには抵抗があった。それで石切場まで行って、4カ月くらい、ああでもないこうでもないと試しながら石をひとつずつ積んでいき、それをスキャニングして模型に置き換え、事務所でまた入れ替えたりしたのちに、それを石に戻して組む。納得する形ができたら、崩して運んで現場でまた組み立てる。手を動かしてつくっているなあ、と強く感じます。
ーーー石で建築をつくるということ自体は、ガリシア地方であれば割と普通に考えられるのでしょうが、アンサンブル・スタジオの場合は、それをどうやって組み上げていくのか、工法というところに一番の関心がある。そこが彼らの特徴なのかなと思います。
坂本:そのとおりです。そこにある素材を使って、何ができるかを考えるということでしょうね。もし彼らが日本で何か手がけるとしたら、木を使って何か新しいものをつくってくれるのかもしれません。与えられた素材があったとしても、その使い方をゼロから考えているんですよね。
コンクリートという素材へのアプローチも、彼らは独自です。コンクリートと言われて思い浮かぶのはもちろん固体ですよね。でもコンクリートというのは、固まる前は液体なんです。それを使って、例えば「トリュフ」でも、土を掘ってその穴に流し込んだり、積んだ干し草の上に鉄筋を入れてそのうえにかけたりしている。コンクリートを固体として扱っていないんです。
できあがったコンクリートは、ごつごつした表面で、着いている土に植物の種が飛んできて、草が生えています。整えられた緑化とは全然ちがって、何万年も前からそこにあったような様相を見せています。そういうタイムスケール感を、意図してか意図せずか、表せているのはすごいなと思います。
コンクリートという素材へのアプローチも、彼らは独自です。コンクリートと言われて思い浮かぶのはもちろん固体ですよね。でもコンクリートというのは、固まる前は液体なんです。それを使って、例えば「トリュフ」でも、土を掘ってその穴に流し込んだり、積んだ干し草の上に鉄筋を入れてそのうえにかけたりしている。コンクリートを固体として扱っていないんです。
できあがったコンクリートは、ごつごつした表面で、着いている土に植物の種が飛んできて、草が生えています。整えられた緑化とは全然ちがって、何万年も前からそこにあったような様相を見せています。そういうタイムスケール感を、意図してか意図せずか、表せているのはすごいなと思います。
ーーーアンサンブル・スタジオのようなスタンスの建築家は、スペインにはほかにもいるのでしょうか。
坂本:たとえばエンリック・ルイス・ジェリ(Enric Ruiz-Geli)というバルセロナの建築家は、セラミック、ガラスなどの素材をそれまでにないような使い方をして目を引きます。しかし、それはハイテックな技術です。アンサンブル・スタジオのように、原始的で洗練されていない方法にあえて突き進むという傾向は、彼ら独自のものです。エコロジーとか、情報化とか、未来を見据えた新しい建築をつくろうとする人はたくさんいますが、アンサンブル・スタジオの場合は、どちらかというとあまりそういうことは気にしていないようにさえ見えるのです。でも現代建築のなかで100年後、あるいは1000年後に残っているものはどちらかというと、アンサンブル・スタジオの作品の方だという気もします。
ーーーお話をうかがっていて連想したのは、鉄筋コンクリート造の「蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)」にセルフビルドで取り組んでいる岡啓輔さんです。彼も自分がつくるコンクリートは200年は保つと言っていて、コンクリートの打設方法もいろいろと工夫しています。あるいは、西沢立衛さんが設計した「豊島美術館」(2010年)や、石上純也さんが設計した「House & Restaurant」(2021年竣工予定)。これらの建物では、コンクリート打設後に土を掘り返して空間を生み出していきました。何をつくるかと同時に、どうつくるのかが考えられています。

岡啓輔によるセルフビルドで建設が進行中の「蟻鱒鳶ル」
坂本:アンサンブル・スタジオの作品は、世界を見渡しても類例がないととらえられてきましたが、日本に共通性をもったものがあるというのは面白いですね。共感をもって、受け入れられるかもしれません。
ーーースペイン建築界において、アンサンブル・スタジオはどのような位置にあると理解すればいいでしょうか。
坂本:まず押さえておいてほしいのは、彼らはスペインの建築家としてあまり見られていないかもしれない、という点です。ふたりともマドリード工科大学を卒業されていますが、現在、米国に拠点を置き、そこで教鞭をとりながらマドリードの事務所やメノルカ島をはじめ世界中を行き来しながら仕事をしているようです。
ーーー日本から見ると、どうしてもスペインの建築家としてひとまとめに見がちですが、それぞれの建築家からすると、スペインの出身を特にアイデンティティーにしてはいないということでしょうか。
坂本:そういう意味では、TOTOギャラリー・間で2019年に展覧会を行ったRCRアーキテクツとは対照的です。RCRアーキテクツは、ものすごく地元への意識が強くて、スペインのカタルーニャ地方にあるオロットという町に根ざした建築をつくるということにこだわっていました。

TOTOギャラリー・間「RCRアーキテクツ展 夢のジオグラフィー」
©Nacása & Partners Inc.
©Nacása & Partners Inc.
設計の進め方も、顔を付き合わせてああでもないこうでもないと話をしながら、紙の上に線を重ねてつくっていく。一方、アンサンブル・スタジオは、働き方もつくり方もものすごくインターナショナルです。今回の書籍をつくることになって、初めて打ち合わせをしたのは、コロナ禍の前でしたけれども、すでにオンライン・ミーティングでした。アントンさん、デボラさんがボストンにいて、わたしがバルセロナにいて、別のスタジオ・スタッフがマドリードや、「カン・テラ」があるメノルカ島から参加する。地球のいろいろなところにいる人たちがパッとつながって、「今日は何語で話しましょうか?」みたいな感じで、会議が始まりました。設計も大量のデータをオンラインで共有しながら、たくさんのスタッフが意見を言い合ってつくっていく。土地に根ざさないグローバルな働き方には、正直、びっくりしました。
ーーースペイン出身の建築家では、たとえばアレハンドロ・ザエラ・ポロもグローバルな活動をしている建築家ですよね。
坂本:彼はスペイン出身ですが、ロンドンに事務所を置き、現在は米国で活動しています。FOA(フォーリン・オフィス・アーキテクツ)というかつての事務所名にも表れているように、自分は外国人であるという意識を強く持っていました。そういうスペイン人建築家は、割といるかもしれないですね。日本の建築家だと、日本の文化をルーツにもっていることを誇りに思う人が多いですよね。もちろんスペインにも誇るべき文化はたくさんある。でもそこから抜け出したい願望も強い。「俺たちのことをスペイン建築家と呼ぶな」、それが逆にスペイン人気質なのかもしれません。
ーーーヨーロッパのこの20年間の建築状況を見ると、大雑把にいってふたつの大きな流れがあったように思います。ひとつはグローバリズムで、もうひとつは地域主義です。なかでもグリーバリズムは、レム・コールハースや、その事務所のOMAから巣立ったザハ・ハディド、MVRDV、BIGといった面々を中心に、大きな勢力となりました。スペインもまた、そうだったわけですね。
坂本:スペインの国内事情も関係しているでしょう。2008年からの世界不況の後、十分に景気が回復しないままの状況が続いています。なので、建築家として活躍するためには国外にプロジェクトを探さざるをえない。スペイン人は言葉の通じる中南米で仕事をしやすいという面もあります。
ーーーなるほど。でも、とても意外でした。アンサンブル・スタジオはガリシア特産の石を使ったりして、一見、地域主義者に映るけれども、実はコールハースらと並ぶグローバリストに位置付けられるとは。
坂本:ある土地があってそこに建物を建てるというときに、そのまわりに建っている建物や文化だけを参照するのではなく、もっと長い地質学的な時間でできあがっているものも見ているということなんだと思います。目の前に広がる地形とか海岸線とか。
ーーーコンテクストをとらえるときの視野が広いということでしょうか。
坂本:そう、スケールがちがう。それと彼らが愛用するコンクリートという素材はグローバルな素材で、それを地面を型枠にしてつくります。地面はローカルなものだけれど、それは文化的コンテクストとは無関係で、もっと原初的なものです。大地から生み出された建築、それが今回の書籍のタイトル(『大地の建築 アンサンブル・スタジオ』)にもなっています。
ーーー確かに、普遍的な建築と言うか、根源的なところを追い求めている感じがします。
坂本:重要なのは、彼らが建築家であり、彼らにとってはすべてが設計行為として見なされているということです。今回の書籍にいわゆる平面図や断面図はほとんど載っていませんが、アントンさんは「カン・テラ」を3Dスキャンした不定形なボリューム図を示して「これが僕たちにとっての図面なんだ」とおっしゃっていました。そこにあるのは既存の洞窟の内皮境界面なのですが、それこそが彼らにとっての建築ととらえて設計したということなんだと思います。内部空間のインスタレーションではなく。
ーーーアーティストではない、あくまでも建築家であるということですね。
坂本:今回、TOTOギャラリー・間の展覧会では、アーティスティックに見えてしまうタイプの作品を集めているので、初めてアンサンブル・スタジオの作品を見る人は誤解してしまうかもしれません。彼らはそれぞれ大学で教鞭をとっていて、そこでは低所得者向け住宅の研究など、都市問題の解決にも取り組んでいます。建築の工業化やプリファブリケーションもテーマにしており、「シクロピアン・ハウス」では、マドリードで制作した部材をコンテナで輸送し、米国で組み立てました。スペインの建築でもない、米国の建築でもない、地球の建築。そういう意味で、これも「Architecture of The Eearth」です。正反対のことをやっているようですけれども、共通性があります。
「ランドスケープの構造体」のような作品も、彼らにとっては十分に合理性のある建築です。建築をサステイナブルにしたい。どうすればそれは可能なのか、と考えた時にひとつの最適解が、「ランドスケープの構造体」のようなものなのではないか。岩が立っているだけで、インテリアもエクステリアもない、しかしこれは1000年間も存在して、強い日差しから人々を守ってくれる。そしてすてきな音響効果を与えてくれるコンサートホールとしても使われ続ける。このようにとらえると、超持続的な建築にも受け取れるのです。経済性を追求した工業化とは真逆のように見えるけれども、サステイナビリティの追求というロジックはかけ離れてはいない。アンサンブル・スタジオの建築を、そういうふうに見てみると、面白いと思います。
「ランドスケープの構造体」のような作品も、彼らにとっては十分に合理性のある建築です。建築をサステイナブルにしたい。どうすればそれは可能なのか、と考えた時にひとつの最適解が、「ランドスケープの構造体」のようなものなのではないか。岩が立っているだけで、インテリアもエクステリアもない、しかしこれは1000年間も存在して、強い日差しから人々を守ってくれる。そしてすてきな音響効果を与えてくれるコンサートホールとしても使われ続ける。このようにとらえると、超持続的な建築にも受け取れるのです。経済性を追求した工業化とは真逆のように見えるけれども、サステイナビリティの追求というロジックはかけ離れてはいない。アンサンブル・スタジオの建築を、そういうふうに見てみると、面白いと思います。
坂本知子(さかもとともこ)
早稲田大学建築学部修士課程卒。1998年渡西。EMBT建築事務所、Actar Publishersを経て、2012年David LorenteとSpreadを共同設立。建築や都市計画、デザインなどに関する本の編集やデザインを手掛ける。
TOTO出版のその他の仕事として、『RCRアーキテクツ 夢のジオグラフィー』がある。
TOTO出版のその他の仕事として、『RCRアーキテクツ 夢のジオグラフィー』がある。

アンサンブル・スタジオ展をより深く楽しむためのガイド(1)
アンサンブル・スタジオの名前に初めて接する人も多いだろう。アントン・ガルシア=アブリルとデボラ・メサの二人が主宰するチームで、2000年にスペインで設立された。ガルシア=アブリルはマサチューセッツ工科大学、メサはジョージア工科大学で教鞭をとっており、現在はスペインと米国の両方を拠点として活動している。プレファブリケーションの技術を究めた住宅の設計を行う一方、自然素材を大胆な工法で組み上げた環境彫刻的な作品にも取り組む。今回の展示では、後者の系統にあたる作品が紹介される。代表作を見ていこう。
初期の作品で注目すべきは、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステラで手がけた2つの作品だ。巨石文明が栄えた地で、彼らは石を建築に大胆に使った。音楽高等学校(2003年)では、採石場で切り出した石を、表面の加工を行わずにそのまま外装材とした。スペイン著作権協会(2007年)では、採石場に捨てられていた不整形な廃材を、セルフビルドで組み上げている。これらの建築を構成しているのは、設計されたものではなく、荒々しいままの素材である。
初期の作品で注目すべきは、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステラで手がけた2つの作品だ。巨石文明が栄えた地で、彼らは石を建築に大胆に使った。音楽高等学校(2003年)では、採石場で切り出した石を、表面の加工を行わずにそのまま外装材とした。スペイン著作権協会(2007年)では、採石場に捨てられていた不整形な廃材を、セルフビルドで組み上げている。これらの建築を構成しているのは、設計されたものではなく、荒々しいままの素材である。

スペイン著作権協会本部(スペイン、サンティアゴ・デ・コンポステラ、2007)
©Iwan Baan
©Iwan Baan
彼らの取り組みがさらに発展していくきっかけとなったのが、トリュフ(2010年)と言えるだろう。この作品では、地面を掘って干し草を積み上げたのち、周りの土を型枠としてコンクリートを打って躯体をつくった。そしてその後、子牛に干し草を食べさせることにより、内部空間を生み出したのである。ここで建築家は、設計どころか施工のコントロールも自らの手から離してしまっている。続いて米国で手がけた「ランドスケープの構造体」(2016年)と呼ばれる一連の作品では、大地を型枠として打ったコンクリートを、クレーンで建て起こして、原初的な空間を生み出している。その姿は、古代に築かれたストーンヘンジのようでもある。建築とはそもそも何か? そんな問いかけを、彼らの作品は見る者ひとりひとりに突きつけてくる。

トリュフ(スペイン、コスタ・ダ・モルテ、2010)
©Iwan Baan
©Iwan Baan

ランドスケープの構造体インバーテッド・ポータル(裏返された門)
(米国、モンタナ州、ティペット・ライズ・アート・センター、2016)
©Iwan Baan
(米国、モンタナ州、ティペット・ライズ・アート・センター、2016)
©Iwan Baan
近年の世界的な建築設計界の主流は、抽象的なデザインの追求や社会的な問題の解決といったテーマだったように思う。そのなかで、建築の根源的なあり方を探るアンサンブル・スタジオのアプローチは異色と言える。しかし孤立した動きではなく、日本にでも例えば西沢立衛の設計による「豊島美術館」(2010年)や、石上純也が設計した「House & Restaurant」(進行中)といった、共通の志向がうかがえる。あるいは、セルフビルドで建設を続けている岡啓輔の自邸「蟻鱒鳶ル」や、そのルーツである高山建築学校の活動も思い起こされた。それぞれに孤立した追及と見えていたが、実はつながった流れなのかもしれない。地面下に流れるラディカルな建築の水脈について、この展覧会で確かめてみたい。
磯達雄 Tatsuo Iso
編集者・1988年名古屋大学卒業。1988~1999年日経アーキテクチュア編集部勤務後2000年独立。2002年~20年3月フリックスタジオ共同主宰。20年4月から宮沢洋とOffice Bungaを共同主宰。
https://bunganet.tokyo/
https://bunganet.tokyo/

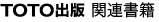
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。