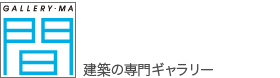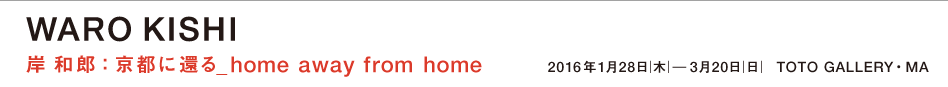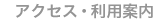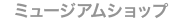- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

講演会レポート
<建築>のアルカディアから
レポーター=日埜直彦
レクチャーのレポートがこのテクストの役割ではあるのだが、どうもこのレクチャーには一種のゴーストノートがあって、それをまず踏まえておかないことには見通しが悪いようだ。
そんなわけでのっけからやや大げさな話に迂回をした上で、それを裏地としてこのレクチャーのレポートをまとめてみよう。ヴィラ・アドリアーナである。ハドリアヌス帝の別荘として2世紀に建造されたこの建築群は、ローマ帝国が栄華を極めた時代の広大な版図のあちらこちらの風景・建築を模して作られた。ローマ郊外、ティボリの丘陵地に築かれたこの建築群は、コーリン・ロウが『コラージュ・シティ』においてリファレンスしたことで、20世紀後半になって建築論的テーマのひとつの象徴となった。
ロウがこれを取り上げて提起した問題とはこういうものだ。つまり、仮に各々の建築が完璧に作られ、その完璧さの集積として都市が出来たとして、その都市は果たして「良い」だろうか?彼はヴェルサイユ宮の壮麗さ、徹底性、そして緊密な秩序が結局は全体としては単調で非都市的な退屈さに結果していると述べ、それをモダニズムの都市の貧しさに繋げつつ、それとヴィラ・アドリアーナに実現している複雑さ、都市性と対比させた。ヴィラ・アドリアーナは、さまざまな様式で勝手気侭に建造された建築からなり、そこに全体を統合する秩序は見えないが、しかしそれがゆえにこそある複雑で豊かな都市性を実現しているではないか、というわけだ。
コーリン・ロウの名はいわゆるポストモダニズムを連想させるかもしれないが、すくなくとも表層的な歴史的意匠のパッチワークで建築を装うようないわゆるポストモダニズムはロウとは無縁のもので、彼はその種の何でもありの折衷主義がモダニズムの単調さの解決ないし修正となるなどと考えたことは一度もなかった。むしろ建築はそれぞれにある種の没入的な一貫性であるほかなく、しかしそれが集積したコラージュが都市性を持ちうる可能性にモダニズムの本性的限界を乗り越える可能性を見た。ヴィラ・アドリアーナはそうしたヴィジョンの象徴である。
レクチャーのレポートがこのテクストの役割ではあるのだが、どうもこのレクチャーには一種のゴーストノートがあって、それをまず踏まえておかないことには見通しが悪いようだ。
そんなわけでのっけからやや大げさな話に迂回をした上で、それを裏地としてこのレクチャーのレポートをまとめてみよう。ヴィラ・アドリアーナである。ハドリアヌス帝の別荘として2世紀に建造されたこの建築群は、ローマ帝国が栄華を極めた時代の広大な版図のあちらこちらの風景・建築を模して作られた。ローマ郊外、ティボリの丘陵地に築かれたこの建築群は、コーリン・ロウが『コラージュ・シティ』においてリファレンスしたことで、20世紀後半になって建築論的テーマのひとつの象徴となった。
ロウがこれを取り上げて提起した問題とはこういうものだ。つまり、仮に各々の建築が完璧に作られ、その完璧さの集積として都市が出来たとして、その都市は果たして「良い」だろうか?彼はヴェルサイユ宮の壮麗さ、徹底性、そして緊密な秩序が結局は全体としては単調で非都市的な退屈さに結果していると述べ、それをモダニズムの都市の貧しさに繋げつつ、それとヴィラ・アドリアーナに実現している複雑さ、都市性と対比させた。ヴィラ・アドリアーナは、さまざまな様式で勝手気侭に建造された建築からなり、そこに全体を統合する秩序は見えないが、しかしそれがゆえにこそある複雑で豊かな都市性を実現しているではないか、というわけだ。
コーリン・ロウの名はいわゆるポストモダニズムを連想させるかもしれないが、すくなくとも表層的な歴史的意匠のパッチワークで建築を装うようないわゆるポストモダニズムはロウとは無縁のもので、彼はその種の何でもありの折衷主義がモダニズムの単調さの解決ないし修正となるなどと考えたことは一度もなかった。むしろ建築はそれぞれにある種の没入的な一貫性であるほかなく、しかしそれが集積したコラージュが都市性を持ちうる可能性にモダニズムの本性的限界を乗り越える可能性を見た。ヴィラ・アドリアーナはそうしたヴィジョンの象徴である。

岸和郎はその意味で没入的な一貫性を徹底することに賭けた建築家のひとりであり、それは同じTOTOギャラリー・間で開催された2000年の「プロジェクティド・リアリティーズ」展をふりかえってみても明らかだろう。アナクロを覚悟してモダニズムのスタイルを自ら引き受け、それに「死に損ない」的に没入する。単にあれでもこれでもありうる任意の意匠のひとつとしてのスタイルの選択ではなく、建築の本性的な一貫性の現代における可能態のひとつとしてモダニズムを徹底するということなのだろう。いや丁寧に見ればその視野は必ずしもモダニズムに完結したわけではなかった。モダニズムへのオブセッションはあったとしても、それはこの建築家が反応してきたさまざまな建築の経験の大きな部分をそれが占めてたというだけのことだったかもしれない。単にモダニズムへの深い執着があったばかりではなく、広く建築のさまざまなあり方を背景としてその実践があったことはこの建築家のいくつかの著作に当たれば明らかだろう。
この時期の作品として個人的に印象深いもののひとつに「園部SD Office」(1993)がある。変形敷地に直行するふたつのヴォリュームをレベル差を付けながら配した、さほど大きくないプロジェクトだが、それぞれのヴォリュームが共有する庭がさまざまに展開する構成が生む空間的な効果は実に驚くべきものがあった。この建築家がたびたびその関心を表明してきたケーススタディハウスの反響がまずはそこに見えるが、これに岸和郎が常に敬意を表してきた安藤忠雄の「淡路夢舞台」(1999)などの大型プロジェクトや「八木邸」(1997)を並べて見るとどうなるか。あるいはやはり岸和郎が建築家を志す頃に衝撃を受けたとしばしば述べてきたフィリップ・ジョンソン自邸のコンプレックスをさらに見れば?この系譜を辿ればいずれヴィラ・アドリアーナにたどり着く。性格の異なる要素からなるコンプレックスの中に複雑さを組み込む、しかもモダニズムのスタイルを徹底することを通じてそうしようというわけだ。
さらに、実際に敷地内にコンプレックスを配するような直接性を越えて、そして実際の敷地に何が建つかということ以前に、建築家の脳裏に一種のヴィラ・アドリアーナがあったとも言えるかもしれない。建築家がこれまでに体得し読み取ってきた建築、さまざまな形象の雲となった建築が集う、建築のアルカディアのような何かだ。
この時期の作品として個人的に印象深いもののひとつに「園部SD Office」(1993)がある。変形敷地に直行するふたつのヴォリュームをレベル差を付けながら配した、さほど大きくないプロジェクトだが、それぞれのヴォリュームが共有する庭がさまざまに展開する構成が生む空間的な効果は実に驚くべきものがあった。この建築家がたびたびその関心を表明してきたケーススタディハウスの反響がまずはそこに見えるが、これに岸和郎が常に敬意を表してきた安藤忠雄の「淡路夢舞台」(1999)などの大型プロジェクトや「八木邸」(1997)を並べて見るとどうなるか。あるいはやはり岸和郎が建築家を志す頃に衝撃を受けたとしばしば述べてきたフィリップ・ジョンソン自邸のコンプレックスをさらに見れば?この系譜を辿ればいずれヴィラ・アドリアーナにたどり着く。性格の異なる要素からなるコンプレックスの中に複雑さを組み込む、しかもモダニズムのスタイルを徹底することを通じてそうしようというわけだ。
さらに、実際に敷地内にコンプレックスを配するような直接性を越えて、そして実際の敷地に何が建つかということ以前に、建築家の脳裏に一種のヴィラ・アドリアーナがあったとも言えるかもしれない。建築家がこれまでに体得し読み取ってきた建築、さまざまな形象の雲となった建築が集う、建築のアルカディアのような何かだ。

今回のレクチャーは、前回展までの建築家の建築作品を早足に振り返りつつ、「京都に還る_home away from home」と題された今回展で紹介された近作の解説へと進んだ。展覧会そのものは、前半を教職を通じてかかわってきたプロジェクトを中心とした仕事、後半を建築家としての近作に割り当てていることを踏まえるなら、レクチャーが扱ったのは今回の展覧会の後半で、それらを通して何を考えてきたか、率直に語られた。
まず日本国内の作品、とりわけ京都の文脈、日本の文脈を踏まえ、それを現代建築としていかに作るかという仕事が扱われる。京都の職人とのかかわりの数々、茶室のような日本文化とともにある建築の作法と現代建築を融合させる仕事ということになる。かつての仕事と比べると、平面図で見て取られるような構造フレームの秩序が希薄になり、むしろ壁で組み立てられた奥行きと間合いの感覚的調整が主調になってきているように見受けられる。京都の培ってきた土壁をモダンなエレメントとする天井パネルや、奥行きを作りつつ空間の分節を行うガラスの坪庭のような、総じて部分の手法が全体のシステムと関係なく挿入されるようになったのも大きな転換だろう。ついでインドや中国など海外の作品が紹介され、そこではむしろ京都あるいは日本という背景を持った建築家がいかにその文脈を離れて作るか、ということがテーマとなった。古来よりさまざまな文物がシルクロードを介してたどり着き蓄積された極東の国としての日本。歴史が破壊的創造というよりは時を経て折り重なり融合してきた日本。岡倉天心の『東洋の理想』にも似た日本の特殊性が意識されるようになったようだ。仏教寺院がことごとく文化大革命で破壊された中国において禅寺を再興するプロジェクトなどを見れば、そこで日本に残された禅寺が構想のてがかりとして浮かんでくるのは当然のことで、日本という文脈をあらためて建築家に強く意識させたことは想像に難くない。
さまざまな文化的なレイヤーが錯綜するグローバリズムの現実の中で、建築はそれにどう応答出来るか。そこであらためて建築家が問われるのが「おまえは誰だ?」という問いだとしたら、岸和郎はそこで世界中の文物が流れ着き沈殿した「京都」に立つ自らを掘り下げるほかないと覚悟したのだろう。いや、覚悟というよりは大胆で向こう見ずな野心と言うべきかもしれない。かつての岸和郎がモダニズムへの没入に駆り立てられ自家薬籠中の物としてきた手法を敢えて解きほぐして、あらためて建築の広大な世界をまるごと身に引き受けようというのだから。モダニズムへと絞り込まれていたからこそ、そしてそれへの集中がほとんど没頭的なものであったからこそ掘り下げられた深さを、同様にかちうることが出来るものだろうか。
まず日本国内の作品、とりわけ京都の文脈、日本の文脈を踏まえ、それを現代建築としていかに作るかという仕事が扱われる。京都の職人とのかかわりの数々、茶室のような日本文化とともにある建築の作法と現代建築を融合させる仕事ということになる。かつての仕事と比べると、平面図で見て取られるような構造フレームの秩序が希薄になり、むしろ壁で組み立てられた奥行きと間合いの感覚的調整が主調になってきているように見受けられる。京都の培ってきた土壁をモダンなエレメントとする天井パネルや、奥行きを作りつつ空間の分節を行うガラスの坪庭のような、総じて部分の手法が全体のシステムと関係なく挿入されるようになったのも大きな転換だろう。ついでインドや中国など海外の作品が紹介され、そこではむしろ京都あるいは日本という背景を持った建築家がいかにその文脈を離れて作るか、ということがテーマとなった。古来よりさまざまな文物がシルクロードを介してたどり着き蓄積された極東の国としての日本。歴史が破壊的創造というよりは時を経て折り重なり融合してきた日本。岡倉天心の『東洋の理想』にも似た日本の特殊性が意識されるようになったようだ。仏教寺院がことごとく文化大革命で破壊された中国において禅寺を再興するプロジェクトなどを見れば、そこで日本に残された禅寺が構想のてがかりとして浮かんでくるのは当然のことで、日本という文脈をあらためて建築家に強く意識させたことは想像に難くない。
さまざまな文化的なレイヤーが錯綜するグローバリズムの現実の中で、建築はそれにどう応答出来るか。そこであらためて建築家が問われるのが「おまえは誰だ?」という問いだとしたら、岸和郎はそこで世界中の文物が流れ着き沈殿した「京都」に立つ自らを掘り下げるほかないと覚悟したのだろう。いや、覚悟というよりは大胆で向こう見ずな野心と言うべきかもしれない。かつての岸和郎がモダニズムへの没入に駆り立てられ自家薬籠中の物としてきた手法を敢えて解きほぐして、あらためて建築の広大な世界をまるごと身に引き受けようというのだから。モダニズムへと絞り込まれていたからこそ、そしてそれへの集中がほとんど没頭的なものであったからこそ掘り下げられた深さを、同様にかちうることが出来るものだろうか。

「京都に還る」。建築家の脳裏にヴィラ・アドリアーナがあるとしたら、それがいまや「京都」なのだ。単にデザインソースとしての建築のさまざまなイメージというのではない。いささかの逡巡はあれども、自らの視野とそのよって立つ場所、それを「京都」と敢えて呼ぶ。展覧会場の中庭には京都の都市グリッドが描かれ、そこには過去の建築作品のそれぞれの位置がマッピングされていた。上階(4F)のギャラリースペースの中庭に面するガラス面には京都の方角から望み見た東京のスカイラインがうっすら貼り込まれてさえいた。それもこれもそのような野心を意味しているはずだ。これからそれはどこへ向かうのだろう。最終講義とも称して行われたこのレクチャーではあるが、教育者としてはともかく、建築家としての今後への強い意欲を感じさせるものであった。

日埜直彦 Naohiko Hino
1971年
茨城県生まれ
1994年
大阪大学工学部建築工学科卒業
1994~2002年
アークスコーベ勤務
2002年
日埜建築設計事務所設立
2006年~
芝浦工業大学非常勤講師
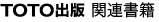
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。