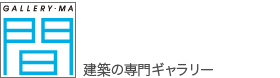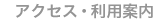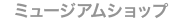- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

コラム
「建築のすそ野を広げたい」という想いで設立された編集事務所Office Bungaの磯達雄さんの視点から、「企画展 How is Life? ――地球と生きるためのデザイン」をより深く楽しむのに役立つ情報をお届けします。
文化人類学者の久保明教さんをお招きし、キュレーター塚本由晴さんと対談いただきました
本展の会場には、キュレーターたちが参考にした図書も展示されている。その中には、取り上げたプロジェクトの立案者による著作に混じって、ブルーノ・ラトゥールによる著書『虚構の「近代」』もあった。フランスの哲学者であるラトゥールは、人間以外を含むすべてのものが等しく社会のネットワークを形成しているとするアクターネットワーク論の推進者として注目された。彼の思想は「How is Life?」のテーマにどのように関わっているのか。本展の参考図書にも挙がっている『ブルーノ・ラトゥールの取説 アクターネットワーク論から存在様態探求へ』の著者で、文化人類学者の久保明教さんを招き、キュレーターのひとり、塚本由晴さんと対談してもらった。聞き手は磯達雄(建築ジャーナリスト)。
ーー塚本さんに案内をしてもらいながら、ひと通り展示会場を回りましたが、まずは率直な印象を聞かせていただけますか。
ーー塚本さんに案内をしてもらいながら、ひと通り展示会場を回りましたが、まずは率直な印象を聞かせていただけますか。

(写真右)一橋大学社会学研究科教授 久保明教氏。(写真左)建築家・How is Life?キュレーター 塚本由晴氏。
久保:まず思ったのは「でも四角だなぁ」ということです。いかにも建築展らしい模型や図面ではなく、様々な人やモノの関係性を描写したり組み替えたりデザインすること自体を建築として提示しているように見えるものが多かったですが、その大半が四角いフレームにコンテンツを配置する仕方で展示されていたので。
塚本:そうですね(笑)。
久保:単体の建築物というシステムではなく、建築をめぐる多様な要素が織りなすネットワークを探求している一方で、それを建築作品として展示するには、内外の区別のないネットワークをどこかで切り取って内外の区別があるシステムに変換しなければならなくなる、という矛盾を強く感じましたね。そうなると、特定の仕方でネットワークを切り取ることの根拠をどこからもってくるのかが問題になる。解決策としては、地域的なものや伝統的なものを部分的に参照することで、本来性と現代性を兼ね備えた緩やかなまとまりをイメージさせるような展示が多かったように思います。
人間も人間以外の存在も含む行為者(アクター)の諸関係(ネットワーク)によって私たちの生きる現実が作られるとみなすアクターネットワーク理論(ANT)のなかに、「ANTトポロジー」と呼ばれる一連の議論があります。アクターネットワークの組みたてられ方によって現れる空間性を「Region」「Network」「Fluid」「Fire」の4つに分類したものです。
まず「Network」は、特定の存在者同士の関係が複製されることで地域の差を超えて近接性が生みだされるようなアクターネットワークのあり方を指しています。例えば、「貧血はアフリカでは頻繁に見られるがオランダでは稀である」といった比較分析は、貧血の判断基準となるヘモグロビン測定を可能にする諸要素(測定器、英語の説明書、技師、血液凝固を防止する物質、血液など)とそれらの関係性が、オランダとアフリカ各地の実験室で同じような形で組みたてられることで可能になる。このとき、アフリカの実験室は近隣の市街地よりもオランダの実験室に近い空間になります。世界中の国際空港は近所の飲食店よりも互いに近い、と言ったほうがわかりやすいですかね。空港にせよ道路にせよ鉄道にせよ、20世紀以降急速に広まってきた規格化された長いネットワークは、諸関係の標準化によって遠く離れた諸点をつなげ、似通った場所にしてきた。こうした空間性は、私たちが通常「ネットワーク」という言葉で想起するものに近く、その無制限の拡張が「グローバル化」と呼ばれてきたわけですが、「モダニズム建築」はその先駆けの一つとも言えるのではないかと思います。
次に「Region(地域)」ですが、これは身体やモノと地球の表面(地表)の関係を軸として組みたてられたアクターネットワークが生みだす、ユークリッド幾何学的な空間性です。ここから1日歩いて行けるところは、100日歩いて行けるところよりもここと似ている(はずだ)という感覚。私たちが通常「場所」や「遠い/近い」という言葉で想起するものですね。各地を旅行するとき私たちが探し求めるものが「Region」の産物で、それが近所のスーパーにもあると知ってしまった時に直面しているのが「Network」の産物です(笑)。
つまり、今日の展示は「Network」の側から「Region」に関心を向けることで、前述した矛盾の解消ないし緩和を試みているように見えるものが多かった、ということです。塚本さんは、ハイデガーの「道具連関」に触れられていましたよね。
塚本:はい。「Tool Shed」のところで。
久保:道具連関とアクターネットワークは一見すると近いように思えますけど、現象学的主体としての人間(現存在)にとっての世界の現れを道具の連関において論じるハイデガーと、人間も非人間も現実を作るネットワークの一員としてフラットに捉えてしまうラトゥールには、相容れないところがあると思います。なので、建築をめぐる人とモノの関係性を道具連関として捉えることは、グローバルな「Network」の画一性に対して人間身体と環境との交渉に根ざした「Regional」な本来性を喚起する効果があるように見えます。
ただ、それを支えているのは「Network」の極限としての情報技術ではないのか、とも感じました。例えば「Bicycle Urbanism」では、空からの俯瞰ではなく自転車の目線から都市空間を再構築するという構想が描かれていますが、でも展示のベースに使われているのはグーグルマップのような俯瞰的な地図ですよね。グローバルに拡大する「Network」と、それと対比される「Region」の空間性を、デジタルなネットワークが裏でつないでる。情報技術というのは、この世界のあらゆる存在への認知をデジタルな数列という複製可能な関係性に還元する回路であり、それによって、アフリカの実験室の学問的評価と近所にあるローカルな飲食店の評判が同じグーグルマップ上の口コミの対象になる、ということが起こっちゃうわけですね。つまり、「Network」の極限としての情報技術の遍在、具体的には私たちがインターネットに接続された極小のコンピュータ=スマートフォンを日々どこにでも持ち歩くことによって、標準化されたグローバルな空間(Network)と標準化できない固有性を持つローカルな空間(Region)のあいだを自由に行き来することが可能になる。
塚本:なるほど、確かに。
久保:なので、どの展示にもコンピュータやスマホは表向き登場していないけれども、ローカルな空間性を再構築する展示作品の魅力を醸しだしているのは、制作する側も鑑賞する僕らの側もスマホによってグローバルな空間にもつながっていることではないかと。「Tool Shed」は、それこそ写真とってSNSにあげたくなりますよね、あれはかなり「インスタ映え」するでしょう(笑)。
塚本:道具たちは確かにインスタ映えする。そのリージョナルな価値を支えてるのは、デジタルということですよね。それはそうだなと思います。
久保:「インスタ映え」というものが、情報技術のグローバルな空間性に依存すると同時にそれに対抗して発揮されるローカルな「いま・ここ」の固有性の効果だとするならば、「Tool Shed」にはその極限に近い完成度を感じました。個人的には、あそこに道具と一緒にスマホも置いて欲しいですけども。でも、どう展示すればいいんでしょう? かなり気持ち悪いことになるかもしれませんね(笑)僕らはスマホで見たいんであってスマホを見たいわけではないですから。
塚本:都市では道具をほとんど使わないでしょう。その代わりに、スマホだけ持っていれば、どこでも行ける。これが最後の道具みたいになっています。これ自体はオブジェクトなんだけど、ネットワークの入り口にもなっているという不思議な存在なんだなと、改めて思いました。
ーー久保さんから鋭い指摘をいただきましたが、他の人からどんなことを言われましたか。
塚本:「ずいぶんロマンティックじゃない?」という意見や「言いたいことはわかるけれども、現実の建築の仕事からはかなりの距離がある」という意見がありました。自分としてはピンと来ませんでしたが、そういう意見を引き出したこと自体が大事だと思います。でもデジタルがリージョナルなものと20世紀的な規格による長いネットワークをつなげているという話は、とても的確だなと思いました。それはまさに、今回の我々の展覧会ではカバーできていないところです。
久保:僕はそんなにロマンティックだとは思わなかったですね。むしろ最初に話したような矛盾がわりとボロッと出てしまっているのが面白いなと感じました。たとえばフランスの「Capital Agricole」では工場だったところが畑になると描かれていますが、その工場、たぶん中国とかに行ってますよね?
塚本:そうですね、押し付けてる。
久保:人件費の安い工場をつくれる他国のどこかとフランスが、「Network」の空間によって凄いスピードでつながってるからこそ、郊外都市に農地を入れ込むことができる。都市の現代性と農村の本来性を兼ね備えた諸関係のまとまりが、移転先の工場が切り落とされているからこそ可能になっていることが赤裸々に示されているように感じました。システムではなくネットワークとして展示しているからこそ、そこにないものが見えやすいな、と。
塚本:矛盾を見出すのは、上級者の楽しみ方ですね。
久保:以前、民族学博物館の資料を用いた国立新美術館の展覧会(「イメージの力 国立民族学博物館コレクションにさぐる」展)のシンポジウムに参加したことがあるのですが、僕はなんとなくずっと壁に注目しながら展示を見ていました。「ホワイトキューブ」と呼ばれる現代美術の標準化された空間が想定していないような、トーテムポールや仮面のような民族学的資料が沢山展示されたのですが、そうすると――僕はホワイトキューブを「白壁さん」と呼んでたんですけど――展示物によって色々と困ったような顔を白壁さんがしていくわけです(笑)。絵画と額縁のような関係を「figure/ground」(図/地)と言いますが、通常は作品が「図」で美術館の壁は「地」ですけど、むしろ自分には、呪物や精霊像のローカルな超越性を「地」とすることで近代的な合理性(超越論的主観性)を体現するグローバルなホワイトキューブがムチャクチャにされていく姿が「図」として見えてしょうがなかったので、展覧会の各パートで白壁さんがどのように表情を変えていったかを分析する発表をしました。
塚本:展示される側が展示室や展示するということの当たり前を変えてしまうということですね。
久保:そうですね。今回の展示のなかで、そうしたローカルな特異性によってグローバルな空間性に基づくデザインが変えられてしまう契機が見えたのは、インドでの公衆便所プロジェクトがカーストに関する現地の関係性によって部分的に失敗したというエピソードくらいだったように思います。
もちろん、展示する側(建築家)が展示される側(建築の対象)をより良く変えていく、というクライアントからの期待を明示的に裏切ることは難しいでしょう。ただ、『ブルーノ・ラトゥールの取説』で特に強調したのは、ヒトやモノの関係性をデザインする行為は、それらのアクターネットワークに自らも連なっていくことであり、外側から世界(ネットワーク)を客観的に眺めることもまた、俯瞰できないままネットワークの内側でその組み替えに参与している運動が産出する一時的な効果にすぎない、ということでした。言い換えると、展示する側と展示される側の「図/地」関係は常に反転しうるということですね。
塚本:私が理事をつとめている「小さな地球」というプロジェクトも、まさにそうです。これまで建築系の研究室が農村に行く場合は、フィールドサーベイでした。何かを実践している人がいて、その外側からそれを観察する、というものです。だけどもう農村にはほとんど人がいないんですよ。空き家と耕作放棄地だらけなので、教わりながら自分たちでやるしかない。その姿をまた、自分たちで観察する、そういう不思議な再帰性が生じているので、フィールド・ラーニングと呼んでいます。
ーー今回の展覧会では、ラトゥールの本が参考図書として挙げられていました。なぜこれを取り上げられたのですか。
塚本:そうですね(笑)。
久保:単体の建築物というシステムではなく、建築をめぐる多様な要素が織りなすネットワークを探求している一方で、それを建築作品として展示するには、内外の区別のないネットワークをどこかで切り取って内外の区別があるシステムに変換しなければならなくなる、という矛盾を強く感じましたね。そうなると、特定の仕方でネットワークを切り取ることの根拠をどこからもってくるのかが問題になる。解決策としては、地域的なものや伝統的なものを部分的に参照することで、本来性と現代性を兼ね備えた緩やかなまとまりをイメージさせるような展示が多かったように思います。
人間も人間以外の存在も含む行為者(アクター)の諸関係(ネットワーク)によって私たちの生きる現実が作られるとみなすアクターネットワーク理論(ANT)のなかに、「ANTトポロジー」と呼ばれる一連の議論があります。アクターネットワークの組みたてられ方によって現れる空間性を「Region」「Network」「Fluid」「Fire」の4つに分類したものです。
まず「Network」は、特定の存在者同士の関係が複製されることで地域の差を超えて近接性が生みだされるようなアクターネットワークのあり方を指しています。例えば、「貧血はアフリカでは頻繁に見られるがオランダでは稀である」といった比較分析は、貧血の判断基準となるヘモグロビン測定を可能にする諸要素(測定器、英語の説明書、技師、血液凝固を防止する物質、血液など)とそれらの関係性が、オランダとアフリカ各地の実験室で同じような形で組みたてられることで可能になる。このとき、アフリカの実験室は近隣の市街地よりもオランダの実験室に近い空間になります。世界中の国際空港は近所の飲食店よりも互いに近い、と言ったほうがわかりやすいですかね。空港にせよ道路にせよ鉄道にせよ、20世紀以降急速に広まってきた規格化された長いネットワークは、諸関係の標準化によって遠く離れた諸点をつなげ、似通った場所にしてきた。こうした空間性は、私たちが通常「ネットワーク」という言葉で想起するものに近く、その無制限の拡張が「グローバル化」と呼ばれてきたわけですが、「モダニズム建築」はその先駆けの一つとも言えるのではないかと思います。
次に「Region(地域)」ですが、これは身体やモノと地球の表面(地表)の関係を軸として組みたてられたアクターネットワークが生みだす、ユークリッド幾何学的な空間性です。ここから1日歩いて行けるところは、100日歩いて行けるところよりもここと似ている(はずだ)という感覚。私たちが通常「場所」や「遠い/近い」という言葉で想起するものですね。各地を旅行するとき私たちが探し求めるものが「Region」の産物で、それが近所のスーパーにもあると知ってしまった時に直面しているのが「Network」の産物です(笑)。
つまり、今日の展示は「Network」の側から「Region」に関心を向けることで、前述した矛盾の解消ないし緩和を試みているように見えるものが多かった、ということです。塚本さんは、ハイデガーの「道具連関」に触れられていましたよね。
塚本:はい。「Tool Shed」のところで。
久保:道具連関とアクターネットワークは一見すると近いように思えますけど、現象学的主体としての人間(現存在)にとっての世界の現れを道具の連関において論じるハイデガーと、人間も非人間も現実を作るネットワークの一員としてフラットに捉えてしまうラトゥールには、相容れないところがあると思います。なので、建築をめぐる人とモノの関係性を道具連関として捉えることは、グローバルな「Network」の画一性に対して人間身体と環境との交渉に根ざした「Regional」な本来性を喚起する効果があるように見えます。
ただ、それを支えているのは「Network」の極限としての情報技術ではないのか、とも感じました。例えば「Bicycle Urbanism」では、空からの俯瞰ではなく自転車の目線から都市空間を再構築するという構想が描かれていますが、でも展示のベースに使われているのはグーグルマップのような俯瞰的な地図ですよね。グローバルに拡大する「Network」と、それと対比される「Region」の空間性を、デジタルなネットワークが裏でつないでる。情報技術というのは、この世界のあらゆる存在への認知をデジタルな数列という複製可能な関係性に還元する回路であり、それによって、アフリカの実験室の学問的評価と近所にあるローカルな飲食店の評判が同じグーグルマップ上の口コミの対象になる、ということが起こっちゃうわけですね。つまり、「Network」の極限としての情報技術の遍在、具体的には私たちがインターネットに接続された極小のコンピュータ=スマートフォンを日々どこにでも持ち歩くことによって、標準化されたグローバルな空間(Network)と標準化できない固有性を持つローカルな空間(Region)のあいだを自由に行き来することが可能になる。
塚本:なるほど、確かに。
久保:なので、どの展示にもコンピュータやスマホは表向き登場していないけれども、ローカルな空間性を再構築する展示作品の魅力を醸しだしているのは、制作する側も鑑賞する僕らの側もスマホによってグローバルな空間にもつながっていることではないかと。「Tool Shed」は、それこそ写真とってSNSにあげたくなりますよね、あれはかなり「インスタ映え」するでしょう(笑)。
塚本:道具たちは確かにインスタ映えする。そのリージョナルな価値を支えてるのは、デジタルということですよね。それはそうだなと思います。
久保:「インスタ映え」というものが、情報技術のグローバルな空間性に依存すると同時にそれに対抗して発揮されるローカルな「いま・ここ」の固有性の効果だとするならば、「Tool Shed」にはその極限に近い完成度を感じました。個人的には、あそこに道具と一緒にスマホも置いて欲しいですけども。でも、どう展示すればいいんでしょう? かなり気持ち悪いことになるかもしれませんね(笑)僕らはスマホで見たいんであってスマホを見たいわけではないですから。
塚本:都市では道具をほとんど使わないでしょう。その代わりに、スマホだけ持っていれば、どこでも行ける。これが最後の道具みたいになっています。これ自体はオブジェクトなんだけど、ネットワークの入り口にもなっているという不思議な存在なんだなと、改めて思いました。
ーー久保さんから鋭い指摘をいただきましたが、他の人からどんなことを言われましたか。
塚本:「ずいぶんロマンティックじゃない?」という意見や「言いたいことはわかるけれども、現実の建築の仕事からはかなりの距離がある」という意見がありました。自分としてはピンと来ませんでしたが、そういう意見を引き出したこと自体が大事だと思います。でもデジタルがリージョナルなものと20世紀的な規格による長いネットワークをつなげているという話は、とても的確だなと思いました。それはまさに、今回の我々の展覧会ではカバーできていないところです。
久保:僕はそんなにロマンティックだとは思わなかったですね。むしろ最初に話したような矛盾がわりとボロッと出てしまっているのが面白いなと感じました。たとえばフランスの「Capital Agricole」では工場だったところが畑になると描かれていますが、その工場、たぶん中国とかに行ってますよね?
塚本:そうですね、押し付けてる。
久保:人件費の安い工場をつくれる他国のどこかとフランスが、「Network」の空間によって凄いスピードでつながってるからこそ、郊外都市に農地を入れ込むことができる。都市の現代性と農村の本来性を兼ね備えた諸関係のまとまりが、移転先の工場が切り落とされているからこそ可能になっていることが赤裸々に示されているように感じました。システムではなくネットワークとして展示しているからこそ、そこにないものが見えやすいな、と。
塚本:矛盾を見出すのは、上級者の楽しみ方ですね。
久保:以前、民族学博物館の資料を用いた国立新美術館の展覧会(「イメージの力 国立民族学博物館コレクションにさぐる」展)のシンポジウムに参加したことがあるのですが、僕はなんとなくずっと壁に注目しながら展示を見ていました。「ホワイトキューブ」と呼ばれる現代美術の標準化された空間が想定していないような、トーテムポールや仮面のような民族学的資料が沢山展示されたのですが、そうすると――僕はホワイトキューブを「白壁さん」と呼んでたんですけど――展示物によって色々と困ったような顔を白壁さんがしていくわけです(笑)。絵画と額縁のような関係を「figure/ground」(図/地)と言いますが、通常は作品が「図」で美術館の壁は「地」ですけど、むしろ自分には、呪物や精霊像のローカルな超越性を「地」とすることで近代的な合理性(超越論的主観性)を体現するグローバルなホワイトキューブがムチャクチャにされていく姿が「図」として見えてしょうがなかったので、展覧会の各パートで白壁さんがどのように表情を変えていったかを分析する発表をしました。
塚本:展示される側が展示室や展示するということの当たり前を変えてしまうということですね。
久保:そうですね。今回の展示のなかで、そうしたローカルな特異性によってグローバルな空間性に基づくデザインが変えられてしまう契機が見えたのは、インドでの公衆便所プロジェクトがカーストに関する現地の関係性によって部分的に失敗したというエピソードくらいだったように思います。
もちろん、展示する側(建築家)が展示される側(建築の対象)をより良く変えていく、というクライアントからの期待を明示的に裏切ることは難しいでしょう。ただ、『ブルーノ・ラトゥールの取説』で特に強調したのは、ヒトやモノの関係性をデザインする行為は、それらのアクターネットワークに自らも連なっていくことであり、外側から世界(ネットワーク)を客観的に眺めることもまた、俯瞰できないままネットワークの内側でその組み替えに参与している運動が産出する一時的な効果にすぎない、ということでした。言い換えると、展示する側と展示される側の「図/地」関係は常に反転しうるということですね。
塚本:私が理事をつとめている「小さな地球」というプロジェクトも、まさにそうです。これまで建築系の研究室が農村に行く場合は、フィールドサーベイでした。何かを実践している人がいて、その外側からそれを観察する、というものです。だけどもう農村にはほとんど人がいないんですよ。空き家と耕作放棄地だらけなので、教わりながら自分たちでやるしかない。その姿をまた、自分たちで観察する、そういう不思議な再帰性が生じているので、フィールド・ラーニングと呼んでいます。
ーー今回の展覧会では、ラトゥールの本が参考図書として挙げられていました。なぜこれを取り上げられたのですか。

塚本:私は建築の設計をしていますが、大学では建築意匠論を研究しています。これを進めていくうちに、文化人類学とか民族誌とか、そういうものにどんどん関心が近づいています。そうするうちに、人や物のふるまいをコーディネートするというのが建築で逆に、ふるまいに下りていかない設計は、全然面白くないと思うようになりました。建築の空間論は、幾何学的な形と距離の関係に還元できますが、ふるまいになるととらえられない。ふるまいとは、水が下に流れるとか、熱い空気が上に行くとか、人間だったらある状況になると足を組んでしまうとか、人が亡くなった後に折り合いをつけるため葬式が行われるとか、そういうものを含んでいます。
今回展示されている「動いている庭」は、本当にふるまい学的です。ベルサイユ宮殿にあるようなフランス式庭園は、幾何学的につくられた植え込みを維持するために、常に同じ形に刈っていくというもので、植物のふるまいを、空間的に抑圧するやり方です。「動いている庭」は、逆に植物ひとつひとつのふるまいを理解したうえで、それらにどう一緒にいてもらえるか、遊んでもらえるか、それを考えてつくっています。
建築や都市の設計もそうだと思っていて、ふるまいにどんどん降りていくと、今まで気付かなかった連中がふるまっているわけです。それを見つけて、君たちも一緒に遊ぼうよ、というふうにして、遊び場をつくっていく。これをどうやって説明しようかと考えているときに、ラトゥールのアクターネットワークについて知る機会があり、すごく面白いと思ったんです。
久保:いつ頃ですか?
塚本:2011年のころに『虚構の「近代」』を読みました。その時はアーキエイドという建築家のグループで東日本大震災の復興支援に取り組んでいました。巨大な防潮堤がつくられると山と海の関係や住民と海の関係にいろいろな問題が起こることが想像されるけど、止めることはできない。我々建築家がRegionalな連関をつなぎなおすような提案をしてもNetworkを広げようとする建設産業の生産様式自体が障壁になり現実のものにはなっていかない。大きなモヤモヤを感じていた時に、ラトゥールの「ハイブリッド・モンスター」という概念が、まさに言い当てているなと。
久保:なるほど、建築家はどう社会に関われるのか、という論点からつながってきたわけですかね?
塚本:産業社会から条件を与えられて設計する建築家の関わり方だけでは、良い社会になっていかないだろう。建築家がよく用いる空間という概念も、今では産業社会自らネットワークを再生産し補強してしまっているのが現状。建築空間の議論はどうしても幾何学的に把握できる範囲で全体を切りとってしまい、その外側にあるものは無視できるから、忘れられてしまう。見ているものの向こう側がいっぱいあるということを意識したときにアクターネットワークの発想というのが使えるだろう。
さかのぼって考えると、19世紀後半ぐらいから建築の分野では空間という概念が出てきますが、それは産業革命を経て、社会が産業化するのに伴って出てきていることがわかります。高い生産力を身につけてしまった人間は、明日は昨日と違わなくてはいけなくなってしまった。そうすると今まで自分たちが属してきたRegionalな事物連関から離脱して、次に行かないといけない。そうしないと、自分たちの生産力を行使できないので。能力を行使できなかったら人間はいやじゃないですか。それでみんなでネットワークへと離脱したんですよね。農家の次男、三男が東京へ出ていくというのがまさにそういうことだったわけです。しかし、空間という概念は、解放とは結びつくけど、つなぎこみを説明できない。説明されないまま結局は産業社会的連関、長いネットワークにつなぎ込まれていった。解放された自由があるはずだったのにいつのまにか抜け出せない息苦しさすら感じるようになっている。そういう現実を批判的に捉える上でもアクターネットワークはいいなと思いました。
今回展示されている「動いている庭」は、本当にふるまい学的です。ベルサイユ宮殿にあるようなフランス式庭園は、幾何学的につくられた植え込みを維持するために、常に同じ形に刈っていくというもので、植物のふるまいを、空間的に抑圧するやり方です。「動いている庭」は、逆に植物ひとつひとつのふるまいを理解したうえで、それらにどう一緒にいてもらえるか、遊んでもらえるか、それを考えてつくっています。
建築や都市の設計もそうだと思っていて、ふるまいにどんどん降りていくと、今まで気付かなかった連中がふるまっているわけです。それを見つけて、君たちも一緒に遊ぼうよ、というふうにして、遊び場をつくっていく。これをどうやって説明しようかと考えているときに、ラトゥールのアクターネットワークについて知る機会があり、すごく面白いと思ったんです。
久保:いつ頃ですか?
塚本:2011年のころに『虚構の「近代」』を読みました。その時はアーキエイドという建築家のグループで東日本大震災の復興支援に取り組んでいました。巨大な防潮堤がつくられると山と海の関係や住民と海の関係にいろいろな問題が起こることが想像されるけど、止めることはできない。我々建築家がRegionalな連関をつなぎなおすような提案をしてもNetworkを広げようとする建設産業の生産様式自体が障壁になり現実のものにはなっていかない。大きなモヤモヤを感じていた時に、ラトゥールの「ハイブリッド・モンスター」という概念が、まさに言い当てているなと。
久保:なるほど、建築家はどう社会に関われるのか、という論点からつながってきたわけですかね?
塚本:産業社会から条件を与えられて設計する建築家の関わり方だけでは、良い社会になっていかないだろう。建築家がよく用いる空間という概念も、今では産業社会自らネットワークを再生産し補強してしまっているのが現状。建築空間の議論はどうしても幾何学的に把握できる範囲で全体を切りとってしまい、その外側にあるものは無視できるから、忘れられてしまう。見ているものの向こう側がいっぱいあるということを意識したときにアクターネットワークの発想というのが使えるだろう。
さかのぼって考えると、19世紀後半ぐらいから建築の分野では空間という概念が出てきますが、それは産業革命を経て、社会が産業化するのに伴って出てきていることがわかります。高い生産力を身につけてしまった人間は、明日は昨日と違わなくてはいけなくなってしまった。そうすると今まで自分たちが属してきたRegionalな事物連関から離脱して、次に行かないといけない。そうしないと、自分たちの生産力を行使できないので。能力を行使できなかったら人間はいやじゃないですか。それでみんなでネットワークへと離脱したんですよね。農家の次男、三男が東京へ出ていくというのがまさにそういうことだったわけです。しかし、空間という概念は、解放とは結びつくけど、つなぎこみを説明できない。説明されないまま結局は産業社会的連関、長いネットワークにつなぎ込まれていった。解放された自由があるはずだったのにいつのまにか抜け出せない息苦しさすら感じるようになっている。そういう現実を批判的に捉える上でもアクターネットワークはいいなと思いました。

磯達雄
ーー今のお話を建築の方に引き寄せて語ると、建築のほうではモダニズムという建築の考え方がずっとあって、それに対する批判としてポストモダニズムというのが言われましたけど、それとはまた違う話ですか。
塚本:違います。建築のポストモダニズムは規格化されてネットワークを広げていくことに対しては、ぜんぜん疑っていません。それを温存したまま、何か意匠として差異化を図るという面が大きかった。20世紀型の規格化された長いネットワークをつくっていくことに対して、批判はできていなかった。そこではないやり方はないか、ということを考えているんです。
ーー久保さんの本では、モダニズム、ポストモダニズムに加えて、ノンモダニズムという3項目を挙げていました。
塚本:違います。建築のポストモダニズムは規格化されてネットワークを広げていくことに対しては、ぜんぜん疑っていません。それを温存したまま、何か意匠として差異化を図るという面が大きかった。20世紀型の規格化された長いネットワークをつくっていくことに対して、批判はできていなかった。そこではないやり方はないか、ということを考えているんです。
ーー久保さんの本では、モダニズム、ポストモダニズムに加えて、ノンモダニズムという3項目を挙げていました。

久保:その3分類については、かなり留保しながら書いたつもりです。人文・社会科学でこんな雑な言い方は本来やっちゃいけないんです(笑)。ラトゥール自身も「ノンモダン」とは言ってるけれども、「モダニズム⇒ポストモダニズム⇒ノンモダニズム」と並べているわけではないですし。でも、こういうふうに整理した方が議論のたたき台としてはわかりやすいだろうと思って、あえてやりました。
この3分類について人文・社会科学系の研究者からの反応は今のところなくて、それも当然だと思うのですが、どうも建築界隈の方が割と援用してくれているみたいで、すごいな、大丈夫?と(笑)。文系の学問だと「近代(社会)」というのは私たちの考え方や制度的な基礎のすべてを指すような概念になっているので、「ポスト」とか「ノン」とか頭につけても結局は近代の延長でしかないよね、と言われやすいです。
でも「モダニズム」や「ポストモダニズム」という語彙の出自である建築界の方々は、わりと躊躇なく突っ込んでくれるみたいで。ただ、自然と社会の峻別を排して諸関係を追跡しようとするラトゥールの議論は、建築家の方々には受け入れやすいのかもしれないとは思います。建築物を作るということが、自然の要素と社会的な要素を混ぜ合わせることであるのは明白ですから。塚本さんと話をしていても、文系の研究者にも理系の研究者にも見えるし、アーティストにも見えるし、工務店のひとみたいにも見える。現代の社会を理性的に批判しているように見えると同時に、建築によって社会空間を変えてしまう暴力的な力を手放すつもりもなさそうに見えます。
ラトゥールもまた『フランスのパストゥール化』(1984年)後半の「非還元の原理」において、理性と力という二項対立の無効化を構想しています。多くの研究者が、諸現象をなんらかの原理に還元する理性的な分析によって諸事象に内在する力(惰性や抑圧や暴力)を制御しようとするような考え方、理性をもって力に対抗する発想を倫理的に肯定するように思われるのに対して、ラトゥールは理性と力の二項対立を排して関係の一元論だけでやってしまおうと考えた。こうした発想が、ミシェル・カロンが考案したアクターネットワーク論と合流していったわけですが、ここがラトゥールの独特なところだと思っています。
塚本:モダンな建築の世界というのは規範がはっきりあって、それを守っていればひとまず建てられるようになってますよね。それは底上げにもなったし、大事なことだった。みんながいちいち立ち止まって考えなくてもいい。コンクリートについて、何か泥みたいなものを練っているけど大丈夫なの?みたいなことを毎回、疑う必要はない。そのための技術指針もあるから、それを信頼してやっている。働いてる人もそれで守られた。でも、それによって狭められてることもいっぱいあって、どうやったらそういう規範を外せるかというのは、大きな課題です。大事だと思ったものを、1回キャンセルしてみると、何が起こるだろう。それを実験をするだけの場をどうやったらつくれるか。
久保:理性に基づく静的な回路があって、そこに力が流し込めるというイメージだったものを、もっと色んなやり方で捉え直せるだろう、ということですかね。今回の「小さな地球」で取り組まれていた「里山」というのもそのひとつの契機なのでしょうか?
塚本:里山では、都会でできないことができる。日本ではほとんどの地域で、屋根を不燃材で葺きなさいという法律がかかっているので茅葺の新築はできない。循環型の建築が求められているにもかかわらず、最もそれに近い茅葺ができないのは、鉄道のレールを同じ幅に揃えようという考え方と同じで、不燃の考えが全国に広まっていったから。ヨーロッパではガラスクロスを下地に挟む方法で、爆発的に燃え広がらない茅葺き技術も出てきているのですが、茅葺きというだけで、最初から法律ではじかれている。変なことが起こらないように理性でいろいろ整えてきた結果、自分たちが本当はできることを狭めてるんですよね。
久保:今回の展示を見て、石積みは自分でやりたくなりましたね。
塚本:おおっ(笑)。今度やるときには、声を掛けますよ。
久保:石の方がコンクリートよりコストもかからないんですか。
塚本:そうなんです。昔は建物にも道にも普請という相互扶助的な建設がありました。土木は英語でシビル・エンジニアリングといいますよね。つまり、工学によって産業化された土木も、もともとは市民が自分たちでやるということだったんですよ。
久保:情報技術との関係ということでは、ゲームの「マインクラフト」をやっている今の小学生くらいのひとたちにとって、サンドボックスと石積みは近いところにあるようにも感じます。あのゲームは、文明進歩のシミュレーションみたいに遊べるところがある一方で、自分で一つずつボックスを積んでいくので、壮大な建築物を作りながら足場から落下してすぐ死んじゃったりする。クリックひとつで住宅地が作れる「シムシティ」みたいなゲームとは違って、あまりプレイヤーを接待してくれない。デジタルな数列がもっているミニマルな物質性から特異性が生じていくようなイメージは、石積みに案外近いように感じられるのではないかと思います。
塚本:施設も、もうそんなに手厚くサービスする場でなくていいんじゃないかな。みんなお客さん扱いされるのに飽きてると思うんですよ。お客さん扱いされない人間になる手段として「Tool Shed」の概念が展示で重要なものになっていきました。先日ニュースでIoTを駆使した家が紹介されていました。それは、朝を起きて「おはよう」と言うと自動的にカーテンが開いて、コーヒーポットが作動して、パンも焼いてくれるようになる、みたいな「Service Shed」化でした。それよりは、家を「Tool Shed」化していく方がいいと思う。道具を手にした住み手になるということ。
久保:お客さん扱いというのは「安心安全」ということにも結びついていますよね。20年とか30年前、安心安全というのは「そうだったらいいよね」というくらいのレトリックでしかなかったと思うんですが、今は「そうでなければならない」ことになっている。道具というのは、ケガしやすいですしね。
塚本:そう道具は危ないものでもある。一揆を起こせるしね(笑)。都市から道具がなくなったのは、一揆や暴動を抑える意味もあったのかもしれない。安心安全の問題は、まさにレトリックですよね。
久保:多様性の肯定ということが規範的なものになりつつありますが、そこでも「みんなちがってみんないい」と平気な顔して言えるのは、あらかじめ「安心安全でないもの」や「みんなにとって悪い」とされたものが排除される限りにおいてではないかと。「みんなちがってみんないい」が規範化されると「みんな良い限りにおいてみんなちがって良い」になってしまう。今回の展覧会のコンセプト文で、多様な存在が集えるような「話し合いのテーブル」というイメージが掲げられていますが、そのテーブルには誰がつけるのか、ということですね。そういう意味では「テーブル」の比喩でいいんですかね? テーブルと言っている時点で、みんなちゃんと椅子に座れるひとだろうし、きちんとスーツ着てそうですよね。
塚本:そこは「遊び場」に言い換えましょう(笑)。
久保:でも「遊び場」っていう表現も今は結構きつくないですか? 今年、ゼミで教えている学生に「遊び」というテーマで調べてもらったのですが、公園とかスポーツ観戦のようなきっちり枠が区切られた安心安全な場所しか出てこないんですよね。「夜遊び」も「火遊び」も出てこない。「遊び」のイメージに遊びがなくなってる。ちょっと前まで「遊び場」というのは安心でも安全でもないところだったじゃないですか。安心安全ではないものを「危険」とか「リスク」とは違う言葉で表せないか、ということは考えてみたいですね。
塚本:そう。遊び場こそ、再生されなければいけない。
ーー今回の展示を見て、気になったことがあれば教えてください。
この3分類について人文・社会科学系の研究者からの反応は今のところなくて、それも当然だと思うのですが、どうも建築界隈の方が割と援用してくれているみたいで、すごいな、大丈夫?と(笑)。文系の学問だと「近代(社会)」というのは私たちの考え方や制度的な基礎のすべてを指すような概念になっているので、「ポスト」とか「ノン」とか頭につけても結局は近代の延長でしかないよね、と言われやすいです。
でも「モダニズム」や「ポストモダニズム」という語彙の出自である建築界の方々は、わりと躊躇なく突っ込んでくれるみたいで。ただ、自然と社会の峻別を排して諸関係を追跡しようとするラトゥールの議論は、建築家の方々には受け入れやすいのかもしれないとは思います。建築物を作るということが、自然の要素と社会的な要素を混ぜ合わせることであるのは明白ですから。塚本さんと話をしていても、文系の研究者にも理系の研究者にも見えるし、アーティストにも見えるし、工務店のひとみたいにも見える。現代の社会を理性的に批判しているように見えると同時に、建築によって社会空間を変えてしまう暴力的な力を手放すつもりもなさそうに見えます。
ラトゥールもまた『フランスのパストゥール化』(1984年)後半の「非還元の原理」において、理性と力という二項対立の無効化を構想しています。多くの研究者が、諸現象をなんらかの原理に還元する理性的な分析によって諸事象に内在する力(惰性や抑圧や暴力)を制御しようとするような考え方、理性をもって力に対抗する発想を倫理的に肯定するように思われるのに対して、ラトゥールは理性と力の二項対立を排して関係の一元論だけでやってしまおうと考えた。こうした発想が、ミシェル・カロンが考案したアクターネットワーク論と合流していったわけですが、ここがラトゥールの独特なところだと思っています。
塚本:モダンな建築の世界というのは規範がはっきりあって、それを守っていればひとまず建てられるようになってますよね。それは底上げにもなったし、大事なことだった。みんながいちいち立ち止まって考えなくてもいい。コンクリートについて、何か泥みたいなものを練っているけど大丈夫なの?みたいなことを毎回、疑う必要はない。そのための技術指針もあるから、それを信頼してやっている。働いてる人もそれで守られた。でも、それによって狭められてることもいっぱいあって、どうやったらそういう規範を外せるかというのは、大きな課題です。大事だと思ったものを、1回キャンセルしてみると、何が起こるだろう。それを実験をするだけの場をどうやったらつくれるか。
久保:理性に基づく静的な回路があって、そこに力が流し込めるというイメージだったものを、もっと色んなやり方で捉え直せるだろう、ということですかね。今回の「小さな地球」で取り組まれていた「里山」というのもそのひとつの契機なのでしょうか?
塚本:里山では、都会でできないことができる。日本ではほとんどの地域で、屋根を不燃材で葺きなさいという法律がかかっているので茅葺の新築はできない。循環型の建築が求められているにもかかわらず、最もそれに近い茅葺ができないのは、鉄道のレールを同じ幅に揃えようという考え方と同じで、不燃の考えが全国に広まっていったから。ヨーロッパではガラスクロスを下地に挟む方法で、爆発的に燃え広がらない茅葺き技術も出てきているのですが、茅葺きというだけで、最初から法律ではじかれている。変なことが起こらないように理性でいろいろ整えてきた結果、自分たちが本当はできることを狭めてるんですよね。
久保:今回の展示を見て、石積みは自分でやりたくなりましたね。
塚本:おおっ(笑)。今度やるときには、声を掛けますよ。
久保:石の方がコンクリートよりコストもかからないんですか。
塚本:そうなんです。昔は建物にも道にも普請という相互扶助的な建設がありました。土木は英語でシビル・エンジニアリングといいますよね。つまり、工学によって産業化された土木も、もともとは市民が自分たちでやるということだったんですよ。
久保:情報技術との関係ということでは、ゲームの「マインクラフト」をやっている今の小学生くらいのひとたちにとって、サンドボックスと石積みは近いところにあるようにも感じます。あのゲームは、文明進歩のシミュレーションみたいに遊べるところがある一方で、自分で一つずつボックスを積んでいくので、壮大な建築物を作りながら足場から落下してすぐ死んじゃったりする。クリックひとつで住宅地が作れる「シムシティ」みたいなゲームとは違って、あまりプレイヤーを接待してくれない。デジタルな数列がもっているミニマルな物質性から特異性が生じていくようなイメージは、石積みに案外近いように感じられるのではないかと思います。
塚本:施設も、もうそんなに手厚くサービスする場でなくていいんじゃないかな。みんなお客さん扱いされるのに飽きてると思うんですよ。お客さん扱いされない人間になる手段として「Tool Shed」の概念が展示で重要なものになっていきました。先日ニュースでIoTを駆使した家が紹介されていました。それは、朝を起きて「おはよう」と言うと自動的にカーテンが開いて、コーヒーポットが作動して、パンも焼いてくれるようになる、みたいな「Service Shed」化でした。それよりは、家を「Tool Shed」化していく方がいいと思う。道具を手にした住み手になるということ。
久保:お客さん扱いというのは「安心安全」ということにも結びついていますよね。20年とか30年前、安心安全というのは「そうだったらいいよね」というくらいのレトリックでしかなかったと思うんですが、今は「そうでなければならない」ことになっている。道具というのは、ケガしやすいですしね。
塚本:そう道具は危ないものでもある。一揆を起こせるしね(笑)。都市から道具がなくなったのは、一揆や暴動を抑える意味もあったのかもしれない。安心安全の問題は、まさにレトリックですよね。
久保:多様性の肯定ということが規範的なものになりつつありますが、そこでも「みんなちがってみんないい」と平気な顔して言えるのは、あらかじめ「安心安全でないもの」や「みんなにとって悪い」とされたものが排除される限りにおいてではないかと。「みんなちがってみんないい」が規範化されると「みんな良い限りにおいてみんなちがって良い」になってしまう。今回の展覧会のコンセプト文で、多様な存在が集えるような「話し合いのテーブル」というイメージが掲げられていますが、そのテーブルには誰がつけるのか、ということですね。そういう意味では「テーブル」の比喩でいいんですかね? テーブルと言っている時点で、みんなちゃんと椅子に座れるひとだろうし、きちんとスーツ着てそうですよね。
塚本:そこは「遊び場」に言い換えましょう(笑)。
久保:でも「遊び場」っていう表現も今は結構きつくないですか? 今年、ゼミで教えている学生に「遊び」というテーマで調べてもらったのですが、公園とかスポーツ観戦のようなきっちり枠が区切られた安心安全な場所しか出てこないんですよね。「夜遊び」も「火遊び」も出てこない。「遊び」のイメージに遊びがなくなってる。ちょっと前まで「遊び場」というのは安心でも安全でもないところだったじゃないですか。安心安全ではないものを「危険」とか「リスク」とは違う言葉で表せないか、ということは考えてみたいですね。
塚本:そう。遊び場こそ、再生されなければいけない。
ーー今回の展示を見て、気になったことがあれば教えてください。

久保:しいて言えば「家族」が見あたらないことですかね。伝統的に人類学では、現実を構成する枠組や力動を考える際の重要な準拠点として親族関係が研究されてきました。その力がどんどん弱体化して家族の人数も減っていき、夫婦と子供の三角形に縮減され、その隙間に行政と市場経済がじゃかじゃか入り込んでくる、というのが近代社会の一つの側面なわけですが、今回の展示はそういう傾向をさらに進めているようにも見えます。僕は個々の展示のなかで再構成された建築空間を生きる主体として、単身の人間しか想像できませんでした。結婚しているかどうかに関わらず、五体満足でケアも必要ではなく、意図と自覚を持って他者と積極的に関わっていけるような人物。自転車に乗っている人の視点から都市をデザインするというのは魅力的だとは思うんですけど、自転車に乗れない人はどうなるんだろうって。
塚本:なるほどね。
久保:自立的じゃない繋がりもまたありふれたものではないでしょうか。ご飯を食べさせてもらうとか、お風呂に入れてもらうとか。家族というのは、そうした受動的な関係の拠点なわけですが、今回の展示にはその居場所が見あたらなかったですね。
塚本:企画の最初の頃は家族についても議論していました。キュレーターの千葉学さんと私が、それぞれ高齢の親のための家を建てたばかりだったこともあって、高齢化やケアについてもよく議論しました。「資源的人」というコンセプトもありました。「人的資源」という言葉があるじゃないですか。管理者目線でイヤだなと思って、語順をひっくり返して「資源的人」という言葉を作りました。エネルギーでも食べ物でも、身の回りの環境から自分で取り出せる人。そういう人には道具やスキルが必要で、それは元気な人ということになってしまったわけですね。
久保:「元気に生きていこうぜ」だけでは結構つらいですよね。いつのまにか「持続可能性」って全面的に良いことみたいになってますけど、ずっと持続可能でなきゃならないって死ねないってことですからね。「いかに死ぬか」、「いかに終わりにするか」といったことが、どんどん語りにくくなっているように思います。
ーー「How is Life?」のパート2でやりましょう。
塚本:「How is Death?」ですね(笑)ぜひやりましょう。
塚本:なるほどね。
久保:自立的じゃない繋がりもまたありふれたものではないでしょうか。ご飯を食べさせてもらうとか、お風呂に入れてもらうとか。家族というのは、そうした受動的な関係の拠点なわけですが、今回の展示にはその居場所が見あたらなかったですね。
塚本:企画の最初の頃は家族についても議論していました。キュレーターの千葉学さんと私が、それぞれ高齢の親のための家を建てたばかりだったこともあって、高齢化やケアについてもよく議論しました。「資源的人」というコンセプトもありました。「人的資源」という言葉があるじゃないですか。管理者目線でイヤだなと思って、語順をひっくり返して「資源的人」という言葉を作りました。エネルギーでも食べ物でも、身の回りの環境から自分で取り出せる人。そういう人には道具やスキルが必要で、それは元気な人ということになってしまったわけですね。
久保:「元気に生きていこうぜ」だけでは結構つらいですよね。いつのまにか「持続可能性」って全面的に良いことみたいになってますけど、ずっと持続可能でなきゃならないって死ねないってことですからね。「いかに死ぬか」、「いかに終わりにするか」といったことが、どんどん語りにくくなっているように思います。
ーー「How is Life?」のパート2でやりましょう。
塚本:「How is Death?」ですね(笑)ぜひやりましょう。

久保明教 Akinori Kubo
人類学者。1978年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科単位習得退学。博士(人間科学)。現在、一橋大学社会学研究科教授。主な著書に『ロボットの人類学 20世紀日本の機械と人間』(世界思想社、2015年)、『機械カニバリズム 人間なきあとの人類学へ』 (講談社選書メチエ、2018年)、『ブルーノ・ラトゥールの取説 アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019年)、『「家庭料理」という戦場: 暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020年)など。
ノンモダニズムへの実践
展示されているプロジェクトは実に様々だ。世界の各都市で始まっている最新の都市デザインもあれば、「茅葺普請」や「石積み学校」など身近な環境をつくる技術の実践がある。自宅の浴場を銭湯として地域の人々に開放した「神水公衆浴場」のような小さな半公共的施設の取り組みもある一方で、ヨナ・フリードマンや菊竹清訓といった著名な建築家による過去の都市提案も採り上げられている。
これらは、まとまりとなって何を伝えようとしているのか?
ヒントになるのは、プロジェクト群をつないだ展示となっている「Tool Shed」(写真1)だ。これには、それぞれのプロジェクトの現場で使われている道具が集められている。かつてのル・コルビュジエは、建築をつくるのに自動車や飛行機といった機械を参照しようとしたが、この展覧会のキュレーター・チームは機械と人間の間にある道具というものに着目する。
その意味で自転車もまた、機械と人間の中間にあるものといえる。千葉学による展示「Bicycle Urbanism」(写真2)は、自転車という交通手段を主とすることで、都市はこのように変わるのだと提案する。またチューリッヒの「Bikeable」では、自転車に適した都市を実現するために、サイクリストの日常的な体験から改善を進めていくプロセスを示す。生活環境における人間と機械の関係が、ここでは考え直されている。
都市と農業の関係もまた、重要な問い直しのテーマである。ロッテルダムの「Floating Farm」は水の上に浮かぶ農場で、土地がなくても都市に接して食料を生み出せることを示す。ビルや工場に農地が混然と絡んでいる光景を描いたのが、「Capital Agricole」のヤン・ケビのドローイングで、新しい都市のヴィジョンを提示したものとして感動的だ。未来都市といえば、空中ブリッジでつながれた超高層ビルが林立し、その間をエアカーが行き来するようなイメージがまず思い浮かぶ。こうした未来都市像は20世紀の初めにはすでにあって、それがいまだに人々の頭に刷り込まれているが、その描き換えが、ようやく行われようとしているのかもしれない。
会場で参考文献として挙げられている著作のひとつが、ブルーノ・ラトゥール『虚構の「近代」』だ。ラトゥールは、人間に限らないさまざまなアクターが相互に関係しあって世界ができているというアクターネットワーク論をとなえ、科学や技術も人間と独立して存在するものではなないとする。そして、近代という科学的なものの見方に準拠したモダニズムも、それを批判して文化的なもの見方に重きを置いたポストモダニズムも否定し、近代という枠組み自体を捨てたノンモダニズムを提唱する。
この展覧会で紹介されているのは、そんなノンモダニズムの建築や都市を探ろうとする試みなのだろう。そこでは建築家とプロジェクトの関係も変わる。建築家はプロジェクトにあくまで外側からかかわるものだったが、ここで展示されているプロジェクトの多くは、建築家が内側に入り込んで実践に加わっている。
例えば「小さな地球」は、古民家の再生や棚田での耕作などを通じて、自律的な生活の場をつくっていこうという活動で、キュレーターのひとりである塚本由晴が設立や運営に参画している。塚本はかつて、貝島桃代、黒田潤三らとともに「メイド・イン・トーキョー」というリサーチ・プロジェクト行い、「アーキテクチャー・オブ・ザ・イヤー1966 革命の建築博物館展」で展示を行った。それは都市で目にする建物を冷徹な視線でとらえた観察の記録だったが、30年という年月を経て、里山での実践という対極の位置へと自らをずらした。
ここから建築や都市は変わっていくのだ。そんなことを感じさせる展示だった。
これらは、まとまりとなって何を伝えようとしているのか?
ヒントになるのは、プロジェクト群をつないだ展示となっている「Tool Shed」(写真1)だ。これには、それぞれのプロジェクトの現場で使われている道具が集められている。かつてのル・コルビュジエは、建築をつくるのに自動車や飛行機といった機械を参照しようとしたが、この展覧会のキュレーター・チームは機械と人間の間にある道具というものに着目する。
その意味で自転車もまた、機械と人間の中間にあるものといえる。千葉学による展示「Bicycle Urbanism」(写真2)は、自転車という交通手段を主とすることで、都市はこのように変わるのだと提案する。またチューリッヒの「Bikeable」では、自転車に適した都市を実現するために、サイクリストの日常的な体験から改善を進めていくプロセスを示す。生活環境における人間と機械の関係が、ここでは考え直されている。
都市と農業の関係もまた、重要な問い直しのテーマである。ロッテルダムの「Floating Farm」は水の上に浮かぶ農場で、土地がなくても都市に接して食料を生み出せることを示す。ビルや工場に農地が混然と絡んでいる光景を描いたのが、「Capital Agricole」のヤン・ケビのドローイングで、新しい都市のヴィジョンを提示したものとして感動的だ。未来都市といえば、空中ブリッジでつながれた超高層ビルが林立し、その間をエアカーが行き来するようなイメージがまず思い浮かぶ。こうした未来都市像は20世紀の初めにはすでにあって、それがいまだに人々の頭に刷り込まれているが、その描き換えが、ようやく行われようとしているのかもしれない。
会場で参考文献として挙げられている著作のひとつが、ブルーノ・ラトゥール『虚構の「近代」』だ。ラトゥールは、人間に限らないさまざまなアクターが相互に関係しあって世界ができているというアクターネットワーク論をとなえ、科学や技術も人間と独立して存在するものではなないとする。そして、近代という科学的なものの見方に準拠したモダニズムも、それを批判して文化的なもの見方に重きを置いたポストモダニズムも否定し、近代という枠組み自体を捨てたノンモダニズムを提唱する。
この展覧会で紹介されているのは、そんなノンモダニズムの建築や都市を探ろうとする試みなのだろう。そこでは建築家とプロジェクトの関係も変わる。建築家はプロジェクトにあくまで外側からかかわるものだったが、ここで展示されているプロジェクトの多くは、建築家が内側に入り込んで実践に加わっている。
例えば「小さな地球」は、古民家の再生や棚田での耕作などを通じて、自律的な生活の場をつくっていこうという活動で、キュレーターのひとりである塚本由晴が設立や運営に参画している。塚本はかつて、貝島桃代、黒田潤三らとともに「メイド・イン・トーキョー」というリサーチ・プロジェクト行い、「アーキテクチャー・オブ・ザ・イヤー1966 革命の建築博物館展」で展示を行った。それは都市で目にする建物を冷徹な視線でとらえた観察の記録だったが、30年という年月を経て、里山での実践という対極の位置へと自らをずらした。
ここから建築や都市は変わっていくのだ。そんなことを感じさせる展示だった。

写真1 GALLERY 1展示風景 中央「Tool Shed」
©Nacása & Partners Inc.
©Nacása & Partners Inc.

写真2 GALLERY 2展示風景 手前「BicycleUrbanism」
©Nacása & Partners Inc.
©Nacása & Partners Inc.
磯達雄 Tatsuo Iso
編集者・1988年名古屋大学卒業。1988~1999年日経アーキテクチュア編集部勤務後2000年独立。2002年~20年3月フリックスタジオ共同主宰。20年4月から宮沢洋とOffice Bungaを共同主宰。
https://bunganet.tokyo/
https://bunganet.tokyo/

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。