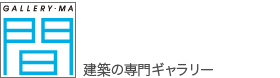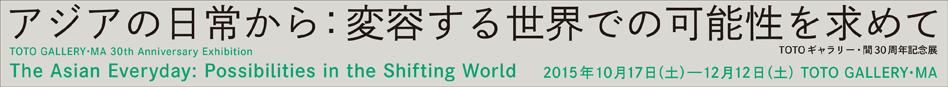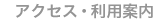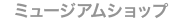- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO

「アジアの日常から :変容する世界での可能性を求めて」と題された今回の展覧会では、出展作家が日本の各地を訪れるという新しい試みがなされ、リン・ハオさんが札幌で講演をするという今回の機会に結実した。講演会に先だって行われた3日間に及ぶ学生ワークショップ(これについてもどこかで発信できればと思う)も含めると、たくさんの時間をリン・ハオさんと過ごした。どこまでも誠実で建築の文化性を信じるリン・ハオさんに教わったことは数え切れないが、本レポートを通してそのほんの一部でも共有することができれば幸いである。
「Towards an old Landscape」と題する講演会は、リン・ハオさんが”建築をどうつくるか”ということよりも大事にしている”環境をどう捉えるか”というところから始まった。人やモノが風に運ばれるように行き着くシンガポールは、周辺の地域とは異なるまったく新しいコンセプトを持っているという。それは一体どんなもので、その中でリン・ハオさんはどのような実践をしているのだろうか。
リン・ハオさんはまず、自身の経験と記憶の大切さを説き、原体験とも言えるいきいきとした3つの空間体験を紹介する。
1つ目は幼少期を過ごしたマレーシアの典型的なコンパウンドハウス。木造2階建てのこの住宅の1階部分は、周囲の庭と連続した柱だけのオープンなスペースで、家具やモノのレイアウトによって自由に居場所をつくることができる。2つ目は、大学卒業後に初めて勤めたシンガポールのオフィス。覆いのかかった吹き抜けの中庭が特徴的で、そこには光が降り注ぎ、雨が入り込み、樹々が生い茂る。動線の中心でもあるその場所には自然に人が集まり、天気の良い日に食事をしたり、休憩やおしゃべりをしたり、外の変化に合わせて思い思いに過ごす。3つ目は、ジャングルに埋もれた友人のアーティストの住まいで、少しづつ建て増された居室やハナレ、それらをつなぐ小径、植えられた樹々がひとまとまりの環境として成長してゆく。ジャングルとのエネルギッシュなつながりのままに。3つの例はどれも周辺環境と住まい手の生活が密接に関係していて、環境とのみずみずしい関係性に開かれている。

そうした快楽的なオープンさは、東南アジアのトロピカルな気候に支えられた、一見すると楽観的でイノセントな態度に見えなくもない。ところがリン・ハオさんの建築は、変わりゆくシンガポールの風景に対する批判的な実践だということが、続くディスカッションを通して次第に明らかになってゆく。講演会のタイトルに含まれている「old Landscape」とは、例えばインドネシアや香港、シンガポールの古いエリアを歩いた時に感じるような、歓びに溢れ、快楽的な雰囲気で、必要に応じて設けられた庇や植物といった、即物的なものが織りなす風景をいう。リン・ハオさんは、そうした風景が”環境を使う”ことによって生まれるものだと分析する。一方、現在のシンガポールの日常はというと、常に急かされ、室内はどこもかしこもエアコンで完全にコントロールされている。それに慣れてしまった人々にとって、外は出たくない不快な場所になってしまった。外に出る、外にいるという感覚の喪失は、知らぬ間に身の回りの環境や社会的なものとの関わりの喪失へとつながっていく。リン・ハオさんは、そうした状況を苛立ち、徹底的にオープンな建築をつくることで批判的に乗り越えようとしているように見える。環境との繋がりを回復するためには、自分たちのライフスタイルを変えてゆくことも厭わないという迫力で。「old Landscape」がそうであるように、リン・ハオさんはユーザーの目線からいかに”環境を使うか”を考え、住まい手が即物的に応答できる余地を残す。光や風や雨や植物を建築に招き入れ、それぞれがのびのびいられる寛容な状態は、同時に住まい手に”環境を使う”さまざまなきっかけを提供しているのだ。


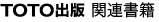
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。