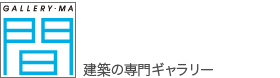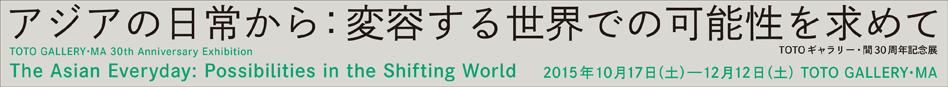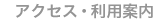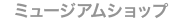- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

シンポジウムレポート
「アジアの日常」は建築を超えるか
レポーター=岩元真明
「会話は空気」という一言からシンポジウムは開始された。キュレーターのエルウィン・ビライは、電車の中吊り広告で見つけたこのフレーズから霊感を得て、名状しがたい何かによって緩やかにつながる5組の建築家――タイのチャトポン・チュエンルディーモル、シンガポールのリン・ハオ、ベトナムのヴォ・チョン・ギア、日本の大西麻貴と百田有希(o+h)、中国のチャオ・ヤン――の合同展を構想したという。ビライは彼らが活動する都市を訪れ、次々と新しい問いを発見してゆく。八百屋のように開けっぴろげな東京のo+hのオフィスでは内外の関係に思いを馳せ、シンガポールのインド人街では超高密度の可能性をとらえ、中国・大理市では――鍋の具材の並び方から発想を得て――序列性を思い、ベトナムの竹建築からは素材の力を、雑種的に事物が混在するタイの街角からは境界性というキーワードを発見する。飾り気のないスナップショットを通じて追体験されるビライの眼差しは、まさに「アジアの日常」に向けられている。
「会話は空気」という一言からシンポジウムは開始された。キュレーターのエルウィン・ビライは、電車の中吊り広告で見つけたこのフレーズから霊感を得て、名状しがたい何かによって緩やかにつながる5組の建築家――タイのチャトポン・チュエンルディーモル、シンガポールのリン・ハオ、ベトナムのヴォ・チョン・ギア、日本の大西麻貴と百田有希(o+h)、中国のチャオ・ヤン――の合同展を構想したという。ビライは彼らが活動する都市を訪れ、次々と新しい問いを発見してゆく。八百屋のように開けっぴろげな東京のo+hのオフィスでは内外の関係に思いを馳せ、シンガポールのインド人街では超高密度の可能性をとらえ、中国・大理市では――鍋の具材の並び方から発想を得て――序列性を思い、ベトナムの竹建築からは素材の力を、雑種的に事物が混在するタイの街角からは境界性というキーワードを発見する。飾り気のないスナップショットを通じて追体験されるビライの眼差しは、まさに「アジアの日常」に向けられている。

展覧会とシンポジウムのタイトルになった「アジアの日常から」というフレーズは、出展者全員が参加したミーティングで決められたという。会場デザインを担当した藤原徹平は、個性の強い5組の建築家の間で議論が紛糾し、まずは「使いたくない」言葉が決まったと回想している。それは「未来」と「新しい」という言葉である。だとすれば、彼らにとっての「日常」とは「未来」ではなく「新しく」もない何かということになる。
そんなことを考えていたら、後日ある研究者が「monumental(記念碑的)」と「everyday(日常)」という言葉を対比しているのを見つけた。記念碑とは、ある一瞬を凍結させることで記念碑たりうる。対して、日常とは一瞬の現在ではなく、繰り返される現在というわけだ。この繰り返される現在というのは、個々人の経験に依存するわけで、実際のところ「空気」のように捉えどころのない存在である。
だからであろうか。「アジアの日常」というテーマに対する出展者の回答は見事なまでに異なっていた。リン・ハオの建築にみられる公園の散歩道を歩くような動的体験は、自然と人工性が溶け合ったシンガポール独特の日常風景を思わせる。一方、ベトナムのヴォ・チョン・ギアは「緑が少なく」、「人々が活発さを失った」大都市の日常に危機感をもって接し、緑が建物を凌駕する住宅や、自然と人工の境界を曖昧にする竹構造建築を発表している。「緑」や「竹」という素材を共有しながらも、この二者の表現はきわめて対照的である。そこに地域性の違いを見るのは容易だが、むしろ二人の作家の世界観の違い、すなわち「日常」の捉え方にこそ本質的な差異があるように思えた。中国のチャオ・ヤンも大都市に対して批判的である。ただし、ギアのように大都市に挑戦するのではなく、距離を置くことを選んでいる。過剰な投資が渦巻く北京や上海をあえて避け、「建築家が一人もいなかった」大理市を活動拠点とするチャオ・ヤンは、長い歴史をもつ地方都市にこそ残された「中国的なるもの」を日常として受け止めているのだ。それゆえ、彼の創作は地場の素材を利用し(大理市は大理石の語源である)、地元の職人との対話を通じて行われる。直角と箱形を基本とする造形は、差異を競い合う大都市のアイコン建築とは対照的に静謐である。
そんなことを考えていたら、後日ある研究者が「monumental(記念碑的)」と「everyday(日常)」という言葉を対比しているのを見つけた。記念碑とは、ある一瞬を凍結させることで記念碑たりうる。対して、日常とは一瞬の現在ではなく、繰り返される現在というわけだ。この繰り返される現在というのは、個々人の経験に依存するわけで、実際のところ「空気」のように捉えどころのない存在である。
だからであろうか。「アジアの日常」というテーマに対する出展者の回答は見事なまでに異なっていた。リン・ハオの建築にみられる公園の散歩道を歩くような動的体験は、自然と人工性が溶け合ったシンガポール独特の日常風景を思わせる。一方、ベトナムのヴォ・チョン・ギアは「緑が少なく」、「人々が活発さを失った」大都市の日常に危機感をもって接し、緑が建物を凌駕する住宅や、自然と人工の境界を曖昧にする竹構造建築を発表している。「緑」や「竹」という素材を共有しながらも、この二者の表現はきわめて対照的である。そこに地域性の違いを見るのは容易だが、むしろ二人の作家の世界観の違い、すなわち「日常」の捉え方にこそ本質的な差異があるように思えた。中国のチャオ・ヤンも大都市に対して批判的である。ただし、ギアのように大都市に挑戦するのではなく、距離を置くことを選んでいる。過剰な投資が渦巻く北京や上海をあえて避け、「建築家が一人もいなかった」大理市を活動拠点とするチャオ・ヤンは、長い歴史をもつ地方都市にこそ残された「中国的なるもの」を日常として受け止めているのだ。それゆえ、彼の創作は地場の素材を利用し(大理市は大理石の語源である)、地元の職人との対話を通じて行われる。直角と箱形を基本とする造形は、差異を競い合う大都市のアイコン建築とは対照的に静謐である。


(上左)リン・ハオ(上右)チャオ・ヤン(下)ヴォ・チョン・ギア
しかし今度は都市の日常を抱擁する建築家が登場する。チャトポンはバンコクにあるセックス・モーテルや出稼ぎ労働者住居などを「バンコクの私生児」と呼び、その構成や空間性を分析して創作のインスピレーション源としている。また、古材や日用品をユーモラスに転用する材料の使い方もブリコラージュ的かつ都市的である。他方、日本のo+hは「まちの人々」の日常に自ら飛び込むことを通じて「強度のある」建築をつくることを模索している。建具が一切なく、シャッターを開けると街とダイレクトにつながる彼らのオフィスは、まさにこの態度表明である。続くディスカッションでは、チャトポンとo+hの視点の違いが藤原によって指摘された。人々の営みと関係を取り結ぶ点では一致しているが、チャトポンは「冷静な観察者」の姿勢を崩さず、o+hは「状況に巻き込まれている」というのだ。この視点の相違は、タイと日本の状況の違いから発しているのかもしれない。タイでは、矛盾をはらみつつも都市は発展を続けている。一方、大西は3.11以降の日本において「新しい建築はもはや必要ではないという流れがある」と述べた上で、建築が必要となる状況を生み出すべく人々の生活に入り込む、という方法論を提示している。つまり、チャトポンは日常を設計に活かし、o+hは日常から建築の存在理由を探っているのである。

(左)チャトポン・チュエンルディーモル(右)大西麻貴+百田有希
ところで、過去にも世界中で多くの建築家が「日常という他者」を「建築」に取り込むことを目指してきた。ラスベガスのストリップのように醜く凡庸(アグリーでオーディナリー)な構築物を礼讃したヴェンチューリはその代表格である。5組の建築家もまた同様だろうか。ある者は「日常」という「他者」に寄り添う建築をつくり、ある者は衝突し、ある者は転換させ、ある者は存在の根拠とする...?
いや、そうではないだろう。
状況は反転している。5組の建築家にとっては「アジアの日常」こそが「自己=主体」であり、「建築」こそが「他者」なのではないだろうか。アジアの国々にとって、西洋に由来する「建築」という概念はそもそも黒船的な他者である。「建築」の受容から一世紀以上を経て、アジアの創作者たちは仮初めの「自己」を「他者」へと反転させ、真にオリジナルな表現を模索しているのかもしれない。
いや、そうではないだろう。
状況は反転している。5組の建築家にとっては「アジアの日常」こそが「自己=主体」であり、「建築」こそが「他者」なのではないだろうか。アジアの国々にとって、西洋に由来する「建築」という概念はそもそも黒船的な他者である。「建築」の受容から一世紀以上を経て、アジアの創作者たちは仮初めの「自己」を「他者」へと反転させ、真にオリジナルな表現を模索しているのかもしれない。
岩元真明 Masaaki Iwamoto
首都大学東京特任助教、九州大学非常勤講師、修士(工学)、一級建築士
1982年東京都生まれ。2005年東京大学工学部卒業。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011~15年Vo Trong Nghia Architectsパートナー兼ホーチミン事務所ディレクター。2015年より現職。設計実務と東南アジア建築の研究を行っている。
1982年東京都生まれ。2005年東京大学工学部卒業。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011~15年Vo Trong Nghia Architectsパートナー兼ホーチミン事務所ディレクター。2015年より現職。設計実務と東南アジア建築の研究を行っている。
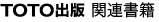
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。