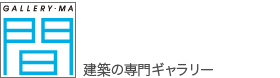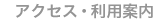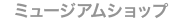- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

講演会レポート
「植物のような開放性」
レポーター=髙橋一平
黄聲遠(ホァン・シェン・ユェン)さんの建築を、この機会にはじめて知ることができた。
講演会は、拠点である宜蘭の風土や人々の反抗精神の話、亀と蛇の神話、土を握り味と匂いによって今年の作物を慎重に選ぶ農夫の話、そして最初の仕事となるバスケットゴールの設計から始まり、活動が少しずつ等身大で次第に広がっていく様子が、静かにぱっぱと紹介されていった。牛小屋の改修、小道や歩行橋、銀行のコンバージョン、本屋の改装、高架下のヒューマンな活用方法、治水、親水公園など、プロジェクトが紹介されていくリズムは、カテゴリーに関わらず黄さんがまるで本能的かつ独自の倫理感をもとに活動の手を伸ばし、あれよあれよという間に彼の仕事が宜蘭に拡がっていくそのさまをそのまま映し出しているようであった。実に淡々としていて、まるで映画の導入シーンのようだった。「維管束」という例えを用いているように、植物的に拡大してゆく。中には植物形態を彷彿とさせる建築言語も用いられるが、建築家の姿勢自体が、これまでの人間的欲望を剥き出しに活動してゆくそれとは少し異なった、植物的な開放性を持ち合わせており、それこそが彼の個性であると感じた。独自の感受性によって環境からの刺激に反応し、逆に全く反応しないこともある(会場からの質問の一部に対してそのような感じだった)その態度も何というか植物的である。全て自己を拠り所に自発的に、率直に言動が繰り出され、それゆえにむしろ活動がどこまで拡張発展していくのかわからない、植物のような無限性を秘めている。
黄聲遠(ホァン・シェン・ユェン)さんの建築を、この機会にはじめて知ることができた。
講演会は、拠点である宜蘭の風土や人々の反抗精神の話、亀と蛇の神話、土を握り味と匂いによって今年の作物を慎重に選ぶ農夫の話、そして最初の仕事となるバスケットゴールの設計から始まり、活動が少しずつ等身大で次第に広がっていく様子が、静かにぱっぱと紹介されていった。牛小屋の改修、小道や歩行橋、銀行のコンバージョン、本屋の改装、高架下のヒューマンな活用方法、治水、親水公園など、プロジェクトが紹介されていくリズムは、カテゴリーに関わらず黄さんがまるで本能的かつ独自の倫理感をもとに活動の手を伸ばし、あれよあれよという間に彼の仕事が宜蘭に拡がっていくそのさまをそのまま映し出しているようであった。実に淡々としていて、まるで映画の導入シーンのようだった。「維管束」という例えを用いているように、植物的に拡大してゆく。中には植物形態を彷彿とさせる建築言語も用いられるが、建築家の姿勢自体が、これまでの人間的欲望を剥き出しに活動してゆくそれとは少し異なった、植物的な開放性を持ち合わせており、それこそが彼の個性であると感じた。独自の感受性によって環境からの刺激に反応し、逆に全く反応しないこともある(会場からの質問の一部に対してそのような感じだった)その態度も何というか植物的である。全て自己を拠り所に自発的に、率直に言動が繰り出され、それゆえにむしろ活動がどこまで拡張発展していくのかわからない、植物のような無限性を秘めている。

印象的だったのは、「歩行橋の幅が少し狭いことが人々のコミュニケーションを生み出し、夜間照明を少し暗くすることで鳥が集まる」のであり、「われわれは必要な分だけ(ささやかに)環境に介入すべきである」という思想、「自分さえ良ければいいという発想では、その都市は廃れる」といった、自然に対する人工物の介入の「程度」を問題としている考え方に、ひやりとさせられたし、共感した。思えば、日本で生きる私たちにとって、プロジェクトの種類が建築/土木/内装/外構、もしくは修復/改修/転用というように、大鉈を振りかざしてジャンルに分断され、分野が孤立したことを良いことに専門家が経験を武器に大袈裟に介入していく、その閉鎖的分業の仕切りの中で活動せざるをえない状況に、彼の言葉で改めて気付かされた。もしかしたら2011年に起きた東日本大震災の復興も、そうした思想さえもリセットされていたら、もっと可能性を拡げられたのかもしれない、と改めて思う。コンクリートに理不尽に分断(機能主義的に建てられた都市の外壁や間仕切壁)され、オルタナティブな可能性や自由を阻害された近代的都市活動と比べると、黄さんによる宜蘭の更新の有り様は遥かにダイナミックだ。しかし、話を聞いていると、黄さんにも宜蘭なりの同様の問題があり、政府への反抗を繰り返して今のデザインに統合されていくのだそうだ。興味深いのはそうした制度に対し全否定するのではなくて、「程度」を抑えることが重要であるという、物事の「性質」に着目した柔軟な思想に着地する点である。すなわち「都市と田園(自然ということと解釈)の双方からヒントを得る」という理念、その結果としてプロジェクトのアウトプットは、双方の調停によって生み出されたユーモアや楽観精神に満ち溢れている。
レクチャー後の質疑の際には「頭の固い政府との戦いは比較的簡単」なのであって、どちらかというと一緒に活動しているフィールドオフィス・アーキテクツの若い人々との「交流」の中から一筋の考えを導き出す方がよほど難しいと言う。これは台湾からアメリカへ渡りエリートな経歴を辿り、また宜蘭でも様々な困難を乗り越えた人物ならでは、と言えるかもしれない。つまり、政府との戦いは経験により克服可能だが、戦いにより既成概念を解体した後たちまち訪れる新しい創造の機会における行動の選択こそセンスが試され、最も慎重さを極めた難しい行為なのである。
レクチャー後の質疑の際には「頭の固い政府との戦いは比較的簡単」なのであって、どちらかというと一緒に活動しているフィールドオフィス・アーキテクツの若い人々との「交流」の中から一筋の考えを導き出す方がよほど難しいと言う。これは台湾からアメリカへ渡りエリートな経歴を辿り、また宜蘭でも様々な困難を乗り越えた人物ならでは、と言えるかもしれない。つまり、政府との戦いは経験により克服可能だが、戦いにより既成概念を解体した後たちまち訪れる新しい創造の機会における行動の選択こそセンスが試され、最も慎重さを極めた難しい行為なのである。

日本でも最近、地域に根ざした建築家による活動が取り上げられているが、私自身の興味として、彼の姿勢が個性的と思われる点を整理してみた。ひとつは、ほぼ全てがパブリックのプロジェクトであり、ブルジョア邸宅のようなものは一切含まれていないこと。そして個人よりも公共が上位であるべきと強く唱えている(著書より)点。ふたつ目に設計事務所のボスの着想が大勢のスタッフを支配する、いわば軍隊型アトリエ事務所ではなく、創造はスタッフとの「交流」の過程にあり、設計事務所を「建築学校」とまで位置づける点。これまでのストイックな建築家には無いケースだろう。3つ目に、その結果なのかどうかはわからないけれど、モダニズム的趣向で地域性と普遍性を同時に獲得する、いわば批判的地域主義の終末的な様態が前面に押し出されるのとは異なり、彼らの建築形態はあるひとつの形式・様式には回収されにくい点。これには、レクチャーの途中で出て来た「新しい故郷をつくる」という言葉がヒントになった。彼による宜蘭のプロジェクトは、地域性の歴史的な性質を「適切に」アップデートした現代建築の姿を期待させる。だがしかし、2000年代以降、次第に規模も大きくなりはじめ(羅東文化工場〜櫻花陵園D区納骨廊〜雲門新家)、宜蘭での一連のプロジェクトと比べると、アメリカで培われたと思われる(ご本人も言及されている)ニュアンスも時折現れる。そして、これが黄さんの建築に現れる力強さの根拠と成っているよう見えた。これについては正直なところ、わからなかった。

質疑では、世界の建築家の中に自身が位置づけられることに言及するのを避け、「ただの地域主義では決してなく、どこでも建築への熱意があるだけ」と言う。宜蘭で息を潜め、自身の活動を他の建築家と比較・対象化する素振りを少しも見せず、直面する矛盾や、立ち現れるプロジェクトに真摯に集中していく姿勢を表明する一方で、プロジェクトの必然性(建築の動機)と建築表現の「程度」の一致というものに敏感に反応し、建築家への大いなる期待が込められたフィールドではそれに相応しい形態で建築表現を揮うという、非常に思慮深くもあり、柔軟でパワフルな建築家なのだと、講演会の途中で思索をシフトさせた。いずれにせよ私自身の中に最も強く印象に残ったのは、インテリアや建築や土木といった、ありがちな分類を感じさせない、生活と等身大で自然につながった、流動的そしてダイナミックで、交流を重んじる黄さんの姿勢それ自体である。
髙橋一平 Ippei TAKAHASHI
1977年
東京都出身
2002年
横浜国立大学大学院修了
2002-09年
西沢立衛建築設計事務所入社
2009年
髙橋一平建築事務所設立
2011年-
横浜国立大学大学院Y-GSA設計助手, 現在助教
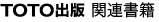
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。