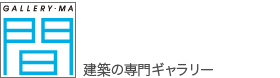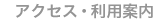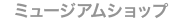- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

コラム
「建築のすそ野を広げたい」という想いで設立された編集事務所Office Bungaの磯達雄さんの視点から、「ドットアーキテクツ展 POLITICS OF LIVING」をより深く楽しむのに役立つ情報をお届けします。
家成俊勝×アリソン理恵対談「ちょっと建築ができる普通のオッチャン」
設計事務所でありながら、建物の施工にも積極的にかかわり、そればかりか映画、舞台、パフォーマンス、バーの運営、畑仕事など、多方面にわたる活動を、多様な人々と実践しているドットアーキテクツ。その活動に共感を寄せる一人が、アリソン理恵さんだ。アリソンさんは建築の設計を行う一方、東京・豊島区の東長崎駅近くにカフェ「MIA MIA」を開いて、遠方からも訪れるコーヒー好きと地域の人々をつなぐ拠点としている。ドットアーキテクツの家成俊勝さんとの対談で、建築家は今、何ができるのかについて、語り合ってもらった。聞き手は磯達雄(建築ジャーナリスト)。
ーー展覧会を見ての感想から聞かせてください。
アリソン:会場へ入ったときに、まずびっくりしました。ネオンサインとミラーボールがあって、エレベーターで降りる階を間違えたかとも思いました(笑)。展示をぐるっと見て回って、最後にまた映画上映でしょう。これまでもドットアーキテクツの活動を横目で見ながら、建築とは言えないレベルのものも含めて、楽しいことを追求しているな、とずっと感じていました。その雰囲気がよく現れていました。
家成:ありがとうございます。
アリソン:ドットアーキテクツ展の前の「How is Life?」展で展示デザインを担当しました。その時にキュレーターの一人である塚本由晴さんが、「今は建築家が正しいと思うことをほとんどできない時代だ」と言っていたのが、耳に付いて離れません。例えば土に還る材料でつくった方がいいとか、地域の人たちと一緒につくりたいとか、そういうことをやろうとしても産業としての建築という枠組みではとても難しくなっていて、だから建築作品に限定せずアートとか、建築ではない活動によって、本来、建築にできることは何かを考え直し、議論を引きだす。展覧会というのはそういう場としても重要だ、とおっしゃっていたんですね。
家成:そういうことは僕も感じますね。建築もそうだし、今の社会で暮らすことがこと自体が、非常に息苦しいことになってきている。制度がそうなっている面もあるし、明文化されていないけど受けているプレッシャーというのもあります。
ーー展覧会を見ての感想から聞かせてください。
アリソン:会場へ入ったときに、まずびっくりしました。ネオンサインとミラーボールがあって、エレベーターで降りる階を間違えたかとも思いました(笑)。展示をぐるっと見て回って、最後にまた映画上映でしょう。これまでもドットアーキテクツの活動を横目で見ながら、建築とは言えないレベルのものも含めて、楽しいことを追求しているな、とずっと感じていました。その雰囲気がよく現れていました。
家成:ありがとうございます。
アリソン:ドットアーキテクツ展の前の「How is Life?」展で展示デザインを担当しました。その時にキュレーターの一人である塚本由晴さんが、「今は建築家が正しいと思うことをほとんどできない時代だ」と言っていたのが、耳に付いて離れません。例えば土に還る材料でつくった方がいいとか、地域の人たちと一緒につくりたいとか、そういうことをやろうとしても産業としての建築という枠組みではとても難しくなっていて、だから建築作品に限定せずアートとか、建築ではない活動によって、本来、建築にできることは何かを考え直し、議論を引きだす。展覧会というのはそういう場としても重要だ、とおっしゃっていたんですね。
家成:そういうことは僕も感じますね。建築もそうだし、今の社会で暮らすことがこと自体が、非常に息苦しいことになってきている。制度がそうなっている面もあるし、明文化されていないけど受けているプレッシャーというのもあります。

(写真左)家成俊勝氏 (中央)アリソン理恵氏 (右)磯達雄氏
アリソン:塚本さんからそういう話を聞いた後にこの展示を見たので、よりいっそう印象が高まった面もあるかもしれません。普通の建築展だと、建築家のアーカイブとして組み立てられていて、見る側としては「この作品はこういうディテールでつくったんだ」というところが勉強になる。それはそれでいいのだけど、ドットアーキテクツ展は参加型で、自分たちがつくっていないものもいっぱい置いてある。その一方で、リサーチの成果も発表していて、見る側に受け止め方を委ねているところが大きい。議論のもとになるものがたくさん置いてあるというか、突っ込まれるのを待っている状態のものがたくさんある。
家成:突っ込まれやすいのは確か(笑)。その場の状況をよくするための方策として、建築だけではなくて、映画をつくることもあれば、バーもやる。やろうと思えば何でもやるんですけど、すべて産業が生み出すある意味で洗練された消費を促す商品としてのクオリティは低い。そういう意味で突っ込まれやすいんだと思います。
ーードットアーキテクツは「千鳥文化」でバーやイベントスペースを運営していますが、アリソンさんもカフェ「MIA MIA」を経営しています。
家成:突っ込まれやすいのは確か(笑)。その場の状況をよくするための方策として、建築だけではなくて、映画をつくることもあれば、バーもやる。やろうと思えば何でもやるんですけど、すべて産業が生み出すある意味で洗練された消費を促す商品としてのクオリティは低い。そういう意味で突っ込まれやすいんだと思います。
ーードットアーキテクツは「千鳥文化」でバーやイベントスペースを運営していますが、アリソンさんもカフェ「MIA MIA」を経営しています。

コーヒショップ MIAMIA ©yurika kono
アリソン:コーヒー屋をやったり、ギャラリーをやったりしながら気付いたのは、ものづくりに関してはクオリティを上げすぎないほうがいい、ということ。手の込んだことをしてディテールを綺麗にすればするほど、通りがかの人は「これはプロの仕事だから自分に関係ない」という目で見てしまう。当事者意識を持ってもらうには、これだったらウチでもつくれそうとか、つくり方の仕組みが見えるとか、そういうディテールを考えていかないといけない。
家成:それは僕もよく考えますね。ディテールを洗練させていくのではなくて、その逆の方向へ行くこと。非洗練化とでもいうのでしょうか。簡単そうに見えるけど、実は工夫しているという。持っている知識や技術を、そちら側に使っていくというのは、これからとても大切じゃないかな。
アリソン:ドットアーキテクツは自分たちで施工までやるから、つくり方まで常に考えられていますよね。「馬木キャンプ」でも、参加したメンバーが運べる材料でどうやったらつくれるか、構造設計者も交えて知恵を絞り、その結果としてできたものがかっこよくなっている。つくっているものは凡庸じゃないし、プランニングもクリエイティブだけど、ディテールは簡素で、つくり方が目に見える。そういう創造性の発揮の仕方というのは、見習うべきだと思います。
家成:つくり方が見えていると、使っている人が自分でメンテナンスすることもできます。それもとても大事です。
アリソン:それは本当にその通りですね。街中に建っている建物は、ほとんど自分でメンテナンスできない。
家成:できるのはせいぜいがインテリアのペンキを塗るとか、壁紙を買ってきて貼るぐらいでしょう。あとはイケアで家具を買ってきて組み立てるとか。もう少し自分たちでつくれるような状況にしていきたいと思います。
アリソン:ドットアーキテクツを始めたきっかけが、阪神淡路大震災だったと聞いたことがあります。災害に直面して、みんなでつくることの意義をとらえ直したとのことだったかと思いますが、この数年間のコロナ禍で、また考えたことはありますか。
家成:それは結構、ありますね。コロナ禍で今の社会を動かしている経済の仕組みが気になって、とりあえず、お好み焼きがどういう材料でできているのかをリサーチしたんです。小麦はなぜアメリカから輸入してるのか、野菜はどこからここに来ているのか、肉や出汁のコンブはどうなのか、いろいろ調べました。するととても興味深くて、子どもの頃に毎週土曜日に家で出されるお好み焼きは、こんなにも複雑な物流経路をたどって、1枚の鉄板の上に結実しているとわかったんです。なんて複雑なんだろう。それ以来、自分たちがつくるものは、できるだけ近場で調達してつくるようにしようと、心がけるようになりました。今年のヴェチア・ビエンナーレ国際建築展でも、僕らは道具だけ持っていったんです。そして日本館に貯まっていた廃材と、ジャルディニ公園の草木と、外されていた吉阪隆正さんデザインの手すりと、貝島桃代さんが置いていった一輪車荷車と、そういうものを全部使って、即興で再構成するといったやり方を取りました。物でも人でも、出自がわかっているものと直接的に関わっていく方法がいいなということを、コロナ禍を通じて実感したんです。
アリソン:確かにそうですね。社会全体が間接的になっている。
家成:政治も間接民主制で、僕らは選挙で会ったこともない人に投票して、それで選ばれた人が代理として国会で何か言うけど、結局は多数決で決まっていってしまって、民主主義とは思えない。もう少し違う、本来の意味での民主主義のあり方があるだろうと思うんですけど。
ーー今回の展覧会のタイトルにも「POLITICS」という言葉が使われていますね。
アリソン:私もこのごろ、政治という言葉についてよく考えていて、というのもコロナ禍の最中に『日々の政治 ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化』(ピー・エヌ・エフ新社)という本を読んだんです。著者はエツィオ・マンズィーニというデザイン学の研究者で、彼は政治を「日常的な小さな決断」ととらえています。
家成:まさにその通りですね。
アリソン:マンズィーニは「プロジェクト中心の民主主義」というものも唱えていて、民主主義を生き生きとさせるには、プロジェクトをどんどんつくっていくことが必要という話をされています。
家成:プロジェクトとは、どういうことを指しているのだろう。建築をつくることもプロジェクトと言うけど。
アリソン:建築をつくるというと、建築家が現れて、かっこいい作品を設計して、腕のいい職人さんを連れてきて、パシッとつくっていなくなるみたいなイメージだけど、もともとは建てられる場所のその時点での生産力が現れるお祭りみたいな出来事で、材料にしろスキルにしろ、隣のおじさんがこんなのつくれるからつくったみたいなことだったはずです。だから上棟式の時には餅まきして、みんなでお祝いしていた。それがない都市部というのは、なんてつまらないんだろう、と思います。
家成:なるほど。
アリソン:自分のコーヒー屋をつくるときにも、10坪ほどの広さの本当に小さなコーヒー屋なので、近所の人たちだけでつくれるかもしれないと考えたんです。まず工務店に電話したら、「うちは建て売りしかやってません」と断られ、しかたなく商店街を一軒一軒、挨拶に回りながらつくってくれる人がいないか、訊いて回ってたら、ひとりのおばあちゃんが「知り合いにいる」と言ってくれました。それでやってきたのが、85歳のおじいちゃん。そこから知り合いの知り合いみたいな感じで、全員80代の施工チームができました。
家成:それはすごい(笑)。
家成:それは僕もよく考えますね。ディテールを洗練させていくのではなくて、その逆の方向へ行くこと。非洗練化とでもいうのでしょうか。簡単そうに見えるけど、実は工夫しているという。持っている知識や技術を、そちら側に使っていくというのは、これからとても大切じゃないかな。
アリソン:ドットアーキテクツは自分たちで施工までやるから、つくり方まで常に考えられていますよね。「馬木キャンプ」でも、参加したメンバーが運べる材料でどうやったらつくれるか、構造設計者も交えて知恵を絞り、その結果としてできたものがかっこよくなっている。つくっているものは凡庸じゃないし、プランニングもクリエイティブだけど、ディテールは簡素で、つくり方が目に見える。そういう創造性の発揮の仕方というのは、見習うべきだと思います。
家成:つくり方が見えていると、使っている人が自分でメンテナンスすることもできます。それもとても大事です。
アリソン:それは本当にその通りですね。街中に建っている建物は、ほとんど自分でメンテナンスできない。
家成:できるのはせいぜいがインテリアのペンキを塗るとか、壁紙を買ってきて貼るぐらいでしょう。あとはイケアで家具を買ってきて組み立てるとか。もう少し自分たちでつくれるような状況にしていきたいと思います。
アリソン:ドットアーキテクツを始めたきっかけが、阪神淡路大震災だったと聞いたことがあります。災害に直面して、みんなでつくることの意義をとらえ直したとのことだったかと思いますが、この数年間のコロナ禍で、また考えたことはありますか。
家成:それは結構、ありますね。コロナ禍で今の社会を動かしている経済の仕組みが気になって、とりあえず、お好み焼きがどういう材料でできているのかをリサーチしたんです。小麦はなぜアメリカから輸入してるのか、野菜はどこからここに来ているのか、肉や出汁のコンブはどうなのか、いろいろ調べました。するととても興味深くて、子どもの頃に毎週土曜日に家で出されるお好み焼きは、こんなにも複雑な物流経路をたどって、1枚の鉄板の上に結実しているとわかったんです。なんて複雑なんだろう。それ以来、自分たちがつくるものは、できるだけ近場で調達してつくるようにしようと、心がけるようになりました。今年のヴェチア・ビエンナーレ国際建築展でも、僕らは道具だけ持っていったんです。そして日本館に貯まっていた廃材と、ジャルディニ公園の草木と、外されていた吉阪隆正さんデザインの手すりと、貝島桃代さんが置いていった一輪車荷車と、そういうものを全部使って、即興で再構成するといったやり方を取りました。物でも人でも、出自がわかっているものと直接的に関わっていく方法がいいなということを、コロナ禍を通じて実感したんです。
アリソン:確かにそうですね。社会全体が間接的になっている。
家成:政治も間接民主制で、僕らは選挙で会ったこともない人に投票して、それで選ばれた人が代理として国会で何か言うけど、結局は多数決で決まっていってしまって、民主主義とは思えない。もう少し違う、本来の意味での民主主義のあり方があるだろうと思うんですけど。
ーー今回の展覧会のタイトルにも「POLITICS」という言葉が使われていますね。
アリソン:私もこのごろ、政治という言葉についてよく考えていて、というのもコロナ禍の最中に『日々の政治 ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化』(ピー・エヌ・エフ新社)という本を読んだんです。著者はエツィオ・マンズィーニというデザイン学の研究者で、彼は政治を「日常的な小さな決断」ととらえています。
家成:まさにその通りですね。
アリソン:マンズィーニは「プロジェクト中心の民主主義」というものも唱えていて、民主主義を生き生きとさせるには、プロジェクトをどんどんつくっていくことが必要という話をされています。
家成:プロジェクトとは、どういうことを指しているのだろう。建築をつくることもプロジェクトと言うけど。
アリソン:建築をつくるというと、建築家が現れて、かっこいい作品を設計して、腕のいい職人さんを連れてきて、パシッとつくっていなくなるみたいなイメージだけど、もともとは建てられる場所のその時点での生産力が現れるお祭りみたいな出来事で、材料にしろスキルにしろ、隣のおじさんがこんなのつくれるからつくったみたいなことだったはずです。だから上棟式の時には餅まきして、みんなでお祝いしていた。それがない都市部というのは、なんてつまらないんだろう、と思います。
家成:なるほど。
アリソン:自分のコーヒー屋をつくるときにも、10坪ほどの広さの本当に小さなコーヒー屋なので、近所の人たちだけでつくれるかもしれないと考えたんです。まず工務店に電話したら、「うちは建て売りしかやってません」と断られ、しかたなく商店街を一軒一軒、挨拶に回りながらつくってくれる人がいないか、訊いて回ってたら、ひとりのおばあちゃんが「知り合いにいる」と言ってくれました。それでやってきたのが、85歳のおじいちゃん。そこから知り合いの知り合いみたいな感じで、全員80代の施工チームができました。
家成:それはすごい(笑)。

アリソン:誰もEメールを使えないから、手紙でのやり取りになって大変。だけど、手刻みで物をつくってきた職人さんたちなので、何でもつくれるんですよ。それで最後に長さが5mの大きな照明を造作でつくったんですけど、板金屋さんと大工さんと電気屋さんがそれぞれ別に部品をつくってきて、現場で組み立てる段になったら、うまくいきません。思い入れが強すぎて、図面に描いてあるよりもこっちの方がかっこいいだろというのを、それぞれがつくって持ってきちゃったんです。今までだったら「図面通りにつくり直して」と言うだけだったけど、自分の愛情から工夫して持ってきてくれたものに「ノー」と返すのが建築家の仕事だったら、私もう建築やらなくていいかな、と思い始めて……。
家成:確かに。それでどうしたんですか。
アリソン:みんなで工夫して取り付けようという方向になったんです。通りすがりの人まで入ってきて、ああでもないこうでもないと言いながら、結局なんとか吊り込んで完成させました。
家成:本当に、お祭りみたいな感じですね。
アリソン:都心部だと、材料をそのエリアで調達することはほぼ不可能ですけど、スキルは調達できるなとわかりました。塚本さんから釜沼の話(How is Life?展でも展示された「小さな地球」のこと)を聞くと、田舎には色々な資源があっていいな、私も山で丸太を切って建築をつくりたいと、憧れを持ちましたが、いやいや、都会でもできることはあるよね。そんなことに気が付いたんです。そういう人のスキルを集められるプロジェクトをどんどんつくっていくことが、建築家の仕事として求められているんじゃないかとも思って、コツコツ始めているところです。
ーーカフェをやろうと思ったきっかけは何だったんですか。
アリソン:結婚した相手が、コーヒー・フェスティバルみたいなイベントを企画して開催する仕事をずっとやっていたんです。「千鳥文化」でもやらせてもらいました。
家成:ああ、そうでしたね。
アリソン:コーヒー屋をやりたいとずっと前から言われていたんですが、私がtecoにいた時は忙しくてなかなかやれなくて、辞めたタイミングで、物件探しからやり出しました。コーヒーをやるならそれなりに極めようと思って、私もきちんとトレーニングを受けましたよ。別に建築だけがやりたかったわけでもないし。でもコーヒー屋をつくるということは、地域を活性化させるという意味でも、すごく大きな意味がありました。高齢者や子ども達、近所の人たちとの日常的な挨拶や見守りができるので、福祉的な場所にもなっていると思うし。
家成:周りの人が話をしにやって来ますからね。
アリソン:建築なんて、人の生活を豊かにするひとつの手段でしかないです。この展覧会のオープニング・セレモニーで、家成さんは「ちょっと建築ができる普通のオッチャンになりたい」と言っていましたよね。
家成:はい。
アリソン:それは私も一緒です。建築もできるスナックのママでいたい。本当そうなんです。コーヒーも畑仕事も、必要だと思うのでやっているわけですが、それをやっていくと建築家と言えなくなっていくんです。「何なんやろ?」と思ったら、ただの人間なんですよね。
家成:福祉も今や業務としてのサービスになってしまっていますが、アリソンさんが町の中でみんなでやっていくことが、結果的に福祉のようにもなっている。そういう状況の方が、僕も絶対にいいと思います。
アリソン:制度や施設も当然、整えていかなければいけないけど、日常的なアプローチがゼロになってしまうのはまずいでしょう。大きな災害が起こったときにも困りますし。
家成:お金がないとサービスを受けられないというのでは、よくないですね。
アリソン:最近は「街の営繕」というのも始めました。建物を建て替えて、街を良くしていくみたいなことは、絵は描けるけど現実味はありません。何ができるかを考えると、建物の外は割と緩い決まりでできているので、所有の概念さえ少し手放してもらえれば、結構みんなで使える場所ができていく。外だけちょっと間借りして、「何かやらせてくれませんか」という活動です。みんなでコンクリートをはつって植物を植えたり、コンポストをつくってもらったりしています。
家成:めちゃくちゃ面白そうですね。
ーードットアーキテクツはパーティーを積極的に仕掛けていますよね。これはどういう意味ですか。
家成:僕らはパーティーを、プロジェクトのひとつとしてやっています。特にコロナ禍では、家から出られない時期があったし、オンラインばかりでつながっていたので、肉体的な接触がまったくできなくなったじゃないですか。それは非常にまずいなと思っていて、コロナが終息してまた普通に出会えるようになったときに開くパーティーの練習をとりあえずやっておこうと考えて、月に1回、contact Gonzoというアーティスト集団と一緒に、大阪のギャラリーの中でパーティーを続けていました。その中で、丸太からでかい地域通貨をつくったり、ドラァグクイーンからメイクを教えてもらったり、そういうことをやっていました。
家成:確かに。それでどうしたんですか。
アリソン:みんなで工夫して取り付けようという方向になったんです。通りすがりの人まで入ってきて、ああでもないこうでもないと言いながら、結局なんとか吊り込んで完成させました。
家成:本当に、お祭りみたいな感じですね。
アリソン:都心部だと、材料をそのエリアで調達することはほぼ不可能ですけど、スキルは調達できるなとわかりました。塚本さんから釜沼の話(How is Life?展でも展示された「小さな地球」のこと)を聞くと、田舎には色々な資源があっていいな、私も山で丸太を切って建築をつくりたいと、憧れを持ちましたが、いやいや、都会でもできることはあるよね。そんなことに気が付いたんです。そういう人のスキルを集められるプロジェクトをどんどんつくっていくことが、建築家の仕事として求められているんじゃないかとも思って、コツコツ始めているところです。
ーーカフェをやろうと思ったきっかけは何だったんですか。
アリソン:結婚した相手が、コーヒー・フェスティバルみたいなイベントを企画して開催する仕事をずっとやっていたんです。「千鳥文化」でもやらせてもらいました。
家成:ああ、そうでしたね。
アリソン:コーヒー屋をやりたいとずっと前から言われていたんですが、私がtecoにいた時は忙しくてなかなかやれなくて、辞めたタイミングで、物件探しからやり出しました。コーヒーをやるならそれなりに極めようと思って、私もきちんとトレーニングを受けましたよ。別に建築だけがやりたかったわけでもないし。でもコーヒー屋をつくるということは、地域を活性化させるという意味でも、すごく大きな意味がありました。高齢者や子ども達、近所の人たちとの日常的な挨拶や見守りができるので、福祉的な場所にもなっていると思うし。
家成:周りの人が話をしにやって来ますからね。
アリソン:建築なんて、人の生活を豊かにするひとつの手段でしかないです。この展覧会のオープニング・セレモニーで、家成さんは「ちょっと建築ができる普通のオッチャンになりたい」と言っていましたよね。
家成:はい。
アリソン:それは私も一緒です。建築もできるスナックのママでいたい。本当そうなんです。コーヒーも畑仕事も、必要だと思うのでやっているわけですが、それをやっていくと建築家と言えなくなっていくんです。「何なんやろ?」と思ったら、ただの人間なんですよね。
家成:福祉も今や業務としてのサービスになってしまっていますが、アリソンさんが町の中でみんなでやっていくことが、結果的に福祉のようにもなっている。そういう状況の方が、僕も絶対にいいと思います。
アリソン:制度や施設も当然、整えていかなければいけないけど、日常的なアプローチがゼロになってしまうのはまずいでしょう。大きな災害が起こったときにも困りますし。
家成:お金がないとサービスを受けられないというのでは、よくないですね。
アリソン:最近は「街の営繕」というのも始めました。建物を建て替えて、街を良くしていくみたいなことは、絵は描けるけど現実味はありません。何ができるかを考えると、建物の外は割と緩い決まりでできているので、所有の概念さえ少し手放してもらえれば、結構みんなで使える場所ができていく。外だけちょっと間借りして、「何かやらせてくれませんか」という活動です。みんなでコンクリートをはつって植物を植えたり、コンポストをつくってもらったりしています。
家成:めちゃくちゃ面白そうですね。
ーードットアーキテクツはパーティーを積極的に仕掛けていますよね。これはどういう意味ですか。
家成:僕らはパーティーを、プロジェクトのひとつとしてやっています。特にコロナ禍では、家から出られない時期があったし、オンラインばかりでつながっていたので、肉体的な接触がまったくできなくなったじゃないですか。それは非常にまずいなと思っていて、コロナが終息してまた普通に出会えるようになったときに開くパーティーの練習をとりあえずやっておこうと考えて、月に1回、contact Gonzoというアーティスト集団と一緒に、大阪のギャラリーの中でパーティーを続けていました。その中で、丸太からでかい地域通貨をつくったり、ドラァグクイーンからメイクを教えてもらったり、そういうことをやっていました。

GDP(Gonzo dot Party)大阪府 | 2020 アーティストとの協働による映画制作とパフォーマンス。
©アートエリアB1/photo by Ryo Yoshimi
©アートエリアB1/photo by Ryo Yoshimi
アリソン:真面目にパーティーに取り組んでいたんですね。
家成:真面目とは言えないかもしれないけど。
アリソン:みんなで何かをつくるとか、お祭りをやるとか、そういうことは人間の生にとって絶対に必要ですよね。パーティーもそのひとつということですね。
家成:そうだと思います。
アリソン:そういえば、この間、町屋について調べる機会があったんですけど、町屋というのは小屋と店と桟敷でできている、と書かれていたんです。
家成:桟敷というのは?
アリソン:桟敷席という言葉もありますが、桟敷というのはもともと仮設の床という意味だったらしくて、神社で舞を舞う時に設ける台のことを呼んでいました。町屋では、お祭りの時にステージであり客席である場所が必要になって、それが桟敷になっています。町屋では井戸やトイレといった水回りは共有して、自分の家に小屋と店と桟敷がある。今は水回りはすべて家の中に入っていますが、逆に桟敷や店を共有すべきなんじゃないか、とも考えました。パーティーの話から、そんなことも思い出しました。
家成:僕が今、仕事でちょくちょく行っている滋賀県の町では、通りに面した塀に窓があるんですよ。そこがお祭りの日だけ開いて、そこから行列を見物するんだそうです。その窓が、桟敷窓と呼ばれています。
アリソン:お祭りと対応した空間があるというのがいいですよね。戦後の復興期からずっと、日本では町屋で言うところの小屋ばかりをどんどんつくっていきました。当初は、住む場所がなかったから、それが正しかったのかもしれないけど、もはや住宅が余ってる時代になって久しいわけです。この時代に私たちがやるべきことは、桟敷のような場所をつくることなんじゃないか。
家成:家の外側に、少しみんなが楽しめる場所をつくっていこうということですよね。それで生きる楽しみが回復できる。同感です。
アリソン:昨夜は今回、出版されたドットアーキテクツの作品集を眺めながら、爆笑していました。こんなに笑える建築の本は初めて見ました。
家成:その感想は嬉しいな。
アリソン:でもそういうことが建築の割と根元的な価値だったのではないのかな。人の生活をより良くするとか、より楽しくするとか、そのためにいろいろと考えられてきたはずです。
家成:古典落語だと、長屋の両隣がめっちゃうるさいから引っ越してくれと交渉したら入れ替わっただけだったとか、浮気してる現場に家人が帰ってきて押し入れに隠れたとか、建物が面白く使われてる話が結構、あるんですよね。それが今のテレビドラマだと、殺人事件の現場にはなるけど、笑いの現場になっていることはあまりない。
アリソン:「馬木キャンプ」は使っている人がみんな楽しそうです。何でだろう。
家成:集落ごとにある自治会館みたいな施設なんですけど、閉鎖的になることを避けて、外から中で何をやってるか、見えるようにしました。形はただの四角です。まあ僕らは大体、四角のプランでやってしまう。それでできるだけ大きくします。用途ごとに分けずに、いろいろなことをその大きい四角形に収める。
アリソン:四角の方がつくりやすいですしね。
家成:「馬木キャンプ」は、敷地の形に対して少し斜めに配置しています。これは、瀬戸内国際芸術祭のときに建てられたので、押しかける大勢の観光客の相手をずっとしていたら少ししんどいだろうから、裏庭みたいな隠れてタバコを吸えるところをつくろうと思ったからでした。デザインとしては、斜めに振らない方がカッコよかったかもしれません。でもこの裏庭をつくっておいてよかったなと思います。最近はそこが畑になっていて、大きなズッキーニが転がってました。
アリソン:そういう生活者の視点は大事ですね。私は坂本一成という建築家のもとで建築を勉強し、その下で仕事をしていた時期もあったんですけど、彼がいつも言っていたのは、「形式と便宜のせめぎ合いの中に建築はできる」ということでした。形式というのは建築家としての意識、便宜というのは要件であったり、環境であったり、あるいは生活者としての視点のようなもののことです。形式だけでつくってしまうと独りよがりの表現に終わってしまうし、ただ便宜的につくると建築家なんていらないじゃないかとなってしまう。先ほどの、敷地に対してまっすぐ置いた方がきれいに見えるんだけど振ったという話も、そういうことだと思うんです。矛盾する形式と便宜の間で、ちょうどいい角度に調整するみたいな。
家成:そうですね。調整の連続。それがプロジェクトというものです。
ーードットアーキテクツは設計するだけでなくて、施工にも積極的に関わっていますね。
アリソン:誰がつくるかによって、できるものや設計が変わったりもしますか。
家成:そうですね。僕らのまわりには、工芸を本業にしているような金属加工の達人とか、自分で設計して自分で建てられるようなアーキテクトビルダーのような大工さんとか、とても優秀な人たちがいて、現場を手伝ってくれています。そういう人たちがいるので、設計も少し無茶するということもありますね。みんな面白がってやってくれるので、いいですよ。
アリソン:現場が楽しいのは大事ですね。
家成:現場がキャンプ場みたいになっているんですよ。庭にタープを張って、昼休みが長くて、本格的なコーヒーを淹れて飲んでたりする。仕事する前にフリスビーで準備体操をしたりね。遊びと仕事の切れ目がぼんやりしてるというか、両方楽しくてやってるみたいな感じです。
アリソン:楽しみながら働いていることを、業界的にもどんどん見せた方がいいですよね。職人になりたいという若い人が減って、困っているのだから。
家成:現場で畑をつくってしまうこともありますね。
アリソン:お施主さんもそこに参加して、つくるプロセスを一緒に楽しめたらいいですね。
ーー展覧会の会場には、ヨーロッパの社会センターをリサーチした成果も展示されています。ヨーロッパのそうした活動は、日本でも参考になりますか。
家成:非常に参考になると思います。イタリアの社会センターに行くと、大きい建物の中に共有のキッチンがあって、ダイニングがあって、卓球台やスケボーのランプがあったりします。週に1回の集まりでは、参加者がそれぞれ持ってきた食べ物を食べることができて、隣の部屋では映画の上映をやっている、という感じ。木工室、金工室、映像や音楽のスタジオもあって、そこに居住区がくっついています。生きていくためのあらゆる設備が、整っているんですよ。スクウォッティングなので、家賃は原則かからないのですが、運営に必要な金額を、シルクスクリーンでTシャツをつくって売ったりして稼いだりもしています。基本的にみんな楽しんでいるのですが、その場所をどう運営していくかについては、チーム内で活発な議論が行われます。きちんとした政治が、そこにあるんですよね。誰かに委任する政治ではなくて、自分たちで自分たちのことを決めていくという政治。
家成:真面目とは言えないかもしれないけど。
アリソン:みんなで何かをつくるとか、お祭りをやるとか、そういうことは人間の生にとって絶対に必要ですよね。パーティーもそのひとつということですね。
家成:そうだと思います。
アリソン:そういえば、この間、町屋について調べる機会があったんですけど、町屋というのは小屋と店と桟敷でできている、と書かれていたんです。
家成:桟敷というのは?
アリソン:桟敷席という言葉もありますが、桟敷というのはもともと仮設の床という意味だったらしくて、神社で舞を舞う時に設ける台のことを呼んでいました。町屋では、お祭りの時にステージであり客席である場所が必要になって、それが桟敷になっています。町屋では井戸やトイレといった水回りは共有して、自分の家に小屋と店と桟敷がある。今は水回りはすべて家の中に入っていますが、逆に桟敷や店を共有すべきなんじゃないか、とも考えました。パーティーの話から、そんなことも思い出しました。
家成:僕が今、仕事でちょくちょく行っている滋賀県の町では、通りに面した塀に窓があるんですよ。そこがお祭りの日だけ開いて、そこから行列を見物するんだそうです。その窓が、桟敷窓と呼ばれています。
アリソン:お祭りと対応した空間があるというのがいいですよね。戦後の復興期からずっと、日本では町屋で言うところの小屋ばかりをどんどんつくっていきました。当初は、住む場所がなかったから、それが正しかったのかもしれないけど、もはや住宅が余ってる時代になって久しいわけです。この時代に私たちがやるべきことは、桟敷のような場所をつくることなんじゃないか。
家成:家の外側に、少しみんなが楽しめる場所をつくっていこうということですよね。それで生きる楽しみが回復できる。同感です。
アリソン:昨夜は今回、出版されたドットアーキテクツの作品集を眺めながら、爆笑していました。こんなに笑える建築の本は初めて見ました。
家成:その感想は嬉しいな。
アリソン:でもそういうことが建築の割と根元的な価値だったのではないのかな。人の生活をより良くするとか、より楽しくするとか、そのためにいろいろと考えられてきたはずです。
家成:古典落語だと、長屋の両隣がめっちゃうるさいから引っ越してくれと交渉したら入れ替わっただけだったとか、浮気してる現場に家人が帰ってきて押し入れに隠れたとか、建物が面白く使われてる話が結構、あるんですよね。それが今のテレビドラマだと、殺人事件の現場にはなるけど、笑いの現場になっていることはあまりない。
アリソン:「馬木キャンプ」は使っている人がみんな楽しそうです。何でだろう。
家成:集落ごとにある自治会館みたいな施設なんですけど、閉鎖的になることを避けて、外から中で何をやってるか、見えるようにしました。形はただの四角です。まあ僕らは大体、四角のプランでやってしまう。それでできるだけ大きくします。用途ごとに分けずに、いろいろなことをその大きい四角形に収める。
アリソン:四角の方がつくりやすいですしね。
家成:「馬木キャンプ」は、敷地の形に対して少し斜めに配置しています。これは、瀬戸内国際芸術祭のときに建てられたので、押しかける大勢の観光客の相手をずっとしていたら少ししんどいだろうから、裏庭みたいな隠れてタバコを吸えるところをつくろうと思ったからでした。デザインとしては、斜めに振らない方がカッコよかったかもしれません。でもこの裏庭をつくっておいてよかったなと思います。最近はそこが畑になっていて、大きなズッキーニが転がってました。
アリソン:そういう生活者の視点は大事ですね。私は坂本一成という建築家のもとで建築を勉強し、その下で仕事をしていた時期もあったんですけど、彼がいつも言っていたのは、「形式と便宜のせめぎ合いの中に建築はできる」ということでした。形式というのは建築家としての意識、便宜というのは要件であったり、環境であったり、あるいは生活者としての視点のようなもののことです。形式だけでつくってしまうと独りよがりの表現に終わってしまうし、ただ便宜的につくると建築家なんていらないじゃないかとなってしまう。先ほどの、敷地に対してまっすぐ置いた方がきれいに見えるんだけど振ったという話も、そういうことだと思うんです。矛盾する形式と便宜の間で、ちょうどいい角度に調整するみたいな。
家成:そうですね。調整の連続。それがプロジェクトというものです。
ーードットアーキテクツは設計するだけでなくて、施工にも積極的に関わっていますね。
アリソン:誰がつくるかによって、できるものや設計が変わったりもしますか。
家成:そうですね。僕らのまわりには、工芸を本業にしているような金属加工の達人とか、自分で設計して自分で建てられるようなアーキテクトビルダーのような大工さんとか、とても優秀な人たちがいて、現場を手伝ってくれています。そういう人たちがいるので、設計も少し無茶するということもありますね。みんな面白がってやってくれるので、いいですよ。
アリソン:現場が楽しいのは大事ですね。
家成:現場がキャンプ場みたいになっているんですよ。庭にタープを張って、昼休みが長くて、本格的なコーヒーを淹れて飲んでたりする。仕事する前にフリスビーで準備体操をしたりね。遊びと仕事の切れ目がぼんやりしてるというか、両方楽しくてやってるみたいな感じです。
アリソン:楽しみながら働いていることを、業界的にもどんどん見せた方がいいですよね。職人になりたいという若い人が減って、困っているのだから。
家成:現場で畑をつくってしまうこともありますね。
アリソン:お施主さんもそこに参加して、つくるプロセスを一緒に楽しめたらいいですね。
ーー展覧会の会場には、ヨーロッパの社会センターをリサーチした成果も展示されています。ヨーロッパのそうした活動は、日本でも参考になりますか。
家成:非常に参考になると思います。イタリアの社会センターに行くと、大きい建物の中に共有のキッチンがあって、ダイニングがあって、卓球台やスケボーのランプがあったりします。週に1回の集まりでは、参加者がそれぞれ持ってきた食べ物を食べることができて、隣の部屋では映画の上映をやっている、という感じ。木工室、金工室、映像や音楽のスタジオもあって、そこに居住区がくっついています。生きていくためのあらゆる設備が、整っているんですよ。スクウォッティングなので、家賃は原則かからないのですが、運営に必要な金額を、シルクスクリーンでTシャツをつくって売ったりして稼いだりもしています。基本的にみんな楽しんでいるのですが、その場所をどう運営していくかについては、チーム内で活発な議論が行われます。きちんとした政治が、そこにあるんですよね。誰かに委任する政治ではなくて、自分たちで自分たちのことを決めていくという政治。

ドットアーキテクツ展 GALLERY 1展示風景 (写真左手前)イタリアの社会センターのリサーチ
©Nacása & Partners Inc.
©Nacása & Partners Inc.
アリソン:スクウォッティングを前提にすると日本では無理のように思えてしまうけど、場所のアイディア自体は、実現できることかもしれませんね。
家成:そうなんです。イタリアにもスクウォッティングではなく、家賃を払って活動している社会センターもあります。それだったら日本でも可能ですし、僕らがやっている「コーポ北加賀屋」も、社会センターと言ってしまっていいかなと思っています。
ーー近年はドットアーキテクツのほかにも「建築コレクティブ」とでも呼ぶべきグループの活動が、いろいろ目につくようになっています。建築家が集団で活動することの意味は、どのようにとらえればいいでしょうか。
家成:僕らの場合は、流動的に多くの人の話し合いから、いろいろなアイディアを持ち寄ってつくっていくので、ひとりの個人名を掲げるというよりは、集団名を名乗るということになったんですけどね。例えば「家成&アソシエイツ」みたいな名前だと、僕がいなくなったら成り立たないじゃないですか。誰かがいなくなってもしいし、別の誰かが入ってきてもいい。同じ志向を持った人が集まってやっている、そういう組織であることを表明しています。
アリソン:先に触れたマンズィーニが、やはりそういう組織のあり方を説いていましたね。プロジェクトを続けるためには、出入り自由なエコシステムをつくることが重要で、同じメンバーでやっていると、原理的になってしまったりとか、きついという人が出てきたりとか、ブレークスルーが生まれなくなってしまう。出入り自由にすることで、常に面白い状態で続けられるとのことでした。
家成:文化人類学者の小川さやかさんが、アフリカの路上商人について説明してくれたのですが、商人たちは1台のシティバスに乗っていて、いつ乗り込んできてもいいし、いつ降りてもいいみたいな状態らしいです。それでもバスはずっと走っている。バスの話でもうひとつ、劇作家の神里雄大さんから聞いた話で、ボリビアのチキンバスというのが、デコラティブに改造されたバスらしいですけど、それに乗っていたら、運転手は隣に愛人を座らせているし、こっちでは牧師が祈ってるし、あっちでは年寄りが泣いてる。その間を縫って、物売りがウロウロしている。ごちゃごちゃの人間が同じ空間にいて、好き放題振る舞っている。そういう状態を体験したんだそうです。バスの例え2連発ですけど、そういう状況をつくりたいですね。
アリソン:いいですね。そういうバスの風景を、私は街の中につくりたい。今は同じ種類の人が同じ場所に集まってしまっていて、それではつまらない。
家成:どんどん平準化していっている。
アリソン:うちのコーヒー屋は、そのバスみたいな感じが少しあるかもしれません。おじいちゃんとおばあちゃんが若い子に「結婚とは」という話してる横で、コーヒー通の人がめちゃくちゃマニアックな話をしていて、ベリーダンスを踊っているおじいちゃんもいる。
家成:すごいですね。
アリソン:建築を学んで、建築の仕事をずっとしてきましたけど、最近は建築じゃなくてもいいかもしれないと思います。無理に建築で解決しようとしなくても、この問題に対してはアートが、この問題には映画が、といったかたちで、いろいろなスキルを場合に応じて出すみたいなことの方が、社会的には求められているんです。
家成:映画をつくる時にも、建築のスキルは活きてきますしね。セットをつくるときには、両方が統合されています。
アリソン:今は「私、何もできません」と言わされているような状況なので、「自分はこれができます、あれもできます」と言いやすい環境にしたい。そういう社会の方が健全ですよ。
家成:「仮の家」の基礎をつくってくれた石屋さんは、週の半分は大判焼きの店を開いてる人です。そんな人ばかりが周りにいるので、「建築しかできません」と言うのは、だんだん恥ずかしくなってくる(笑)。
家成:そうなんです。イタリアにもスクウォッティングではなく、家賃を払って活動している社会センターもあります。それだったら日本でも可能ですし、僕らがやっている「コーポ北加賀屋」も、社会センターと言ってしまっていいかなと思っています。
ーー近年はドットアーキテクツのほかにも「建築コレクティブ」とでも呼ぶべきグループの活動が、いろいろ目につくようになっています。建築家が集団で活動することの意味は、どのようにとらえればいいでしょうか。
家成:僕らの場合は、流動的に多くの人の話し合いから、いろいろなアイディアを持ち寄ってつくっていくので、ひとりの個人名を掲げるというよりは、集団名を名乗るということになったんですけどね。例えば「家成&アソシエイツ」みたいな名前だと、僕がいなくなったら成り立たないじゃないですか。誰かがいなくなってもしいし、別の誰かが入ってきてもいい。同じ志向を持った人が集まってやっている、そういう組織であることを表明しています。
アリソン:先に触れたマンズィーニが、やはりそういう組織のあり方を説いていましたね。プロジェクトを続けるためには、出入り自由なエコシステムをつくることが重要で、同じメンバーでやっていると、原理的になってしまったりとか、きついという人が出てきたりとか、ブレークスルーが生まれなくなってしまう。出入り自由にすることで、常に面白い状態で続けられるとのことでした。
家成:文化人類学者の小川さやかさんが、アフリカの路上商人について説明してくれたのですが、商人たちは1台のシティバスに乗っていて、いつ乗り込んできてもいいし、いつ降りてもいいみたいな状態らしいです。それでもバスはずっと走っている。バスの話でもうひとつ、劇作家の神里雄大さんから聞いた話で、ボリビアのチキンバスというのが、デコラティブに改造されたバスらしいですけど、それに乗っていたら、運転手は隣に愛人を座らせているし、こっちでは牧師が祈ってるし、あっちでは年寄りが泣いてる。その間を縫って、物売りがウロウロしている。ごちゃごちゃの人間が同じ空間にいて、好き放題振る舞っている。そういう状態を体験したんだそうです。バスの例え2連発ですけど、そういう状況をつくりたいですね。
アリソン:いいですね。そういうバスの風景を、私は街の中につくりたい。今は同じ種類の人が同じ場所に集まってしまっていて、それではつまらない。
家成:どんどん平準化していっている。
アリソン:うちのコーヒー屋は、そのバスみたいな感じが少しあるかもしれません。おじいちゃんとおばあちゃんが若い子に「結婚とは」という話してる横で、コーヒー通の人がめちゃくちゃマニアックな話をしていて、ベリーダンスを踊っているおじいちゃんもいる。
家成:すごいですね。
アリソン:建築を学んで、建築の仕事をずっとしてきましたけど、最近は建築じゃなくてもいいかもしれないと思います。無理に建築で解決しようとしなくても、この問題に対してはアートが、この問題には映画が、といったかたちで、いろいろなスキルを場合に応じて出すみたいなことの方が、社会的には求められているんです。
家成:映画をつくる時にも、建築のスキルは活きてきますしね。セットをつくるときには、両方が統合されています。
アリソン:今は「私、何もできません」と言わされているような状況なので、「自分はこれができます、あれもできます」と言いやすい環境にしたい。そういう社会の方が健全ですよ。
家成:「仮の家」の基礎をつくってくれた石屋さんは、週の半分は大判焼きの店を開いてる人です。そんな人ばかりが周りにいるので、「建築しかできません」と言うのは、だんだん恥ずかしくなってくる(笑)。

アリソン:家成さんに、それぞれの人のできることを引き出すという能力があるんでしょうね。今日のお話でも、ジャンルの違う人がたくさん出てきました。建築の職人もいるし、演劇の人もいるし、アーティストもいる。いろいろな人とフラットに接して、その中から強いアイディアを引き出して、みんなを束ねて進めていく。この役割を建築家と呼ぶのがいいのかよくわかりませんが、素晴らしいスキルだと思います。
家成:みんなが楽しそうにしてくれていたら、僕はそれでいいんです。
家成:みんなが楽しそうにしてくれていたら、僕はそれでいいんです。
アリソン理恵|How is Life? 展示デザイン (写真中央)
©Eichi Tano1982年宮崎県出身。2005 年東京工業大学工学部建築学科卒業。2010年東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。2010-2014年ルートエー勤務。2014-2015年アトリエ・アンド・アイ坂本一成研究室勤務。2015-2019年一級建築士事務所teco共同主宰。2020年一級建築士事 務所ara設立。豊島区東長崎にてコーヒショップ MIAMIA、カルチュラルキオスクIAMを運営。

©Eichi Tano
最強のアマチュアリズム
呆気にとられるとはこのことか。展示室に足を踏み入れると、そこにあるのはバーのカウンターらしきもので、その周りの台には、模型やら、工具やら、材料やら、なんだかよくわからないものも含めて、雑多なものが置かれている。その向こうにはシルクスクリーンの印刷機やラジオの放送機もある。いわゆる作品らしきものは、この空間で見つけることができない。
この展示を行ったドットアーキテクツは、7人のメンバーから成る、今ふうに言えば建築コレクティブだ。展示パネルの説明では、もともと6人でつくってあったものに、急遽、一人を書き足した格好になっている。融通無碍な感じも、この組織のあり方を象徴している。建築にとどまらない様々な活動を続けており、瀬戸内国際芸術祭や水と土の芸術祭といったアート・イベントにも多く参加しているので、そこで彼らの作品に触れている人も多いかもしれない。
この展示を行ったドットアーキテクツは、7人のメンバーから成る、今ふうに言えば建築コレクティブだ。展示パネルの説明では、もともと6人でつくってあったものに、急遽、一人を書き足した格好になっている。融通無碍な感じも、この組織のあり方を象徴している。建築にとどまらない様々な活動を続けており、瀬戸内国際芸術祭や水と土の芸術祭といったアート・イベントにも多く参加しているので、そこで彼らの作品に触れている人も多いかもしれない。

⾺⽊キャンプ(⾹川県、2013年)©HIDEAKI HAMADA
瀬戸内国際芸術祭を機に建てられた自主施工による地域の交流施設。ドットアーキテクツ と住⺠総出で一日で制作した映画の、一夜限りの上映会。
瀬戸内国際芸術祭を機に建てられた自主施工による地域の交流施設。ドットアーキテクツ と住⺠総出で一日で制作した映画の、一夜限りの上映会。
彼らが拠点としているのは、大阪市の廃屋だった家具工場を改修した「コーポ北加賀屋」という協働スタジオだ。その雰囲気が、今回、TOTOギャラリー・間には転送されている。自分たちの活動の場をどのようにつくるのか。それこそがまず、彼らにとっての作品であるということなのだろう。ここではシルクスクリーンでTシャツにプリントしたり、簡易なラジオ放送も実際に行ったりもした。展示というより実践の場となっている。
中庭にはパターゴルフのコースが設置されている。参加者は手作りのパターで、ゴルフを楽しむことができる。驚くのは、前回の企画展で制作した茅葺きの壁が残っていること。個展という意識がないのであろうか。
上のフロアには、「No.00」、「馬木キャンプ」、「仮の家」といった代表作や、進行中のプロジェクトが模型や写真を使って展示されている。そのいくつかでは、セルフビルドを前提とした新しい掘立柱が採用されていて、建築の構造としてもたいへん興味深い。ようやくTOTOギャラリー・間らしくなったな、と安心しながら奥まで進んでいくと、そこではSF映画「ギャラクティック運輸の初仕事」を上映している。ドットアーキテクツが美術を担当するだけでなく、出演まで果たしてしまったという映像作品で、ここで再び、建築展らしさが吹っ飛ばされる。
中庭にはパターゴルフのコースが設置されている。参加者は手作りのパターで、ゴルフを楽しむことができる。驚くのは、前回の企画展で制作した茅葺きの壁が残っていること。個展という意識がないのであろうか。
上のフロアには、「No.00」、「馬木キャンプ」、「仮の家」といった代表作や、進行中のプロジェクトが模型や写真を使って展示されている。そのいくつかでは、セルフビルドを前提とした新しい掘立柱が採用されていて、建築の構造としてもたいへん興味深い。ようやくTOTOギャラリー・間らしくなったな、と安心しながら奥まで進んでいくと、そこではSF映画「ギャラクティック運輸の初仕事」を上映している。ドットアーキテクツが美術を担当するだけでなく、出演まで果たしてしまったという映像作品で、ここで再び、建築展らしさが吹っ飛ばされる。




展示風景 ©Nacása & Partners Inc.
ドットアーキテクツがきちんとした資格と知識を持った建築設計集団であることはもちろんだが、それだけでなく施工に参画したり、出来上がった建物の運営を行ったりもする。そればかりか、バーテンダーもやるし、Tシャツもつくるし、ラジオ放送もやるし、映画までつくってしまう。専門性の垣根を超えて、やってしまうこと。そうしたアマチュアリズムが、彼らの活動を貫いている。
プロのスポーツは、競技者と観客ははっきりと分かれている。それに対してアマチュアのスポーツでは、見る側と見られる側が分かれていない。現代の都市や建築をめぐるあれやこれやでも、つくる側とつくられる側、決める側と決められる側、サービスする側とされる側、両者がはっきりと分かれてしまったことが問題なのであって、これらを未分化の状態に引き戻すことが解決の道なのだ。
そんな考えが、この展覧会を強く反映している。来場者も単に展示を見せられる人であることは求められていない。ゴルフをプレーし、パターをつくることが要請されている。ヘタでもいいではないか。みんなで参加しよう。そうした状態を達成することが、展覧会のタイトルにもなっている「POLITICS OF LIVING」なのである。
展覧会のオープニングの内覧会で、ドットアーキテクツの家成俊勝さんは「ドットは色々なことをやっていますが、その中でも比較的建築の得意なおっちゃんとおばちゃんを目指します」と宣言されたという。
彼らが目指すのは、建築界最強のアマチュアである。
プロのスポーツは、競技者と観客ははっきりと分かれている。それに対してアマチュアのスポーツでは、見る側と見られる側が分かれていない。現代の都市や建築をめぐるあれやこれやでも、つくる側とつくられる側、決める側と決められる側、サービスする側とされる側、両者がはっきりと分かれてしまったことが問題なのであって、これらを未分化の状態に引き戻すことが解決の道なのだ。
そんな考えが、この展覧会を強く反映している。来場者も単に展示を見せられる人であることは求められていない。ゴルフをプレーし、パターをつくることが要請されている。ヘタでもいいではないか。みんなで参加しよう。そうした状態を達成することが、展覧会のタイトルにもなっている「POLITICS OF LIVING」なのである。
展覧会のオープニングの内覧会で、ドットアーキテクツの家成俊勝さんは「ドットは色々なことをやっていますが、その中でも比較的建築の得意なおっちゃんとおばちゃんを目指します」と宣言されたという。
彼らが目指すのは、建築界最強のアマチュアである。
磯達雄 Tatsuo Iso
編集者・1988年名古屋大学卒業。1988~1999年日経アーキテクチュア編集部勤務後2000年独立。2002年~20年3月フリックスタジオ共同主宰。20年4月から宮沢洋とOffice Bungaを共同主宰。
https://bunganet.tokyo/
https://bunganet.tokyo/

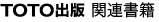
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。