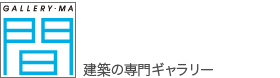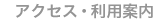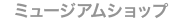- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

展覧会レポート
建築家とキュレーターの新しい関係
レポーター=保坂健二朗
パネルがあって模型がある。一見する限り、きわめてオーソドックスな建築展である。しかしよくよく見ていくと、実に大胆であることに驚かされる。展覧会も、そしてそれが紹介しているところの山下保博という人物も、実に大胆だ。どういうことか。
たとえば入り口に掲げられた「アトリエ・天工人を知るための『モノ・コトめがね』」。縦列を「コト」として七つに、横列を「モノ」として同じく七つに区分したマトリックスをつくり、そこに山下が手がけたプロジェクトをマッピングするというものである。これを見れば、たとえば代表作のひとつである《Lucky Drops》は、モノでは「五感からの冒険」に、コトでは「共に創る」と「開発する」にあてはまると一目でわかる。(写真A)(写真B)
パネルがあって模型がある。一見する限り、きわめてオーソドックスな建築展である。しかしよくよく見ていくと、実に大胆であることに驚かされる。展覧会も、そしてそれが紹介しているところの山下保博という人物も、実に大胆だ。どういうことか。
たとえば入り口に掲げられた「アトリエ・天工人を知るための『モノ・コトめがね』」。縦列を「コト」として七つに、横列を「モノ」として同じく七つに区分したマトリックスをつくり、そこに山下が手がけたプロジェクトをマッピングするというものである。これを見れば、たとえば代表作のひとつである《Lucky Drops》は、モノでは「五感からの冒険」に、コトでは「共に創る」と「開発する」にあてはまると一目でわかる。(写真A)(写真B)

写真A

写真B
しかし、モノのひとつに書いてある「構造からの冒険」には全く当てはまらないと見えてもしまう。そこには「冒険」とは呼べないまでも構造的な特徴はあるはずなのだが……。ただ、わかりやすさ、理解しやすさを獲得するためには、細部を大胆に捨て去る必要もあるのだろう。そしてそのような大胆さを微塵にも感じさせぬほど、「モノ・コトめがね」はポップにデザインされていた。大胆である。
誤解されるかもしれないリスクを引き受けてまで、「モノ・コトめがね」をつくったのはなぜか。山下本人曰く、藤森照信をはじめ多くの人が「山下保博とはどういう建築家かがわかりにくい」と感じていることへの回答なのだそうだ。ここで面白いのは、そのような疑問に対して、丁寧に、しかし実際には大胆な形で返答しているところである。これも、実に山下らしい。
確かに山下は「わかりにくい」。会場を歩くと、多種多様なプロジェクトが並んでいて、気を抜くとグループ展と感じられてきて戸惑ってしまう。「違う違う、これは個展なのだ」と自分に言い聞かせつつ見ていっても、それはそれで山下の「趣味」がどこにあるのかわからなくなってきて、ちょっと混乱してくる。
ここで用いている「趣味」とは、もちろんhobbyではなくてtasteの意味でのそれである。すなわち様式的特徴を吟味する能力であり、とりわけ建築家の場合には、無数に続く判断の局面において、道筋を決めるためにそれは必要となってくる。趣味とは恣意性であると捉えて、他者のためのデザインである建築ではそれを乗り越えるべきだと考える傾向もあるにはあるが、チャンスオペレーションでも取り入れない限り、完全に趣味から自由になることなどできはしない。しかもややこしいことに、設計する建物の数が増えれば、自ずと自分の「趣味」が収斂されていき、いわゆる個人様式ができあがる。それが、普通である。望むと望まざるにかかわらず、クリエイティヴとはそういうものなのだ。ほとんどの人がそうだと思っていた。
だが山下は違った。彼の場合、つくればつくるほど、「趣味」が拡散していくのだ。いや、もちろん、判断の能力がないと言っているわけではない。ここで言いたいのはつまりこういうことである。山下は、つくり続ける中で、判断をする能力としての趣味は洗練させていくが、個人様式を生み出していくところの趣味は否定していくのだ、と。
わかりにくいかもしれないのでtaste=趣味=味覚という言葉を用いて喩えてみると、山下は、味覚を洗練させていくことで逆にどんな料理でもつくれるようになっている、といった風になろう。「味覚」ついでに更なる比喩を用いれば、山下はどこか、たとえば故村上信夫氏に代表される、ホテルの総料理長のような存在でもあるように私には思える。
いや、あくまでも「建築」の中で語るべきだろうか。それについては、藤森照信が、今回の展覧会にあわせて刊行された書籍(『Tomorrow――建築の冒険』)に収められた山下との対談の中で見事にまとめているので、参照させていただくことにしよう。藤森曰く、「山下さんは、20世紀全体をちゃんとやっている人ですよ。ひとつ言えるのは、建築というものの全体をやっている人です。そうすると、仮に建築がこんなかたちをしたものだとすると、全体をやった結果、山下さんはその建築のかたちに重なっているんですよ」。
山下=建築。なるほど確かにそんな気がする。ここでさらに考えを進めれば、山下が「建築というものの全体」をやることができるのは、きっと彼が、「部分」同士の間にヒエラルキーを認めていないからだろう。この姿勢は、かつてポストモダンと呼ばれる時代にもあったけれど、あれが結局のところ、ひとつの建物の間での複数性だったのに対して(そしてその結果、ひとつの様式を生み出してしまっていたのに対して)、山下は、自らの持続的な制作のうちに複数性を取り入れている点で、大きく異なる。時代様式や地域様式は認めながらも、個人様式の意義は認めないその徹底した姿勢こそ、本当のポストモダン(あるいは近代に対する生産的な批判)ではないかと言いたくなる。
だがもちろん、山下の営みは、個人様式の否定のみに向けられているわけではない。そんなつまらないところを彼は目指してはいないことは、今回展示されている《熱の美術館》というアンビルトのプロジェクトを見ればわかる(この建物、英語ではMuseum of Heatとあるように、本来は「熱の美術館」ではなくて、「熱ミュージアム」、あるいは「熱(の)館」とでも訳すべきだろう。ひょっとしたら、感性的な体験が成立する特殊なトポスとして「美術館」を特別視してくれているのかもしれないけれど)。(写真C)
誤解されるかもしれないリスクを引き受けてまで、「モノ・コトめがね」をつくったのはなぜか。山下本人曰く、藤森照信をはじめ多くの人が「山下保博とはどういう建築家かがわかりにくい」と感じていることへの回答なのだそうだ。ここで面白いのは、そのような疑問に対して、丁寧に、しかし実際には大胆な形で返答しているところである。これも、実に山下らしい。
確かに山下は「わかりにくい」。会場を歩くと、多種多様なプロジェクトが並んでいて、気を抜くとグループ展と感じられてきて戸惑ってしまう。「違う違う、これは個展なのだ」と自分に言い聞かせつつ見ていっても、それはそれで山下の「趣味」がどこにあるのかわからなくなってきて、ちょっと混乱してくる。
ここで用いている「趣味」とは、もちろんhobbyではなくてtasteの意味でのそれである。すなわち様式的特徴を吟味する能力であり、とりわけ建築家の場合には、無数に続く判断の局面において、道筋を決めるためにそれは必要となってくる。趣味とは恣意性であると捉えて、他者のためのデザインである建築ではそれを乗り越えるべきだと考える傾向もあるにはあるが、チャンスオペレーションでも取り入れない限り、完全に趣味から自由になることなどできはしない。しかもややこしいことに、設計する建物の数が増えれば、自ずと自分の「趣味」が収斂されていき、いわゆる個人様式ができあがる。それが、普通である。望むと望まざるにかかわらず、クリエイティヴとはそういうものなのだ。ほとんどの人がそうだと思っていた。
だが山下は違った。彼の場合、つくればつくるほど、「趣味」が拡散していくのだ。いや、もちろん、判断の能力がないと言っているわけではない。ここで言いたいのはつまりこういうことである。山下は、つくり続ける中で、判断をする能力としての趣味は洗練させていくが、個人様式を生み出していくところの趣味は否定していくのだ、と。
わかりにくいかもしれないのでtaste=趣味=味覚という言葉を用いて喩えてみると、山下は、味覚を洗練させていくことで逆にどんな料理でもつくれるようになっている、といった風になろう。「味覚」ついでに更なる比喩を用いれば、山下はどこか、たとえば故村上信夫氏に代表される、ホテルの総料理長のような存在でもあるように私には思える。
いや、あくまでも「建築」の中で語るべきだろうか。それについては、藤森照信が、今回の展覧会にあわせて刊行された書籍(『Tomorrow――建築の冒険』)に収められた山下との対談の中で見事にまとめているので、参照させていただくことにしよう。藤森曰く、「山下さんは、20世紀全体をちゃんとやっている人ですよ。ひとつ言えるのは、建築というものの全体をやっている人です。そうすると、仮に建築がこんなかたちをしたものだとすると、全体をやった結果、山下さんはその建築のかたちに重なっているんですよ」。
山下=建築。なるほど確かにそんな気がする。ここでさらに考えを進めれば、山下が「建築というものの全体」をやることができるのは、きっと彼が、「部分」同士の間にヒエラルキーを認めていないからだろう。この姿勢は、かつてポストモダンと呼ばれる時代にもあったけれど、あれが結局のところ、ひとつの建物の間での複数性だったのに対して(そしてその結果、ひとつの様式を生み出してしまっていたのに対して)、山下は、自らの持続的な制作のうちに複数性を取り入れている点で、大きく異なる。時代様式や地域様式は認めながらも、個人様式の意義は認めないその徹底した姿勢こそ、本当のポストモダン(あるいは近代に対する生産的な批判)ではないかと言いたくなる。
だがもちろん、山下の営みは、個人様式の否定のみに向けられているわけではない。そんなつまらないところを彼は目指してはいないことは、今回展示されている《熱の美術館》というアンビルトのプロジェクトを見ればわかる(この建物、英語ではMuseum of Heatとあるように、本来は「熱の美術館」ではなくて、「熱ミュージアム」、あるいは「熱(の)館」とでも訳すべきだろう。ひょっとしたら、感性的な体験が成立する特殊なトポスとして「美術館」を特別視してくれているのかもしれないけれど)。(写真C)

写真C
《熱の美術館》とは「熱を感じ、熱による現象を体験するための美術館」である。具体的にどうするかといえば、庇の下では霜を、上では虹を発生させる。建物の際では、結露した水により植物を育てる。室内では、雲や蜃気楼を発生させる。またガラスの熱割れも観察する対象とする。しかもそれは、100年というスパンで増殖していくことを前提としているのだそうだ。《熱の美術館》は、いわば巨大な実験装置とでもいうべきものである。
と、あっさりまとめるべきではない。ここで山下が主役に据えようとしているのは、建築家たちがなんとかして建物から排除しようとしてきた熱現象なのだから。
結露や熱割れの消去に務めるのではなくて、それらとの共生に向かって姿勢を取りなおそうとしているところに、彼自身がしばしば言及するところの「奄美大島」なるものの存在を感じ取ることは容易だろう。だが、そうやって安直に納得するのではなく、この美術館が、来館者にも、来館者がそうであるところの人間がつくりあげた創作物にも捧げられてはいないことを見逃さないようにしよう。そのようにデザインされたものを、果たして「建築」と呼ぶべきかどうか、私にはもはやわからない。
だが、山下はおそらく「建築」だと認めるだろう。彼が人間を特別視していないことは、ある展覧会に出品されたというオブジェ作品《万華鏡と走馬灯》に寄せられた言葉にも明らかである。そこで山下は次のように言っている。「木や石や鉄という物質の全てが等価値であるばかりでなく、人の思いさえも等価値に扱いたいと思っている」と。(写真D)
と、あっさりまとめるべきではない。ここで山下が主役に据えようとしているのは、建築家たちがなんとかして建物から排除しようとしてきた熱現象なのだから。
結露や熱割れの消去に務めるのではなくて、それらとの共生に向かって姿勢を取りなおそうとしているところに、彼自身がしばしば言及するところの「奄美大島」なるものの存在を感じ取ることは容易だろう。だが、そうやって安直に納得するのではなく、この美術館が、来館者にも、来館者がそうであるところの人間がつくりあげた創作物にも捧げられてはいないことを見逃さないようにしよう。そのようにデザインされたものを、果たして「建築」と呼ぶべきかどうか、私にはもはやわからない。
だが、山下はおそらく「建築」だと認めるだろう。彼が人間を特別視していないことは、ある展覧会に出品されたというオブジェ作品《万華鏡と走馬灯》に寄せられた言葉にも明らかである。そこで山下は次のように言っている。「木や石や鉄という物質の全てが等価値であるばかりでなく、人の思いさえも等価値に扱いたいと思っている」と。(写真D)

写真D
これは、ともすれば、「人の思い」の軽視とすら捉えられかねない発言であるが、逆にここから、山下が、徹底的に俯瞰しようとする視点を持とうとしていることがわかる。そして私は、そんな山下の姿勢を確認するや否や、それがある職業に共通していると気づいた。ほかならぬ私がそうであるところのキュレーターである。
そもそも、「モノ・コトめがね」に掲げられている「モノ」と「コト」というキーワード自体、キュレーターという職能と関係が深い。佐々木俊尚の『キュレーションの時代――「つながり」の情報革命がはじまる』も指摘しているように、キュレーションとは、単に、美しいモノや面白いコンテンツを提供することではない。そうではなく、数多あるモノの中からこれはと思うものを選び出し、組み合わせ、かつまたコンテキストをつくって、場・コトとして提供する行為を指す。このような行為が、美術展に限らず、「情報」への対応についても必要になっているからこそ「キュレーションの時代」と呼ばれるわけだが、山下の営みもまた、彼の言葉を借りれば「この指とまれ」式に人と人とをつなげているという点で、現代的なキュレーションだと言えるだろう。
だが、それだけが、私が山下に「キュレーター」性を見出した理由ではない。そもそも(ここは佐々木が指摘していないところになるけれども)キュレーターとは、展覧会を企画する人を意味するのではなかった。curatorとは、語源的にはラテン語でcurareする人、英語に訳せば、take care ofする人のことなのである。このとき、ケアする対象はなんでもかまわないのであるが、語用としては当然のことながら、人をケアする人としてキュレーターの語はまずは使われた。たとえば病院などで、lunatics、主に今でいうところの統合失調症の人たちをケアする人として、あるいは聖職者の一種に対して使われたこともあった。それがやがて、モノを管理する人に使われるようになり、さらに時が経ち、モノを見せるために並べる人、そして企画する人に使われるようになった。
このように、語源に即して考えれば、キュレーターとは、対象にヒエラルキーをつくらず、公平に、世話をし、引き受け、処理をしながら、大事にする人なのである(全部take care ofの意味だ)。これほど山下にふさわしい言葉もないだろう。またcuratorの語源であるcurareからは、accuracy(的確さ、正確さ)やcurious(好奇心の強い)といった言葉も派生しているように、キュレーターには、的確な好奇心が必要となる。このときの「的確さ」が、対象をひとつに絞るという意味ではないことは、そしてそのような好奇心もまた山下が持っているものであることは、言うまでもない。
以上が、山下をキュレーター的な建築家だといった理由だ。そしてそのようなスタイルが、今後もっと増えるべきだと思うのは、もちろん私がキュレーターであるからではなく、キュレーターに本来求められている「判断をする能力としての趣味は洗練させていくが、個人様式を生み出していくところの趣味は否定していく」姿勢が、今の社会には必要だと考えるからである。
最後に、山下の大胆さを示す余談めいた話をひとつ。《クリスタル・ブリック》の構法で特許をとったと言うので、なぜそうしたのか本人に訊ねてみた。普通、特許と言えば、他人が自由に使用する権利を制限するものであり、山下のスタンスとは相反するように思えたからだ。答えは「逆」だった。彼は、誰でも使えるようにするために特許を取ったというのだ。つまり、自分がとらなければ他の人が特許を取ってしまうかもしれない(そして制限をつけてしまうかもしれない)、そのリスクを回避するために特許を取ったというのである。特許にはそのような「使い方」もあることを恥ずかしながら知らなかったが、これもまた、山下の大胆さを証明するかのようなエピソードではないか。
そもそも、「モノ・コトめがね」に掲げられている「モノ」と「コト」というキーワード自体、キュレーターという職能と関係が深い。佐々木俊尚の『キュレーションの時代――「つながり」の情報革命がはじまる』も指摘しているように、キュレーションとは、単に、美しいモノや面白いコンテンツを提供することではない。そうではなく、数多あるモノの中からこれはと思うものを選び出し、組み合わせ、かつまたコンテキストをつくって、場・コトとして提供する行為を指す。このような行為が、美術展に限らず、「情報」への対応についても必要になっているからこそ「キュレーションの時代」と呼ばれるわけだが、山下の営みもまた、彼の言葉を借りれば「この指とまれ」式に人と人とをつなげているという点で、現代的なキュレーションだと言えるだろう。
だが、それだけが、私が山下に「キュレーター」性を見出した理由ではない。そもそも(ここは佐々木が指摘していないところになるけれども)キュレーターとは、展覧会を企画する人を意味するのではなかった。curatorとは、語源的にはラテン語でcurareする人、英語に訳せば、take care ofする人のことなのである。このとき、ケアする対象はなんでもかまわないのであるが、語用としては当然のことながら、人をケアする人としてキュレーターの語はまずは使われた。たとえば病院などで、lunatics、主に今でいうところの統合失調症の人たちをケアする人として、あるいは聖職者の一種に対して使われたこともあった。それがやがて、モノを管理する人に使われるようになり、さらに時が経ち、モノを見せるために並べる人、そして企画する人に使われるようになった。
このように、語源に即して考えれば、キュレーターとは、対象にヒエラルキーをつくらず、公平に、世話をし、引き受け、処理をしながら、大事にする人なのである(全部take care ofの意味だ)。これほど山下にふさわしい言葉もないだろう。またcuratorの語源であるcurareからは、accuracy(的確さ、正確さ)やcurious(好奇心の強い)といった言葉も派生しているように、キュレーターには、的確な好奇心が必要となる。このときの「的確さ」が、対象をひとつに絞るという意味ではないことは、そしてそのような好奇心もまた山下が持っているものであることは、言うまでもない。
以上が、山下をキュレーター的な建築家だといった理由だ。そしてそのようなスタイルが、今後もっと増えるべきだと思うのは、もちろん私がキュレーターであるからではなく、キュレーターに本来求められている「判断をする能力としての趣味は洗練させていくが、個人様式を生み出していくところの趣味は否定していく」姿勢が、今の社会には必要だと考えるからである。
最後に、山下の大胆さを示す余談めいた話をひとつ。《クリスタル・ブリック》の構法で特許をとったと言うので、なぜそうしたのか本人に訊ねてみた。普通、特許と言えば、他人が自由に使用する権利を制限するものであり、山下のスタンスとは相反するように思えたからだ。答えは「逆」だった。彼は、誰でも使えるようにするために特許を取ったというのだ。つまり、自分がとらなければ他の人が特許を取ってしまうかもしれない(そして制限をつけてしまうかもしれない)、そのリスクを回避するために特許を取ったというのである。特許にはそのような「使い方」もあることを恥ずかしながら知らなかったが、これもまた、山下の大胆さを証明するかのようなエピソードではないか。
保坂健二朗 Kenjiro Hosaka
東京国立近代美術館主任研究員。1976年茨城県生まれ。2000年慶應義塾大学大学院修士課程修了。専門は近現代美術。東京国立近代美術館にて、「建築がうまれるとき―ペーター・メルクリと青木淳」(2008年)、「現代美術への視点6 エモーショナル・ドローイング」(2008年)、「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」(2010年)、「イケムラレイコ うつりゆくもの」(2011年)、「ヴァレリオ・オルジャティ」(2011年)を企画・担当。『すばる』『朝日新聞』にて連載。武蔵野美術大学の非常勤講師も務める。
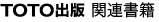
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。