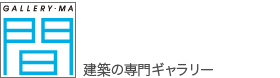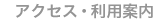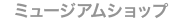- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

講演会レポート
言っていることとやっていることの一致
レポーター=長島明夫
講演ではこれまでに発表された長谷川さんの11作品すべてが2時間以上かけてじっくりと語られた。それらの作品はみな展覧会で、ほとんどが模型として展示されているが、そこでは各作品の在り方に対してそれぞれ特徴的な展示の仕方が考えられており、この講演の内容を踏まえて鑑賞することで、より深い作品の理解が得られるのではないかと思う。すべての作品が網羅された作品集『Go Hasegawa Works』も併せてめくってみるなら言うことなしである。講演は動画として、この同じサイト内で公開されているので、当日聴講されなかった方はそこでご覧いただくとして、この小文では講演の内容よりもその語り口のようなものについて、感じたことをすこし書いておきたい。
講演ではこれまでに発表された長谷川さんの11作品すべてが2時間以上かけてじっくりと語られた。それらの作品はみな展覧会で、ほとんどが模型として展示されているが、そこでは各作品の在り方に対してそれぞれ特徴的な展示の仕方が考えられており、この講演の内容を踏まえて鑑賞することで、より深い作品の理解が得られるのではないかと思う。すべての作品が網羅された作品集『Go Hasegawa Works』も併せてめくってみるなら言うことなしである。講演は動画として、この同じサイト内で公開されているので、当日聴講されなかった方はそこでご覧いただくとして、この小文では講演の内容よりもその語り口のようなものについて、感じたことをすこし書いておきたい。

前半、長谷川さんが「五反田の住宅」の説明をするなか、「建物をふたつに分けて真ん中に螺旋階段を差し込むなんていうと非常に大げさに聞こえるかもしれませんが、やってるのは言ってみればスキップフロア形式ですね」という言い回しに聞き覚えがあった。おそらく過去の数々のレクチャーでも、同じフレーズがくり返されてきたのだろう。私が長谷川さんの自作解説をはじめて聴いたのは2007年の10月のことで、刺激的な内容に興奮したのを覚えている。当時の手帳には落ち着きのない字で次のように書かれていた。「明快なストーリーがありつつ、建築界での批評性と現実的な生活体験を与える質が乖離していないように見える。二面性があっての両立という感じではなくて、ひとつの物差しで無理なく測れるような」。
この印象はきっと今回の講演会および展覧会の「スタディとリアル」というテーマとも重なるところがあるだろう。建築の設計において、さまざまな現実の条件や状況から向き合うべきいくつかの問題を浮かび上がらせ、それらを動的に検討しながら1本のストーリーを導き、かたちに昇華させる。なにしろ長谷川さんの言葉は明快である。ご本人は悩むことや分からない状態を持続することの大切さも言っているが、その言葉自体明快である。想像するに、その明快さは誰かになにかを伝える、表現することに対しての責任感から来るのかもしれない。自らのなまなましい情念を表出させることをよしとせず、そことは一線を画した公に共有可能な言葉を発すること。それは長谷川さんの人間としての公正さにも通じる。
長谷川さんとは友人としてプライベートな場で話をすることもあるのだけれど、そうしたときでも、たとえば事務所の経営状況だとか、親の老後の問題だとか、同年代の人間がお酒を飲みながらつい口にしてしまいそうな、べったりした内輪の話を長谷川さんが積極的に話すことはほとんどない。かといってそれが他人行儀に感じられるかというと決してそんなことはなく、そこにいるのは建築や建築を語る言葉から察せられるのと同じ、爽やかな長谷川さんなのである。その姿は日頃なにかと公私を混同しがちな私にとって無言の戒めともなるのだが、それはともかく、こうした長谷川さんの公正な態度や公私の明瞭な線引きは、創作のより深いレベルでも見受けられるように思う。
この印象はきっと今回の講演会および展覧会の「スタディとリアル」というテーマとも重なるところがあるだろう。建築の設計において、さまざまな現実の条件や状況から向き合うべきいくつかの問題を浮かび上がらせ、それらを動的に検討しながら1本のストーリーを導き、かたちに昇華させる。なにしろ長谷川さんの言葉は明快である。ご本人は悩むことや分からない状態を持続することの大切さも言っているが、その言葉自体明快である。想像するに、その明快さは誰かになにかを伝える、表現することに対しての責任感から来るのかもしれない。自らのなまなましい情念を表出させることをよしとせず、そことは一線を画した公に共有可能な言葉を発すること。それは長谷川さんの人間としての公正さにも通じる。
長谷川さんとは友人としてプライベートな場で話をすることもあるのだけれど、そうしたときでも、たとえば事務所の経営状況だとか、親の老後の問題だとか、同年代の人間がお酒を飲みながらつい口にしてしまいそうな、べったりした内輪の話を長谷川さんが積極的に話すことはほとんどない。かといってそれが他人行儀に感じられるかというと決してそんなことはなく、そこにいるのは建築や建築を語る言葉から察せられるのと同じ、爽やかな長谷川さんなのである。その姿は日頃なにかと公私を混同しがちな私にとって無言の戒めともなるのだが、それはともかく、こうした長谷川さんの公正な態度や公私の明瞭な線引きは、創作のより深いレベルでも見受けられるように思う。

講演では2006年のデビュー作から「未完成の」と言うべき最新作まで、11の作品が時系列で語られた。時系列という形式は一見ニュートラルであり、また実際そのように無自覚的・消去法的に用いられることが多いと思うけれど、今回の講演では長谷川さんも冒頭すこし触れていたように、それはある程度積極的に選択されている。つまり時系列で語ることは、あるストーリーを語ることであり、それぞれの作品を相対化してそのストーリーに位置づけるということである。もちろん建築家が自作を時系列で語ることは珍しいことではない。たとえば長谷川さんに近いところで、師匠筋の篠原一男や坂本一成はそれが特徴的な建築家だろう。とはいえ篠原一男の作品はそもそも時系列でしか語りえないくらいの強い時代区分がされているし(第1の様式~第4の様式)、坂本一成が自作を時系列で対象化して語るようになったのは、建築をつくり始めてそれなりの年月を経てからのことだと思う。それに比べて長谷川さんは、作品の質においてもそれほど明らかな年代的展開があるわけではなく、その前提になる建築家としての経歴も短い。
講演では11の作品が時系列で順番に語られるとともに、そのなかでさらに(1)「森のなかの住宅」「桜台の住宅」「五反田の住宅」、(2)「狛江の住宅」「練馬のアパートメント」、(3)「森のピロティ」「浅草の町家」、(4)「駒沢の住宅」「経堂の住宅」、(5)「日本デザインセンター」、(6)「石巻の鐘楼」と、グループに分節され、それらのセットで作品が意味づけられた。しかしこの年代ごとの分節と意味づけは、それぞれ面白い視点が提示されているとは思うものの、作品にとってそれほど必然性がある切り口だとは考えにくい。おそらく長谷川さん自身も絶対的な区分だとは認識していないのではないか。であるならなぜ、と疑問に思いたくなるのは、このような自分語りにはひとつの危うさが伴うからである。自作を時系列のストーリーに乗せること、言い換えると自分の作品歴に過去から現在へ1本の軸を描くことは、同時に未来への道すじを示すことにもなるだろうが、それはまた自らの未来を拘束することにもなりかねない。これからつくられる作品はつねに現在の自分を超えていく存在であるべきだろうが、その在り方を現在の自分が想定するのは困難なのである。ところが長谷川さんはいつものように明快に思い切りよく言葉を発していく。
この行為の理由を考えてみると、まずは上で書いたように、公に表現することに対しての責任感、つまり聴衆になるべく有益で共有可能な内容を伝えようとするということが挙げられると思う。そしてもうひとつ、そうした公共的な言葉が長谷川さん自身にとっても同様に有益で共有可能であること、いわば自分に向けての批評として作用させること。このふたつ目の理由を可能にさせるのが、先に指摘した長谷川さんの明瞭な公私の線引きではないかと思うのだ。自作を対象化して明快な言葉にし、「私情」を挟まず自分から切り離せるからこそ、再びその言葉の内容を客観的に判断することができる。それは次作の糧にこそなれ、そこに囚われることがない。
じつは以上の推論は、長谷川さんが自らの設計手法について語る言葉に着想を得ている。長谷川さんは設計作業のなかで数多くのスタディ模型を作るという。なぜなら「ぼんやりとした頭のなかのイメージや断片的なスケッチは、自分の身体の内側から抜け出ていない。イメージを外在化し、一旦距離を置くために模型にする」※。けれども一般に、スタディ模型をたくさん作れば作るほどよい建築が生まれるということは言えないと思う。むしろ個人の頭のなかの生き生きとしたイメージが中途半端な状態で外部にかたちを与えられることで、その生気を奪われてしまうということもあるに違いない。そうした模型は現実の物体がもつ有無を言わさないリアリティで、人間の自由な想像力を拘束するかもしれない。だから、スタディ模型を大量に作ることが長谷川さんの設計において有効なのだとしたら、それはやはり、そこでアウトプットする模型群に対して公私の線引きがうまく機能しているからではないだろうか。展覧会の趣旨文には「スタディ」という言葉に関して、「自分がつくった案を客観的に眺め、考え、改め、育てていく行為は、まさに自ら能動的に学んでいくプロセスでもある」と書かれている。
さて、ここまで来てあらためて今回の講演を振り返ってみると、それは展覧会の開催に合わせて自作の解説をするという現実の与条件に対し、すべての作品を時系列で語るという形式が用いられたものだった。そこでは個々の作品が時間軸のストーリーのなかで意味づけられた。そしてその理由のひとつを、聴衆に対する言葉としての表現の責任、もうひとつを自身への客観的な批評とするなら、それはまさしく、長谷川さんが自らの建築について言う「スタディとリアルの応答」にほかならない。言ってみればこの講演会は、過去の作品の「スタディとリアル」が語られるのと同時に、それと相似形の「スタディとリアル」が実践された、そんな場だったのである。
※長谷川豪『長谷川豪 考えること、建築すること、生きること』(INAX出版、2011、p.36)
講演では11の作品が時系列で順番に語られるとともに、そのなかでさらに(1)「森のなかの住宅」「桜台の住宅」「五反田の住宅」、(2)「狛江の住宅」「練馬のアパートメント」、(3)「森のピロティ」「浅草の町家」、(4)「駒沢の住宅」「経堂の住宅」、(5)「日本デザインセンター」、(6)「石巻の鐘楼」と、グループに分節され、それらのセットで作品が意味づけられた。しかしこの年代ごとの分節と意味づけは、それぞれ面白い視点が提示されているとは思うものの、作品にとってそれほど必然性がある切り口だとは考えにくい。おそらく長谷川さん自身も絶対的な区分だとは認識していないのではないか。であるならなぜ、と疑問に思いたくなるのは、このような自分語りにはひとつの危うさが伴うからである。自作を時系列のストーリーに乗せること、言い換えると自分の作品歴に過去から現在へ1本の軸を描くことは、同時に未来への道すじを示すことにもなるだろうが、それはまた自らの未来を拘束することにもなりかねない。これからつくられる作品はつねに現在の自分を超えていく存在であるべきだろうが、その在り方を現在の自分が想定するのは困難なのである。ところが長谷川さんはいつものように明快に思い切りよく言葉を発していく。
この行為の理由を考えてみると、まずは上で書いたように、公に表現することに対しての責任感、つまり聴衆になるべく有益で共有可能な内容を伝えようとするということが挙げられると思う。そしてもうひとつ、そうした公共的な言葉が長谷川さん自身にとっても同様に有益で共有可能であること、いわば自分に向けての批評として作用させること。このふたつ目の理由を可能にさせるのが、先に指摘した長谷川さんの明瞭な公私の線引きではないかと思うのだ。自作を対象化して明快な言葉にし、「私情」を挟まず自分から切り離せるからこそ、再びその言葉の内容を客観的に判断することができる。それは次作の糧にこそなれ、そこに囚われることがない。
じつは以上の推論は、長谷川さんが自らの設計手法について語る言葉に着想を得ている。長谷川さんは設計作業のなかで数多くのスタディ模型を作るという。なぜなら「ぼんやりとした頭のなかのイメージや断片的なスケッチは、自分の身体の内側から抜け出ていない。イメージを外在化し、一旦距離を置くために模型にする」※。けれども一般に、スタディ模型をたくさん作れば作るほどよい建築が生まれるということは言えないと思う。むしろ個人の頭のなかの生き生きとしたイメージが中途半端な状態で外部にかたちを与えられることで、その生気を奪われてしまうということもあるに違いない。そうした模型は現実の物体がもつ有無を言わさないリアリティで、人間の自由な想像力を拘束するかもしれない。だから、スタディ模型を大量に作ることが長谷川さんの設計において有効なのだとしたら、それはやはり、そこでアウトプットする模型群に対して公私の線引きがうまく機能しているからではないだろうか。展覧会の趣旨文には「スタディ」という言葉に関して、「自分がつくった案を客観的に眺め、考え、改め、育てていく行為は、まさに自ら能動的に学んでいくプロセスでもある」と書かれている。
さて、ここまで来てあらためて今回の講演を振り返ってみると、それは展覧会の開催に合わせて自作の解説をするという現実の与条件に対し、すべての作品を時系列で語るという形式が用いられたものだった。そこでは個々の作品が時間軸のストーリーのなかで意味づけられた。そしてその理由のひとつを、聴衆に対する言葉としての表現の責任、もうひとつを自身への客観的な批評とするなら、それはまさしく、長谷川さんが自らの建築について言う「スタディとリアルの応答」にほかならない。言ってみればこの講演会は、過去の作品の「スタディとリアル」が語られるのと同時に、それと相似形の「スタディとリアル」が実践された、そんな場だったのである。
※長谷川豪『長谷川豪 考えること、建築すること、生きること』(INAX出版、2011、p.36)
長島明夫 Akio Nagashima
編集者。1979年神奈川県生まれ。2001年明治大学卒業、2003年東京工業大学大学院修士課程修了、同年から2008年までエクスナレッジに勤務したのち独立、2009年『建築と日常』誌を創刊。編書『昭和住宅メモリー』(エクスナレッジ、2005)、『ザ・藤森照信』(エクスナレッジ、2006)、『建築に内在する言葉』(坂本一成著、TOTO出版、2011)など、共編著書『映画空間400選』(結城秀勇共編、INAX出版、2011)。
『建築と日常』
『建築と日常』編集者日記
『建築と日常』
『建築と日常』編集者日記
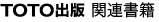
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。