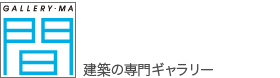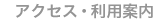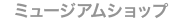- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

展覧会レポート
社会に淫することなかれ
レポーター=日埜直彦
非常に特別なシチュエーションにおかれた建築家が、そのシチュエーションの固有性を味方にし、そのリアリティに力を得た作品をつくっていくことは珍しいことではない。逆に、その場の現実から遊離しスタイリッシュで表層的なデザインがただ突出するような建築は、要するにどこでつくってもいいわけでまさにそこにある必然性を欠く。建築が説得力を持ち、見るものに迫ってくるのは、それが建つ場所、そこで求められているプログラム、それを使うヒトといった建築の背景に深く根ざした固有の姿を見せる時だ。
ところが今、TOTOギャラリー・間で展覧会が行われているアレハンドロ・アラヴェナは必ずしも固有性に依存した建築家ではない。一方に文脈と関係ない建築があり、他方に深く文脈に結びついた建築があるとして、アラヴェナの仕事は文脈の内側から考えられているという意味で間違いなく後者のタイプではあるのだが、面白いことに彼はその固有性に依存して特殊解に彼の建築がすっぽりおさまることは拒んでいるようだ。以下、アラヴェナの仕事が一方で如何に彼の仕事がおかれているシチュエーションに根ざしつつ、他方である種の一般性へ向かっているのか、そのありようを今回の展示から見てみよう。
非常に特別なシチュエーションにおかれた建築家が、そのシチュエーションの固有性を味方にし、そのリアリティに力を得た作品をつくっていくことは珍しいことではない。逆に、その場の現実から遊離しスタイリッシュで表層的なデザインがただ突出するような建築は、要するにどこでつくってもいいわけでまさにそこにある必然性を欠く。建築が説得力を持ち、見るものに迫ってくるのは、それが建つ場所、そこで求められているプログラム、それを使うヒトといった建築の背景に深く根ざした固有の姿を見せる時だ。
ところが今、TOTOギャラリー・間で展覧会が行われているアレハンドロ・アラヴェナは必ずしも固有性に依存した建築家ではない。一方に文脈と関係ない建築があり、他方に深く文脈に結びついた建築があるとして、アラヴェナの仕事は文脈の内側から考えられているという意味で間違いなく後者のタイプではあるのだが、面白いことに彼はその固有性に依存して特殊解に彼の建築がすっぽりおさまることは拒んでいるようだ。以下、アラヴェナの仕事が一方で如何に彼の仕事がおかれているシチュエーションに根ざしつつ、他方である種の一般性へ向かっているのか、そのありようを今回の展示から見てみよう。

1枚の紙に切り込みを入れ、折ることで組み立てられた模型。キャンチレバーに括りつけられた糸の先の針は、重力に逆らい、壁に向かう(影に注目!)
© Nacása & Partners Inc.
© Nacása & Partners Inc.
ラテンアメリカの建築家と社会
アラヴェナはチリの建築家として、我々から見ればラテンアメリカの建築家の系譜上に見えてくる。階級社会的な性格が強く残り貧富の差の激しいラテンアメリカの社会において、そこで活動する建築家は富裕層あるいは文化的な社会層の中での活動を中心としてきた。そのなかでアラヴェナは、広く社会全体を視野に入れて活動する新しい世代の建築家の一人である。

ワイヤーと斜め材とのバランスで水平を保つ約150kgの無垢材。その上に木製のボリューム模型(9作品)が並ぶ
© Nacása & Partners Inc.
© Nacása & Partners Inc.
1902年生まれのルイス・バラガン、1907年生まれのオスカー・ニーマイヤーあたりがラテンアメリカの近代建築の最初の世代になるが、彼らの仕事はブルジョア層の閉じられた社会の内側にすっぽりおさまる。そして1954年生まれのエンリケ・ノルテン、あるいは1965年生まれのマティアス・クロッツの世代まで下ってきてもこうしたあり方はほとんど変わっていない。敢えて典型的に言うならば、彼らはいくらかバナキュラーな風土と素材を取り込みつつモダニズムのマナーで正統的な建築を作る建築家であり、富裕層の住宅を中心とした彼らの作品は一種快楽的な優雅さにおいて我々を魅了してきた。貧困層と関わるような仕事がほとんどないことと彼らの政治的スタンスに関係があるのかどうかはよくわからないが、ラテンアメリカから輩出される多くの建築家は富裕層の求めに応じて設計を行うという枠からはみ出ることは稀だった。これに対し1967年生まれのアラヴェナ、あるいは昨年同じくTOTOギャラリー・間での展覧会に参加していた1965年生まれのスミルハン・ラディック、あるいはスーパースダカなど、建築家というプロフェッションのロールモデルを組み替えつつ、ラテンアメリカの社会の現実に向き合う建築家が出てきたというわけだ。そのラテンアメリカの社会の現実とはなにか? まずはなんと言っても猛烈な都市化、そして泥沼のようなスラム(ファベーラ)である。こうした問題に対して、建築家はその職能にもかかわらず長らく切り離されていた。

「セント・エドワード大学 学生寮」ボリューム模型
© Nacása & Partners Inc.
© Nacása & Partners Inc.
ラテンアメリカはそもそも高度に都市化した地域である。植民地化の歴史から来る社会構造がそうさせたのだろうが、ラテンアメリカ全体の1950年の都市人口比率は41%、そして2010年には80%に達する。意外かもしれないがこれは一貫して日本の都市人口比率より大幅に高い(1950年に35%、2010年に67%)。この激しい都市化の内実は都市の成長というよりもむしろ地方から都市周縁部のスラムへの人口流入であり、2010年のラテンアメリカの都市内スラムに居住する住民の人口比率が実に人口全体の1/4を占める。例えば映画「黒いオルフェ」の山肌に張り付く住宅密集地の迷路のようなあのスラムを思い浮かべれば良いだろう。貧困と不衛生、犯罪と薬物中毒に沈滞するそのイメージがステレオタイプに過ぎるとしても、閉塞した困難にもかかわらずあまりにも繁茂してもはや手の付けようがないほどに広がったスラムはラテンアメリカの都市の現実である。アラヴェナが活動するチリはラテンアメリカの中では比較的ましな状況にあるというが、こうした社会問題と向き合う建築家がようやく若い世代から出てきつつあるということなのだ。
その上でラディックがややアーティスティックに状況と応答し、スーパースダカが人々の間に分け入ったインフォーマルな実践の中からその活動を展開しているのに対し、アラヴェナの活動はきわめてオーソドックスな建築的手法に沿っていると言って良いだろう。今回展示されているプロジェクトの中でも「キンタ・モンロイの集合住宅」などのソーシャル・ハウジングでのアプローチはまさにそれを示している。限られた建築予算をユーティリティ系を含むコア部分の建設に費やし、あるべき本来の床面積の残りは住民の自助努力で増築を想定する手法は、スラム改良手法としてはごく一般的なコア・ハウジングに他ならないし、コミュニティーを維持しながらオンサイトで住宅改善を行う方針も、ペルーでスラム改善に取り組んだジョン・ターナーの記念碑的な著作『Housing by People』以来世界的に試みられている手法の一例に過ぎない。逆に言えば、試行錯誤を続けている世界的なスラムへの取り組みの中から醸成されてきたこうした手法を踏まえた上で、アラヴェナのプロジェクトは成立している。それ自体は独自性というよりはむしろ一般的な解に過ぎない。ただ彼はそれをシリアスな建築家の仕事として徹底しているのだ。
その上でラディックがややアーティスティックに状況と応答し、スーパースダカが人々の間に分け入ったインフォーマルな実践の中からその活動を展開しているのに対し、アラヴェナの活動はきわめてオーソドックスな建築的手法に沿っていると言って良いだろう。今回展示されているプロジェクトの中でも「キンタ・モンロイの集合住宅」などのソーシャル・ハウジングでのアプローチはまさにそれを示している。限られた建築予算をユーティリティ系を含むコア部分の建設に費やし、あるべき本来の床面積の残りは住民の自助努力で増築を想定する手法は、スラム改良手法としてはごく一般的なコア・ハウジングに他ならないし、コミュニティーを維持しながらオンサイトで住宅改善を行う方針も、ペルーでスラム改善に取り組んだジョン・ターナーの記念碑的な著作『Housing by People』以来世界的に試みられている手法の一例に過ぎない。逆に言えば、試行錯誤を続けている世界的なスラムへの取り組みの中から醸成されてきたこうした手法を踏まえた上で、アラヴェナのプロジェクトは成立している。それ自体は独自性というよりはむしろ一般的な解に過ぎない。ただ彼はそれをシリアスな建築家の仕事として徹底しているのだ。
Think Local, Act Global.
ラテンアメリカ社会の厳しい現実に向き合い、そこに現にある経済的、政治的、そして文化的な文脈の内側から、建築が答えられるあり方を探り出していく、その限りで彼の建築はその固有の文脈に発するものだ。厳しい経済的条件の中で、低廉な技術に縛られ、住民の中から小さな芽を丁寧に育てていくことなしにあれらの仕事が成立するわけはない。だが意外なことに、こうして概観してきたヘビーな現実を、今回の展示から見て取るのはなかなか難しいだろう。

プロジェクトの情報が付けられたヘリウム・バルーンが浮かぶ
© Nacása & Partners Inc.
© Nacása & Partners Inc.
ヘビーな現実どころか、むしろアラヴェナの今回のプレゼンテーションは「軽さ」がテーマだったかも知れない。展示の構成は、一枚の紙を刻んで作られたポップアップ絵本のような紙模型と、小さな木片から削り出されたラフなヴォリューム模型。プロジェクト紹介が小さな紙にプリントされ風船に結びつけられてふわふわ浮かび、そして彼がデザインしたものの中でも良く知られた椅子(?)「チェアレス」で床にしゃがみ込んで見るビデオ・プレゼンテーション。地球の反対側から日本に展示物を送るという与条件からこのコンパクトな展示セットが考案されたというが、仮にそうした条件が課せられていたのだとしても、だからといって彼の建築が背負っている社会性をここまで捨象し、ほとんど詩的な表現に転回したプレゼンテーションには普通はならないだろう。浮かんだ風船を引き下ろしプロジェクト紹介を読ませ、あるいは床にしゃがみ込んで映像を見せるヒューマンスケールを意識した身体的なプレゼンテーションの一方で、一枚の紙から立て起こされる紙模型によって軽快な表現が試みられ、あるいは木の模型に依って朴訥とした手の痕跡とマテリアリティが展示に持ち込まれる。もちろんプロジェクトの詳細を丁寧に展示から読み取れば、こうした軽やかな表現の向こう側にそのリアリティは見えてくるのだが、プロジェクトの依って立つ固有の条件によってその有意義さを裏付けるようなそぶりは一切なく、むしろデザインの美的な次元が抽出され、多様な表現で提示されているかのように見える。この振れ幅がこの建築家の一番面白いところではないだろうか。

椅子いらずの椅子(?)「チェアレス」で座り、ビデオを視聴する
© Nacása & Partners Inc.
© Nacása & Partners Inc.
建築的知性
そのことは展示そのものに限った話ではない。建築家のスタンスがそもそもそうなのだろう。アラヴェナは具体的な仕事においてきわめてローカルな状況に密着している。しかし同時に建築家としての彼のスタンスはきわめてニュートラルであり、そのヘビーさそのものを彼の固有性として見せることを慎重に避けながら、一歩下がったところにフリーハンドで構えているようだ。その意味で彼はいわゆる「社会派」の建築家ではない。むしろ単に建築家なのである。チリの現実を離れまったく異なるシチュエーションで建築に取り組むことがあれば、彼のデザインは根本的に変わるだろう。これまでの彼の設計に見える彼の作風はそこで一変するかもしれない。しかしそこで一貫している核心はオープンマインドな建築的知性の行使なのだ。
ニーマイヤー設計によるランドスケープの写真が展示の最初に一枚掲げられている。ニーマイヤーお得意のおおらかな曲線によるプロムナードなのだが、人々はニーマイヤーの創意など一顧だにせずショートカットしていて、その踏み跡がその写真に写っている。アラヴェナは人々の生活の持っているこのどうにもならない指向性をそのまま受け入れ尊重しようと言う。このフレキシブルなスタンスは、したたかであり、一種爽やかでもある。
ニーマイヤー設計によるランドスケープの写真が展示の最初に一枚掲げられている。ニーマイヤーお得意のおおらかな曲線によるプロムナードなのだが、人々はニーマイヤーの創意など一顧だにせずショートカットしていて、その踏み跡がその写真に写っている。アラヴェナは人々の生活の持っているこのどうにもならない指向性をそのまま受け入れ尊重しようと言う。このフレキシブルなスタンスは、したたかであり、一種爽やかでもある。
日埜直彦 Naohiko Hino
1971年
茨城県生まれ
1994年
大阪大学工学部建築工学科卒業
1994~2002年
アークスコーベ勤務
2002年
日埜建築設計事務所設立
2006年~
芝浦工業大学非常勤講師
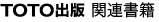
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。