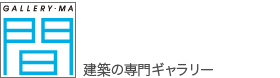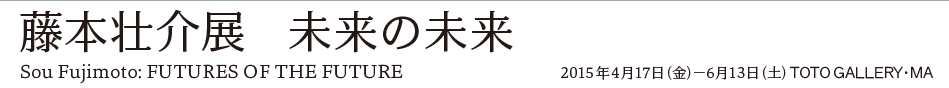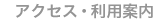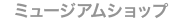- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

展覧会レポート
1995年からの希望の建築またはフューチャーモンスター
レポーター=倉方俊輔
藤本壮介のプロジェクトを見ると、これ以上単純にならないだろうというワンアイデアを堂々とやっている。 「藤本壮介展 未来の未来」には、そんな大胆なプロジェクトの模型が並んでいた。プロジェクトの大きさや地域や年代のヒエラルキーを付けずに、ほぼ同一の率直なつくりの展示台に載って、建物の内外も無視するかのように、会場全体に散りばめられていた。 今までにないほどの客足だという。訪れた際にも多くの人がいた。建築学生や建築関係者のような方々ばかりではない。デザインやアートに普通に関心を持っているようなカップルや家族連れも目立った。海外からの人も多かった。もはや若手という枠を超えて、藤本壮介は現代日本の建築家を代表する存在となったことが分かる。
「パシャ」「カシャ」。会場にシャッター音が響くのは、展覧会の撮影を許可しているためだ。「未来すぎる!?」と興味をそそるプロジェクトの姿は、それぞれのスマートフォンに収まり、お気に入りのSNSで拡散されて、この場所に次の人々を呼び寄せることだろう。
意外にも、インフォメーションテクノロジーの進展で「復活」したのは建築だった。建築は複雑な思想を誰にでも同じように伝えたりすることは苦手。でも、公開性(敷地の外からまったく見えない建築というのは珍しい)があるから、特に明快さや大胆さが画像で伝わるようなものは拡散されやすい。1995年以降、インフォメーションテクノロジーが空前の旅行ブームを生み、同時に体験を拡散するようなプラットフォームを築いた。今や世界中の人々が、自らの美しい人生を彩るものとして、誰に頼まれたわけでも無いのに、訪れた先々の建築を撮り、ネット上にアップし、実際に行ってみたいと思わせる。まるでマチュピチュやグランドキャニオンのように「自然」だ。そんな建築の効果を、現代の建築家はいっそう意識して設計を行うようになった。意識しているように振る舞うか、そうでないかには各人の戦略があるにしても、私たちはもはや、そうした想像と実体の、自分が見る自分と他人が見る自分とのハイスピードな往還の外に出ることはできない。
それが1995年以降の世界だ。でも、建築はまだ生きている。いや願わくば、いっそう生きているのだと思いたい。
藤本壮介のプロジェクトを見ると、これ以上単純にならないだろうというワンアイデアを堂々とやっている。 「藤本壮介展 未来の未来」には、そんな大胆なプロジェクトの模型が並んでいた。プロジェクトの大きさや地域や年代のヒエラルキーを付けずに、ほぼ同一の率直なつくりの展示台に載って、建物の内外も無視するかのように、会場全体に散りばめられていた。 今までにないほどの客足だという。訪れた際にも多くの人がいた。建築学生や建築関係者のような方々ばかりではない。デザインやアートに普通に関心を持っているようなカップルや家族連れも目立った。海外からの人も多かった。もはや若手という枠を超えて、藤本壮介は現代日本の建築家を代表する存在となったことが分かる。
「パシャ」「カシャ」。会場にシャッター音が響くのは、展覧会の撮影を許可しているためだ。「未来すぎる!?」と興味をそそるプロジェクトの姿は、それぞれのスマートフォンに収まり、お気に入りのSNSで拡散されて、この場所に次の人々を呼び寄せることだろう。
意外にも、インフォメーションテクノロジーの進展で「復活」したのは建築だった。建築は複雑な思想を誰にでも同じように伝えたりすることは苦手。でも、公開性(敷地の外からまったく見えない建築というのは珍しい)があるから、特に明快さや大胆さが画像で伝わるようなものは拡散されやすい。1995年以降、インフォメーションテクノロジーが空前の旅行ブームを生み、同時に体験を拡散するようなプラットフォームを築いた。今や世界中の人々が、自らの美しい人生を彩るものとして、誰に頼まれたわけでも無いのに、訪れた先々の建築を撮り、ネット上にアップし、実際に行ってみたいと思わせる。まるでマチュピチュやグランドキャニオンのように「自然」だ。そんな建築の効果を、現代の建築家はいっそう意識して設計を行うようになった。意識しているように振る舞うか、そうでないかには各人の戦略があるにしても、私たちはもはや、そうした想像と実体の、自分が見る自分と他人が見る自分とのハイスピードな往還の外に出ることはできない。
それが1995年以降の世界だ。でも、建築はまだ生きている。いや願わくば、いっそう生きているのだと思いたい。

第一会場 © Nacása & Partners Inc.
展覧会場の体験に話を戻そう。ご承知のように、TOTOギャラリー・間の第1会場(3階)と第2会場(4階)の間には広い外部空間があって、ここをどう使うかが肝要となるのだが、藤本展は内外をあっけらかんとつないでいて、建物の外部と内部の区別を解き放っていた。訪れた日の天候が良かったこともあるけれど、外部をぐるぐるまわっている子どもがいたり、階段の下に腰掛けている人がいたり。こうして見てほしいと主張するような完成度ではなく、使い方のゆるさを許容するデザインが心地よい。気づけば、自分も長居をしていた。
展覧会が、単純であること、大胆であること、ヒエラルキーが無いこと、インターナショナルであること、SNS社会に適合していること、内外の境を外すこと、使い方がゆるいこと。つらつらと書き進めた内容を振り返ってみると、以上7つの展覧会の特徴は、藤本建築の特徴なのである。
展覧会場全体が、藤本建築になっている。これも藤本壮介自身が思い浮かぶほどに、表裏のないストレートな手法だ。しかし、実現するのは難しい。どうやってこれが成功しているのか。
展覧会が、単純であること、大胆であること、ヒエラルキーが無いこと、インターナショナルであること、SNS社会に適合していること、内外の境を外すこと、使い方がゆるいこと。つらつらと書き進めた内容を振り返ってみると、以上7つの展覧会の特徴は、藤本建築の特徴なのである。
展覧会場全体が、藤本建築になっている。これも藤本壮介自身が思い浮かぶほどに、表裏のないストレートな手法だ。しかし、実現するのは難しい。どうやってこれが成功しているのか。

第一会場全景 室内より中庭を見る © Nacása & Partners Inc.
藤本壮介がこんなに人気があるのは、期待を裏切らないからだろう。
例えば、建築学生からの「建築家」に対する期待。多様なプロジェクトが収まっている図録の最後に載った藤本壮介のプロフィールは「1971 北海道生まれ/1994 東京大学工学部建築学科卒業/2000 藤本壮介建築設計事務所設立」とわずか3行なのである。
大学院も進まず、留学もせず、有名建築家のアトリエで修行することもなく・・これ以上、何も引けない美しさだ。しかし、独り概念を深化させ、コンペの入選を積み重ねて実力が認められ、日本各地から世界へ次第に大きな実作が完成するようになる。作品の質だけで勝負する単独者としての建築家、という像を建築家を目指した者なら誰もが一度は頭に思い描いたことがあるのではないだろうか。そんな「建築家」に対する期待を裏切らない。藤本壮介は建築学生の憧れであることも、もっともだ。
しかし、時に青臭い建築学生からの人気と、一般人からの認識がズレるもの。しかし、藤本壮介の卓越したところは「ヘンな形をつくるのが建築家」といったくらいの皮相な期待にも十分に応えられる点だ。
「期待を裏切る」とは、かつてはクリエイティヴィティに対する賞賛の形容詞だったが、この「つながり」の時代には、単にネガティヴな言葉になってしまう。この点でも、期待を裏切らない藤本壮介は、1995年からの世界に適合している。
もちろん、藤本壮介は大衆的な期待に応じているのではなく、その先に進んでいる。あくまで「アトリエ建築家」的に振舞いながらその潜在力を、「ヘンな形」を実現させながらその可能性を、鼓舞している。単に過去から引きずったイメージに乗っているのではなく、行動は未来に向いているのだ。
例えば、建築学生からの「建築家」に対する期待。多様なプロジェクトが収まっている図録の最後に載った藤本壮介のプロフィールは「1971 北海道生まれ/1994 東京大学工学部建築学科卒業/2000 藤本壮介建築設計事務所設立」とわずか3行なのである。
大学院も進まず、留学もせず、有名建築家のアトリエで修行することもなく・・これ以上、何も引けない美しさだ。しかし、独り概念を深化させ、コンペの入選を積み重ねて実力が認められ、日本各地から世界へ次第に大きな実作が完成するようになる。作品の質だけで勝負する単独者としての建築家、という像を建築家を目指した者なら誰もが一度は頭に思い描いたことがあるのではないだろうか。そんな「建築家」に対する期待を裏切らない。藤本壮介は建築学生の憧れであることも、もっともだ。
しかし、時に青臭い建築学生からの人気と、一般人からの認識がズレるもの。しかし、藤本壮介の卓越したところは「ヘンな形をつくるのが建築家」といったくらいの皮相な期待にも十分に応えられる点だ。
「期待を裏切る」とは、かつてはクリエイティヴィティに対する賞賛の形容詞だったが、この「つながり」の時代には、単にネガティヴな言葉になってしまう。この点でも、期待を裏切らない藤本壮介は、1995年からの世界に適合している。
もちろん、藤本壮介は大衆的な期待に応じているのではなく、その先に進んでいる。あくまで「アトリエ建築家」的に振舞いながらその潜在力を、「ヘンな形」を実現させながらその可能性を、鼓舞している。単に過去から引きずったイメージに乗っているのではなく、行動は未来に向いているのだ。

模型 手前はPrimitive Future House(2001) © Nacása & Partners Inc.
藤本壮介の仕事が、なぜこのように成功しているか。その鍵も展覧会場の中にある。なぜなら、すでに明らかにしたように、展覧会の特徴は、藤本建築の特徴だからである。
先に触れたように「藤本壮介展 未来の未来」の会場構成は、第一に、コンテクスチャリズムではない。第1会場において展示台は内部と外部の分け隔てなく散在されており、外に据えられた石も段差もまるで存在しないかのようだ。第2会場では展示台がグリッド状に配置されているが、展示の仕方に変更はない。第二に、イデアリズムでもない。何かの理念の表現として作り込まれてはおらず、理念からの演繹のようにヒエラルキカルでもない。以上のように、周辺敷地から考え始めているようには見えないが、強い理念があるようにも見えないというのは展覧会の特徴であり、藤本建築の特徴である。
では、形態は何かのアルゴリズムによって生み出されたものなのか。あるいは判断を放棄し、ランダムに決定してしまったものなのだろうか。そのどちらでもないだろう。敷地を無視した単純なアイデアのようで、作り込んでいるのが、実際の藤本建築である。「藤本壮介展 未来の未来」では、近いアイデアのプロジェクトが近傍に配置されていた。アイデアは複合し、交差しているものだから、明確にはセクション分けできない。これとこれとは確かに続いているのだけど、どこまでがひとくくりと言われると困る。「困難は分割せよ」と説くデカルトに「いやいや、その分割が困難なんですよ」とぐずりたくなる気分に対して、形を与えている。
100あまりの模型の一つ一つに、短い説明文がテプラのような素材でチープに貼られている。その言葉は図録からの抜粋ではなかった。したがって、模型そのものとフィットして自然に感じられる。機械的な作業の結果というものは、すぐにそれと気づくものだ。1995年以降のインフォメーションテクノロジーの進展によって人材と商材のロジスティクスが飛躍的に向上し、寡占化が進む世の中で、私たちはいっそうそのことに敏感になってしまった。それ以上であるからお金が取れるビジネスに匹敵する心地よさが、藤本壮介の展覧会場にはあった。手作業で調整しているがゆえである。何気ないような展示台の高さや配置も、粘って最後まで微妙に動かしているから、人々が行動できる空間がワンアイデアで自然に成立したように見えている。一見、システマティックに思えて、背後に人間くさい作り込みが横たわっている。藤本壮介の建築を訪れた時の体験も、そのようなものだ。暑苦しくないのが今風である。
このような作り込みに接すると、単純なアイデアが載ったように見える模型も、実際に建てるプロセスにおいて周辺環境に適した落とし込みがなされ、単に模型を大きくしたようなものにならないことが想像できる。
先に触れたように「藤本壮介展 未来の未来」の会場構成は、第一に、コンテクスチャリズムではない。第1会場において展示台は内部と外部の分け隔てなく散在されており、外に据えられた石も段差もまるで存在しないかのようだ。第2会場では展示台がグリッド状に配置されているが、展示の仕方に変更はない。第二に、イデアリズムでもない。何かの理念の表現として作り込まれてはおらず、理念からの演繹のようにヒエラルキカルでもない。以上のように、周辺敷地から考え始めているようには見えないが、強い理念があるようにも見えないというのは展覧会の特徴であり、藤本建築の特徴である。
では、形態は何かのアルゴリズムによって生み出されたものなのか。あるいは判断を放棄し、ランダムに決定してしまったものなのだろうか。そのどちらでもないだろう。敷地を無視した単純なアイデアのようで、作り込んでいるのが、実際の藤本建築である。「藤本壮介展 未来の未来」では、近いアイデアのプロジェクトが近傍に配置されていた。アイデアは複合し、交差しているものだから、明確にはセクション分けできない。これとこれとは確かに続いているのだけど、どこまでがひとくくりと言われると困る。「困難は分割せよ」と説くデカルトに「いやいや、その分割が困難なんですよ」とぐずりたくなる気分に対して、形を与えている。
100あまりの模型の一つ一つに、短い説明文がテプラのような素材でチープに貼られている。その言葉は図録からの抜粋ではなかった。したがって、模型そのものとフィットして自然に感じられる。機械的な作業の結果というものは、すぐにそれと気づくものだ。1995年以降のインフォメーションテクノロジーの進展によって人材と商材のロジスティクスが飛躍的に向上し、寡占化が進む世の中で、私たちはいっそうそのことに敏感になってしまった。それ以上であるからお金が取れるビジネスに匹敵する心地よさが、藤本壮介の展覧会場にはあった。手作業で調整しているがゆえである。何気ないような展示台の高さや配置も、粘って最後まで微妙に動かしているから、人々が行動できる空間がワンアイデアで自然に成立したように見えている。一見、システマティックに思えて、背後に人間くさい作り込みが横たわっている。藤本壮介の建築を訪れた時の体験も、そのようなものだ。暑苦しくないのが今風である。
このような作り込みに接すると、単純なアイデアが載ったように見える模型も、実際に建てるプロセスにおいて周辺環境に適した落とし込みがなされ、単に模型を大きくしたようなものにならないことが想像できる。

第一会場の展示 © Nacása & Partners Inc.
藤本壮介の成功の裏には、彼の勤勉さがある。そんな結論に至りそうだ。それは事実ではある。1995年以降の世の中における評文の締めとして、適切でもあろう。筆者が「いい人」のように見えて「いいね!」を押される。もちろん、藤本壮介だって「いい人」だ。
しかし、そんな勤勉さだけで、ここまでの人々を虜にするはずはない。
第2会場の展示にはハッとさせられた。身の回りのさまざまなモノが建築に見立てられている。それは過去の建築に接続し、まだ見ぬ建築を示唆している。これらがきちんと建築に見えるのは、スケールが適切だからだ。横に置かれた人物像がすべてを決定している。ここには単純さを恐れず、日常の中からワンアイデアを正確に発見する藤本壮介の才能と、それを建築へと細やかに作り込んでいく勤勉さの双方が、その始まりの形として展示されている。この先が見たくなる「未来の種」と言って良い。それは子どもにも分かる。一般人にも好評を博す。インターナショナルで、理屈を要さない。
藤本壮介の最大の素質は、私たちの希望や期待を吸収する能力にあるだろう。実現したものを見てみたい、自分が建てさせたい、この場所を変えてくれそうだ、できたらあんな行動をしてみたい、形にはこんな意味が読み取れるのではないだろうか・・そんな希望や期待の中で、建築は建ってきた。古代も中世も、様式主義にしてもモダニズムにしても、それは変わらない。藤本壮介は、歴史的に変わらない何かの理念や形を想定するのではなく、建築が時間と人の流動の中にあるという不変の事実を駆使して設計している。「未来の種」は、育みたくなる。建築家はそうやって依頼され、助けられ、希望されるプロジェクトの一員だ。展覧会場に並べられた提案は、希望や期待の吸収率が高いようにできている。実作は作り込みの確かさによって、まだ見ぬ行動と読みを誘う。そして、建築が時間と人の流動の中にあるという事実を認めてしまえば、その実現性において、個人の性格や体躯を考慮に入れざるを得なくなる。
しかし、そんな勤勉さだけで、ここまでの人々を虜にするはずはない。
第2会場の展示にはハッとさせられた。身の回りのさまざまなモノが建築に見立てられている。それは過去の建築に接続し、まだ見ぬ建築を示唆している。これらがきちんと建築に見えるのは、スケールが適切だからだ。横に置かれた人物像がすべてを決定している。ここには単純さを恐れず、日常の中からワンアイデアを正確に発見する藤本壮介の才能と、それを建築へと細やかに作り込んでいく勤勉さの双方が、その始まりの形として展示されている。この先が見たくなる「未来の種」と言って良い。それは子どもにも分かる。一般人にも好評を博す。インターナショナルで、理屈を要さない。
藤本壮介の最大の素質は、私たちの希望や期待を吸収する能力にあるだろう。実現したものを見てみたい、自分が建てさせたい、この場所を変えてくれそうだ、できたらあんな行動をしてみたい、形にはこんな意味が読み取れるのではないだろうか・・そんな希望や期待の中で、建築は建ってきた。古代も中世も、様式主義にしてもモダニズムにしても、それは変わらない。藤本壮介は、歴史的に変わらない何かの理念や形を想定するのではなく、建築が時間と人の流動の中にあるという不変の事実を駆使して設計している。「未来の種」は、育みたくなる。建築家はそうやって依頼され、助けられ、希望されるプロジェクトの一員だ。展覧会場に並べられた提案は、希望や期待の吸収率が高いようにできている。実作は作り込みの確かさによって、まだ見ぬ行動と読みを誘う。そして、建築が時間と人の流動の中にあるという事実を認めてしまえば、その実現性において、個人の性格や体躯を考慮に入れざるを得なくなる。

第二会場 © Nacása & Partners Inc.
「未来」が希少材になった1995年以降の日本に降り立った単独者が、人びとの希望や期待を吸収して大きくなっていく様子が「藤本壮介展 未来の未来」において印象的だった。藤本壮介にとっては、その形にしても、建築家としてのスタイルにおいても、このやり方には限界がないだろう。それ以外の人間にとっては、冒頭に触れた「これ以上単純にならない」手法と、その手法が社会に対して効果的に働くか否かが依拠している属人性が、同路線での展開を困難にするだろうけれど。
倉方俊輔/Shunsuke Kurakata
1971年東京生まれ。大阪市立大学大学院工学研究科准教授。早稲田大学大学院博士課程満期退学。伊東忠太の研究で博士号を取得後、著書に『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(2005)、『ドコノモン』(2011)。共著に『東京建築ガイドマップ』(2007)、『建築家の読書術』(2010)、『東京建築みる・あるく・かたる』(2012)、『大阪建築みる・あるく・かたる』(2014)。監修・解説書に『伊東忠太建築資料集』(2013-14)などがある。2015年から日本建築設計学会(ADAN)会誌『建築設計』編集長を務める。
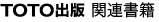
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。