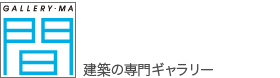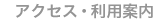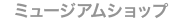- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

講演会レポート
乾久美子ライブ
レポーター=富井雄太郎
正直言って、意外だった。今、講演会場をあとにし、日付も変わらぬうちにこれを書いている。
少し戸惑っている。というのは、このレポートの依頼をいただく前から藝大建築科の教育研究助手として、本展覧会の経緯などをよく知っていたつもりだったし、講演会を聞く前から内容を想像し、こういうことを書こうとおぼろげにイメージしていたものがあったからだ。しかし、それは裏切られた。
正直言って、意外だった。今、講演会場をあとにし、日付も変わらぬうちにこれを書いている。
少し戸惑っている。というのは、このレポートの依頼をいただく前から藝大建築科の教育研究助手として、本展覧会の経緯などをよく知っていたつもりだったし、講演会を聞く前から内容を想像し、こういうことを書こうとおぼろげにイメージしていたものがあったからだ。しかし、それは裏切られた。

講演が展覧会と大きく違った点がふたつある。ひとつは、建築家・乾久美子という個人が前面に出ていたことだ。最初のスライドは、自ら住まうマンションの管理人であるナミキさんとその仕事の紹介だった。そのナミキさんのおかげで、共用廊下は常に掃除が行き届き、庭もきれいに整えられ、快適に日々を過ごすことができるそうだ。それらのプライベートな話や写真は、もちろん展覧会には出されていないし、大学の講評会で披露されていた途中経過(*)にもなかった。また、終盤では自身の設計した建築や、今設計中のプロジェクトが紹介され、これも展覧会とは違っていた(建築家の講演で自作の紹介は普通のことであり、その意味では展覧会の内容が異色であると言える)。つまり、集団制作であった展覧会や書籍とは異なり、乾久美子の現在が示された講演会だった。
もうひとつの違い、これが戸惑いの理由だが、展覧会と書籍の内容=「学び」を設計の方へ結び付けようとしていたことだ。
冒頭に書いた、おぼろげにイメージしていたものとは、今回の「学び」における「回避」についてであった。
まず「小さな風景からの学び」は、ヒロイックな、単一の概念の提出が慎重に避けられている。176もの「ユニット」には「照明いらず」、「何かに沿ってのびる」など、直感で把握できる一般的な語彙が用いられ、全体についても「サービス」という広く解釈可能な言葉が見出されている。
また、採寸や図面化がされなかったことも特徴である。コード化され、設計に「引用」された瞬間に「質」や「味わい」が失われ、陳腐化することを知っていたからだろう。先行のリサーチやフィールドワークへの批評性、風景や人びとの営みへの敬意をもち、その成果の安易な活用を避けていたのだ。現段階では、今後の長きに渡る研究室の活動として探求を続けていくための動的な枠組みであると宣言されていたし、本の中でも「どうつくるか」のためではなく、「何をつくるか」や「なぜつくるのか」という哲学的な問いが示されていた。
もうひとつの違い、これが戸惑いの理由だが、展覧会と書籍の内容=「学び」を設計の方へ結び付けようとしていたことだ。
冒頭に書いた、おぼろげにイメージしていたものとは、今回の「学び」における「回避」についてであった。
まず「小さな風景からの学び」は、ヒロイックな、単一の概念の提出が慎重に避けられている。176もの「ユニット」には「照明いらず」、「何かに沿ってのびる」など、直感で把握できる一般的な語彙が用いられ、全体についても「サービス」という広く解釈可能な言葉が見出されている。
また、採寸や図面化がされなかったことも特徴である。コード化され、設計に「引用」された瞬間に「質」や「味わい」が失われ、陳腐化することを知っていたからだろう。先行のリサーチやフィールドワークへの批評性、風景や人びとの営みへの敬意をもち、その成果の安易な活用を避けていたのだ。現段階では、今後の長きに渡る研究室の活動として探求を続けていくための動的な枠組みであると宣言されていたし、本の中でも「どうつくるか」のためではなく、「何をつくるか」や「なぜつくるのか」という哲学的な問いが示されていた。

ところが、今回の講演会では終盤から自身の設計とつなげた話が始まったのである。「アパートメントI」や「スモールハウスH」や「KYOAI COMMONS」は、かつて実見する機会があったが、今回のリサーチとのつながりについてはあとづけのような強引さや違和感があった。
ただ、もう少し想像を進めてみれば、やはりリサーチのためのリサーチであるはずはなく、展覧会と書籍をまとめた後の講演会では、疑いや迷いの中にありながらも、勇気を持って新たな一歩を踏み出してみた、というのが実際なのではないか。特に進行中のプロジェクトについては、たくさんの設計の試行錯誤や進退を見せながら、自らの言葉でその方向性やプロセスを再確認し、会場にいたであろう事務所のスタッフとそれらを共有しようとしていたからだ。乾さんは何でもすぐにやってみる具体性の人であり、いつでも真摯な行き当たりばったりの人である。現在進行形のライブ感があり、何よりもその思考の逡巡と切迫感、そして創造の最中にあることが強く印象に残り、刺激的だった。
今後のプロジェクトに、誰にも気づかれないほど自然な形で未知なる「質」が現れるのが楽しみだ。「延岡駅周辺整備プロジェクト」のパースはカッコイイので、もっといい意味でのダサさが醸成されると良いなあと思ったし、釜石市唐丹地区の小中学校は、昨今の資材高騰から予算と土地整備と建築それぞれの条件のせめぎ合いと、繰り返される設計変更の様子が重苦しく語られていたが、スケッチに示されていたような室外機や擁壁との関係すら肯定的に取り入れた明るさで突き抜けてほしい。「小さな風景からの学び」を味方にできれば、これほど力強いものはないだろう。最後に、書きながら思い起こしていた音楽家の言葉を引いてこのレポートを終えたい。
「いつでも知られざるものの淵にいて、跳躍の準備をしておくこと。そしていざ向こうへ行こうというときには、準備にかけた歳月、感受性、準備した手段がすべて手元にあり、あとは知られざるものへひと跳びするだけです。」(スティーブ・レイシー)
(出典:デレク・ベイリー『インプロヴィゼーション―即興演奏の彼方へ』、竹田賢一・斉藤栄一・木幡和枝 訳、工作舎、1981年)
*東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻「建築設計Ⅰ」講評会(2013年7月18日)
同「建築設計Ⅱ」講評会(2013年12月11日)
ただ、もう少し想像を進めてみれば、やはりリサーチのためのリサーチであるはずはなく、展覧会と書籍をまとめた後の講演会では、疑いや迷いの中にありながらも、勇気を持って新たな一歩を踏み出してみた、というのが実際なのではないか。特に進行中のプロジェクトについては、たくさんの設計の試行錯誤や進退を見せながら、自らの言葉でその方向性やプロセスを再確認し、会場にいたであろう事務所のスタッフとそれらを共有しようとしていたからだ。乾さんは何でもすぐにやってみる具体性の人であり、いつでも真摯な行き当たりばったりの人である。現在進行形のライブ感があり、何よりもその思考の逡巡と切迫感、そして創造の最中にあることが強く印象に残り、刺激的だった。
今後のプロジェクトに、誰にも気づかれないほど自然な形で未知なる「質」が現れるのが楽しみだ。「延岡駅周辺整備プロジェクト」のパースはカッコイイので、もっといい意味でのダサさが醸成されると良いなあと思ったし、釜石市唐丹地区の小中学校は、昨今の資材高騰から予算と土地整備と建築それぞれの条件のせめぎ合いと、繰り返される設計変更の様子が重苦しく語られていたが、スケッチに示されていたような室外機や擁壁との関係すら肯定的に取り入れた明るさで突き抜けてほしい。「小さな風景からの学び」を味方にできれば、これほど力強いものはないだろう。最後に、書きながら思い起こしていた音楽家の言葉を引いてこのレポートを終えたい。
「いつでも知られざるものの淵にいて、跳躍の準備をしておくこと。そしていざ向こうへ行こうというときには、準備にかけた歳月、感受性、準備した手段がすべて手元にあり、あとは知られざるものへひと跳びするだけです。」(スティーブ・レイシー)
(出典:デレク・ベイリー『インプロヴィゼーション―即興演奏の彼方へ』、竹田賢一・斉藤栄一・木幡和枝 訳、工作舎、1981年)
*東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻「建築設計Ⅰ」講評会(2013年7月18日)
同「建築設計Ⅱ」講評会(2013年12月11日)
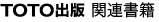
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。