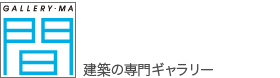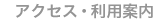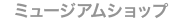- 展覧会TOTOギャラリー・間
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- 開催中の展覧会
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

展覧会レポート
小さな風景という相互連関の際立ち
レポーター=能作文徳
風景の対象化・カテゴリー化
本展覧会「小さな風景からの学び」では2,000を超える風景の写真が一堂に展示されている。「風景」という言葉は包括的な概念である。たとえば絶景と呼ばれる美しい自然環境、都会の風景というようなビルで囲まれた人工物による環境、室内風景とよばれる内部空間はひとくくりに「風景」と呼ばれている。風景はゲシュタルト心理学の「図と地」からすれば、「地」の部分、つまり背景となる部分を指す言葉であるため、風景そのものは対象化しにくい。本展では、風景を写真によってフレームを限定し、正対して撮影することによって物事を対象化する方法が採用されている。そのことで漠然と広がる風景を「小さな」風景へと分割して対象化し、「地」であった風景を「図」とする視点を獲得することができたと考えられる。
まず「小さな風景」の分類作業について着目したい。植物学者カール・フォン・リンネは地球上の植物を分類する際に、果実の形状をもとにして属(生物分類における基本的階級)を決定したそうである。研究者によるとそれは、「結実器官から選び出された特性は明瞭で、識別が容易で、言葉による記述も簡単である」ためで、「植物学者はすべての属を知り、かつ覚えていることが要求される」ためだそうである。つまり多種多様な植物を分類するためには、知覚のしやすさ、記憶のしやすさが、よりどころとなっていたのである。このリンネの分類は、科学的というよりも、民族学的な分類と類似していた。このように自然界を理解するのと同様に私たちは知覚や記憶といった認知のしやすさによる分類から、現実の世界を理解しようとしている。さらにいえば、私たちはただ漠然と見ることによってではなく、分類することによって世界を把握しているのである。
また人類学者ブレント・バーリンによれば、ある民族は、ある植物を呼ぶときに、生活で使用されるレベルの「木」を使うことはなく、「ナラ」や「カエデ」といった属のレベルでの名称を優先させる傾向があると述べられている。こうした事実はその民族の文化にとっては、属(カエデ)のレベルが最も実用的であるからこそ、その言葉が優先されたことを示している。カエデについて次のように上位から下位の順(包括的から個別的の順)の階層構造で示すと、植物>木>落葉樹>カエデ>サトウカエデとなるが、文化によってどの階層を使用するかは、そのなかでの実用に関わっているのである。都会の文化であれば、「木」という言葉だけで事足りたのかもしれない。このように植物だけでなく世界のものごとをどのようなレベルで意思伝達を行なっていくかに差異があるわけだが、一般的に、上位のレベル(包括的な集合)と下位のレベル(個別的な集合)の中間的なレベルが用いられる傾向があることが分かっている。なぜなら上位のレベルでは物事を特定しにくく、下位のレベルでは詳細な違いを問題にしていては労力がかかりすぎるのである。つまり意思伝達するために実用的で効率のいい集合が選ばれるという経済性の原理が働いているのである。より詳細に伝達が必要であればより下位のカテゴリーの優先度が高まっていく。
本展覧会で集められている小さな風景は、176のユニットと呼ばれる小分類、22のグループと呼ばれる大分類によって整理されている。どれもたいへんユニークなネーミングで風景の特徴を言い当てている。先に述べたように、風景とは包括的な上位のカテゴリーである。図と地の「地」の部分であるため、曖昧な状態そのものとして理解するしかなかった。この展覧会の意義は、風景という上位カテゴリーからより個別的な下位カテゴリーへと認識のレベルを活性化することにある。つまり風景>グループ>ユニットといった下位カテゴリーへと、風景の個別的で具体的な認識を与えてくれる。カテゴリー化という方法によって漠然とした認識しかもちえなかった風景という概念に対して、より詳細に具体的に見るための視点を与えてくれるのである。
風景の対象化・カテゴリー化
本展覧会「小さな風景からの学び」では2,000を超える風景の写真が一堂に展示されている。「風景」という言葉は包括的な概念である。たとえば絶景と呼ばれる美しい自然環境、都会の風景というようなビルで囲まれた人工物による環境、室内風景とよばれる内部空間はひとくくりに「風景」と呼ばれている。風景はゲシュタルト心理学の「図と地」からすれば、「地」の部分、つまり背景となる部分を指す言葉であるため、風景そのものは対象化しにくい。本展では、風景を写真によってフレームを限定し、正対して撮影することによって物事を対象化する方法が採用されている。そのことで漠然と広がる風景を「小さな」風景へと分割して対象化し、「地」であった風景を「図」とする視点を獲得することができたと考えられる。
まず「小さな風景」の分類作業について着目したい。植物学者カール・フォン・リンネは地球上の植物を分類する際に、果実の形状をもとにして属(生物分類における基本的階級)を決定したそうである。研究者によるとそれは、「結実器官から選び出された特性は明瞭で、識別が容易で、言葉による記述も簡単である」ためで、「植物学者はすべての属を知り、かつ覚えていることが要求される」ためだそうである。つまり多種多様な植物を分類するためには、知覚のしやすさ、記憶のしやすさが、よりどころとなっていたのである。このリンネの分類は、科学的というよりも、民族学的な分類と類似していた。このように自然界を理解するのと同様に私たちは知覚や記憶といった認知のしやすさによる分類から、現実の世界を理解しようとしている。さらにいえば、私たちはただ漠然と見ることによってではなく、分類することによって世界を把握しているのである。
また人類学者ブレント・バーリンによれば、ある民族は、ある植物を呼ぶときに、生活で使用されるレベルの「木」を使うことはなく、「ナラ」や「カエデ」といった属のレベルでの名称を優先させる傾向があると述べられている。こうした事実はその民族の文化にとっては、属(カエデ)のレベルが最も実用的であるからこそ、その言葉が優先されたことを示している。カエデについて次のように上位から下位の順(包括的から個別的の順)の階層構造で示すと、植物>木>落葉樹>カエデ>サトウカエデとなるが、文化によってどの階層を使用するかは、そのなかでの実用に関わっているのである。都会の文化であれば、「木」という言葉だけで事足りたのかもしれない。このように植物だけでなく世界のものごとをどのようなレベルで意思伝達を行なっていくかに差異があるわけだが、一般的に、上位のレベル(包括的な集合)と下位のレベル(個別的な集合)の中間的なレベルが用いられる傾向があることが分かっている。なぜなら上位のレベルでは物事を特定しにくく、下位のレベルでは詳細な違いを問題にしていては労力がかかりすぎるのである。つまり意思伝達するために実用的で効率のいい集合が選ばれるという経済性の原理が働いているのである。より詳細に伝達が必要であればより下位のカテゴリーの優先度が高まっていく。
本展覧会で集められている小さな風景は、176のユニットと呼ばれる小分類、22のグループと呼ばれる大分類によって整理されている。どれもたいへんユニークなネーミングで風景の特徴を言い当てている。先に述べたように、風景とは包括的な上位のカテゴリーである。図と地の「地」の部分であるため、曖昧な状態そのものとして理解するしかなかった。この展覧会の意義は、風景という上位カテゴリーからより個別的な下位カテゴリーへと認識のレベルを活性化することにある。つまり風景>グループ>ユニットといった下位カテゴリーへと、風景の個別的で具体的な認識を与えてくれる。カテゴリー化という方法によって漠然とした認識しかもちえなかった風景という概念に対して、より詳細に具体的に見るための視点を与えてくれるのである。

(左:第一会場全景 右:展示の見方とユニット名を表示したパネル)© Nacása & Partners Inc.
小さな風景に内在する身体・かたち・相互連関
以上では展覧会の方法について述べた。次に小さな風景の対象について読み解いていきたい。展覧会で集められた写真は、夕日や富士山といったいわゆる自然の美しさを撮ったものではない。どれも自然と人工物の混在が生み出した身近な風景ばかりである。またお金をかけてつくられたものではなく、安価なものやその場にあったものの組み合わせによって、絶妙な関係に置かれたブリコラージュ的(※)なものが多い。整然と並んだビールケース、田んぼのなかにあるカラフルな小屋、絶妙な距離に置かれたベンチ、所狭しと溢れる植栽など、どれもどこかでみたような日常的な風景であり、人の気配で充満している。写真を巡っていくと、どの風景も身体と環境との相互作用のなかで獲得されたものであることに気づく。風景とは包括的であるがために認識されにくいものであった。しかしこの写真の対象を、人間のふるまい、あるいはふるまいの痕跡を中心に据えることによって、風景は単なる漠然とした自然環境ではなく、身体性が内蔵されたものとして知覚されることになる。わたしたちは空間や風景と呼ばれる漠然とした広がりの全体を容易に理解することはできない。そのため全体は知覚しやすい部分から理解されることになる。その理解の起点となる部分が身体である。最も単純な事例は「とりあえず椅子」「とりあえずベンチ」といったユニットである。これらは座る場所のある風景である。椅子は人間を一定の姿勢で定位させる治具である。人間にはお尻があり、背中があり、目があるという身体的特徴が椅子に刻まれている。そのため椅子が置かれていることで風景のなかに知覚の向きがセットされる。たとえば、店先のベンチ、駅のプラットフォームのベンチといった典型的な風景では、そのセッティングを見ただけで、身体の向きやリラックスの度合い、そこでの社会性までもが、日常的な場面として自然と想起される。しかしセッティングが意外であるような例、たとえば外階段の途中、あるいは人の流れが絶え間ない交差点のコーナーなどに置かれた椅子などは、日常で繰り返し体験しているような場面のイメージからずれることにより、日常的なふるまいの見直しが促される。こうした移動と滞留との対立をうまく示したのが「ゆたかな廊下」である。さらに内外の境界の想定を超える使い方を示したのが「内のように外を使う」「外のように内を使う」である。これらは座るという行為だけでなく、本来、内部空間にある物が外部空間にあることで内側の感覚を生み出したり、外部空間にある物が内部空間にあることで外側の感覚を生み出している。これらの風景は私たちの身体が起点となって風景の知覚を可能にする。つまり「小さな風景」には、部分からより大きな全体へ認識を拡張するメトニミー的構造がある。
こうした身体が起点となる風景のほかに、物の配列や状態といった広義の「かたち」に着目したユニットがある。たとえば「ズッコケ三人組」「距離のあるカップル」「双子」「三つ子」「親子」「ファミリー」では、小屋や物置、電話ボックス、ポスト、自動販売機など一見すると何でもない配置に、形象を見いだす事例である。これらは、物自体の機能や意味とは別の「かたち」の次元で、異なる種類の物どうしが結びつけられている事例である。そして配列関係が、友人や家族をあらわす擬人化したネーミングになっているところがおもしろい。人工物がまるで生命をもったものとして記述されることで、人工物のなかにも生命的な構造が転写されていることを示唆しているようである。「平べったい」「やせている」「縞々」「玉散らし」「斜めのスパイス」「さけるチーズ」は、対象物のスケールやかたちが一般的な状態から逸脱しているために、本来の機能よりもそのかたちのほうに目がいってしまう事例である。普段、私たちは物事をかたちとしてではなく記号的に捉えている。石を見て「石」だと認識するだけで済ませている。その石がどんなかたちなのか、いちいち認識することはない(かたちに敏感なデザイナーなどは別だと思うが)。つまり私たちの認識はある程度自動化されているのである。石をはじめて見た人がいたならば、それがどんなかたちをしてどんな性質なのか、安全なのか危険なのか、食べられるのか食べられないのか、そういう物の性質に対して詳細な認識が立ち上がってくるだろう。しかし私たちはいつも世界を新しいものとして認識していては過剰なストレスで疲れきってしまうだろう。だから石は石として、つまり記号として受け取ることでスムーズに世界を知覚しているのである。風景も同様に、あまりに日常的であるために見過ごされやすいが、まじまじとみるとそのかたちの異様さに驚かされる。このようなかたちを捉えた小さな風景のユニットは、自動化した記号的な認識から、物のかたちや状態から認識する手がかりを与えてくれる。言い換えると、はじめて物事に出会ったような瑞々しい詩的感覚を与えてくれるのである。
※ブリコラージュ:寄せ集めて自分で作ること
以上では展覧会の方法について述べた。次に小さな風景の対象について読み解いていきたい。展覧会で集められた写真は、夕日や富士山といったいわゆる自然の美しさを撮ったものではない。どれも自然と人工物の混在が生み出した身近な風景ばかりである。またお金をかけてつくられたものではなく、安価なものやその場にあったものの組み合わせによって、絶妙な関係に置かれたブリコラージュ的(※)なものが多い。整然と並んだビールケース、田んぼのなかにあるカラフルな小屋、絶妙な距離に置かれたベンチ、所狭しと溢れる植栽など、どれもどこかでみたような日常的な風景であり、人の気配で充満している。写真を巡っていくと、どの風景も身体と環境との相互作用のなかで獲得されたものであることに気づく。風景とは包括的であるがために認識されにくいものであった。しかしこの写真の対象を、人間のふるまい、あるいはふるまいの痕跡を中心に据えることによって、風景は単なる漠然とした自然環境ではなく、身体性が内蔵されたものとして知覚されることになる。わたしたちは空間や風景と呼ばれる漠然とした広がりの全体を容易に理解することはできない。そのため全体は知覚しやすい部分から理解されることになる。その理解の起点となる部分が身体である。最も単純な事例は「とりあえず椅子」「とりあえずベンチ」といったユニットである。これらは座る場所のある風景である。椅子は人間を一定の姿勢で定位させる治具である。人間にはお尻があり、背中があり、目があるという身体的特徴が椅子に刻まれている。そのため椅子が置かれていることで風景のなかに知覚の向きがセットされる。たとえば、店先のベンチ、駅のプラットフォームのベンチといった典型的な風景では、そのセッティングを見ただけで、身体の向きやリラックスの度合い、そこでの社会性までもが、日常的な場面として自然と想起される。しかしセッティングが意外であるような例、たとえば外階段の途中、あるいは人の流れが絶え間ない交差点のコーナーなどに置かれた椅子などは、日常で繰り返し体験しているような場面のイメージからずれることにより、日常的なふるまいの見直しが促される。こうした移動と滞留との対立をうまく示したのが「ゆたかな廊下」である。さらに内外の境界の想定を超える使い方を示したのが「内のように外を使う」「外のように内を使う」である。これらは座るという行為だけでなく、本来、内部空間にある物が外部空間にあることで内側の感覚を生み出したり、外部空間にある物が内部空間にあることで外側の感覚を生み出している。これらの風景は私たちの身体が起点となって風景の知覚を可能にする。つまり「小さな風景」には、部分からより大きな全体へ認識を拡張するメトニミー的構造がある。
こうした身体が起点となる風景のほかに、物の配列や状態といった広義の「かたち」に着目したユニットがある。たとえば「ズッコケ三人組」「距離のあるカップル」「双子」「三つ子」「親子」「ファミリー」では、小屋や物置、電話ボックス、ポスト、自動販売機など一見すると何でもない配置に、形象を見いだす事例である。これらは、物自体の機能や意味とは別の「かたち」の次元で、異なる種類の物どうしが結びつけられている事例である。そして配列関係が、友人や家族をあらわす擬人化したネーミングになっているところがおもしろい。人工物がまるで生命をもったものとして記述されることで、人工物のなかにも生命的な構造が転写されていることを示唆しているようである。「平べったい」「やせている」「縞々」「玉散らし」「斜めのスパイス」「さけるチーズ」は、対象物のスケールやかたちが一般的な状態から逸脱しているために、本来の機能よりもそのかたちのほうに目がいってしまう事例である。普段、私たちは物事をかたちとしてではなく記号的に捉えている。石を見て「石」だと認識するだけで済ませている。その石がどんなかたちなのか、いちいち認識することはない(かたちに敏感なデザイナーなどは別だと思うが)。つまり私たちの認識はある程度自動化されているのである。石をはじめて見た人がいたならば、それがどんなかたちをしてどんな性質なのか、安全なのか危険なのか、食べられるのか食べられないのか、そういう物の性質に対して詳細な認識が立ち上がってくるだろう。しかし私たちはいつも世界を新しいものとして認識していては過剰なストレスで疲れきってしまうだろう。だから石は石として、つまり記号として受け取ることでスムーズに世界を知覚しているのである。風景も同様に、あまりに日常的であるために見過ごされやすいが、まじまじとみるとそのかたちの異様さに驚かされる。このようなかたちを捉えた小さな風景のユニットは、自動化した記号的な認識から、物のかたちや状態から認識する手がかりを与えてくれる。言い換えると、はじめて物事に出会ったような瑞々しい詩的感覚を与えてくれるのである。
※ブリコラージュ:寄せ集めて自分で作ること

(第二会場全景)© Nacása & Partners Inc.
これらの他に、自然と人間(あるいは人工物)の相互連関に着目したユニットがみられる。「照明いらず」は、大きなガラスの窓から自然光が入り、床に反射し、部屋全体が柔らかい光に満たされる風景である。室内には蛍光灯が設置されているにもかかわらず、照明をつけずに人々は過ごしており、ゆっくりと時間がながれているように感じられる。「影が呼ぶ」は、木陰に呼び寄せられた家具、人、牛、自動車、物置に着目した風景である。夏の暑い時期には涼しい場所に様々なものが集まってくる。それは人だけではない。自動車も車内の温度が上昇しないように影の下に駐車される。動かない物置であっても中の温度が上がらないようにするためか、木陰の隠れた場所が好まれるためか、影の下に集められている。これらは光や影といった太陽からのリアクションによって物事が定着される事例であり、太陽ともの・人との相互連関が示されている。「不陸のない地面」は、地面が固くフラットに整備されていることにより、フリーマーケットや市場などが発生する事例である。その他の「占める」「ところせまし」なども物や人による空間の占拠は固い地面という支えがあって成立することに着目したもので、地面ともの・人との相互連関があらわれている。「机のある風景」も固くて広い地面と同様な現象が、スケールをかえて机の天板の支えとしてあらわれたと捉えることができる。これらの相互連関の風景はすべてを計画することからは決して生まれてこない。環境を知覚し適応するプロセスを経ることであらわれたものである。これらは閉鎖系の構造ではなく開放系の構造をもっている。開放系の構造とは常時一定の入力がありながら、ある構造を保っている状態である。ここでいう入力とは、自然・もの・人が出たり入ったりを繰り返す持続的な実践のあり方のことである。こうした一定の入力が持続することにより相互連関の構造があらわれてくるのである。このような構造を科学者イリヤ・プリゴジンは「散逸構造」と呼んだ。

(中庭から会場を見る)© Nacása & Partners Inc.
このように「小さな風景」は、身体を起点としたメトニミー的構造をもつもの、記号から形象へと詩的感覚を与えてくれるもの、自然・もの・人の相互連関をもつものであることを述べた。風景という漠然とした広がりのなかに、身体やかたちを起点とした認識によって、あるいは自然・もの・人の相互連関によって際立った部分ができる。その際立ちが「小さな風景」なのである。
能作 文徳 Fuminori Nousaku
建築家 東京工業大学助教 博士(工学)
1982年富山県生まれ、2005年東京工業大学建築学科卒業、2007年東京工業大学建築学専攻修士課程修了、2010年能作文徳建築設計事務所設立、2012年東京工業大学建築学専攻博士課程修了
主な作品
ホールのある住宅、Steel House、高岡のゲストハウス
受賞
2010年東京建築士会住宅建築賞、
2013年SDレビュー2013鹿島賞
主な著書
WindowScape 窓のふるまい学(共著)
2010年 フィルムアート社
WindowScape2 窓と街並の系譜学(共著)
2014年 フィルムアート社
コモナリティーズ ふるまいの生産(共著)
2014年 LIXIL出版
1982年富山県生まれ、2005年東京工業大学建築学科卒業、2007年東京工業大学建築学専攻修士課程修了、2010年能作文徳建築設計事務所設立、2012年東京工業大学建築学専攻博士課程修了
主な作品
ホールのある住宅、Steel House、高岡のゲストハウス
受賞
2010年東京建築士会住宅建築賞、
2013年SDレビュー2013鹿島賞
主な著書
WindowScape 窓のふるまい学(共著)
2010年 フィルムアート社
WindowScape2 窓と街並の系譜学(共著)
2014年 フィルムアート社
コモナリティーズ ふるまいの生産(共著)
2014年 LIXIL出版
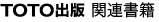
Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。