| 展覧会レポート |
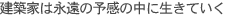 |
| レポーター:藤本壮介 |
| |
会場に入ったとき、ちょっと意外な気がした。
メディアの中での隈さんは、スタイリッシュで、洗練され、知的な建築家として映っている。しかしこの展覧会場の雰囲気は、もっとリラックスして、隈さんの素の部分が現れているかのようだ。
3F展示室いっぱいに、さまざまなプロジェクトのさまざまな段階のスタディ模型が並べられている。その向こうのテラスには、「ウォーター・ブランチ」の実物がある。「ウォーター・ブランチ」のおもちゃの家のような愛嬌ゆえか、これらのスタディ模型たちのおもちゃ箱をひっくり返したような楽しさに、共感のようなものが湧いてくる。
僕は自分の子供時代のことを思い出した。
幼稚園から小学生時代の僕は、小石や、どこかで拾った何かの部品や、たまたま家に落ちていた用途不明の小物、木々の面白い断片、パイプの切れ端、などなどのたくさんのものを集めるのが好きだった。集めて、何をするわけではないのだけれど、そのうちこれらのもので何かを作りたいなあと思ってとにかくいろいろ集めるのが好きだったのだ。それらの品々は、現実的な意味では何かを作る役には立たないものたちなのだが、それゆえに、そこには、圧倒的な「予感」が満ち溢れていた。意味をはぎ取られているゆえに、何ものでもないゆえに、それらのものたちは、無限の想像力を受け止めてくれた。子供は予感の中に生きているのである。それゆえに未来に対してひたすらに楽観的でいられたのかもしれない。
隈さんの模型たちを見ていて、そんな子供時代の「予感」を思い出していた。
もちろんこれらの模型たちは、それぞれ具体的なプロジェクトのさまざまな段階でのまじめなスタディ模型である。個々の模型を眺めていくと、それらはインスピレーションを形にしたという以上に、よく考えられて作られているのが分かる。用途も明確だし、僕が集めていた無意味な品々とはもちろん次元が違う。それでもそこには、開放的な気分にさせてくれる何かがある。なぜだろう。思うに、これらの模型は確かにあるプロジェクトのファサードだったり、屋根だったり、全体の配置だったりを考える中から作られたものに違いないが、しかしその思考の根底に、検討するだけのための模型を超えて、その断片が、その紙の一辺が、突然まだ見ぬ別の建築にジャンプしていくことを期待し、予感している視線があるからではないだろうか。それゆえに、これらの模型たちは、現実的でありながら、常にアイデアの最初の瞬間のようなみずみずしさを備えている。どんな断片にも、何かに変化していく可能性が秘められている。そんな隈さんの好奇心がそのまま展示されているのである。
もちろん好奇心や予感からだけでは、建築は作れない。その点、隈さんとチーム隈は、恐ろしいくらいに強力な組織に変貌しているようだ。まるで、昆虫採集が好きな少年が、好きが高じてTシャツ短パンのまま遺伝子操作を平気でやってのけ、世界にいない自分たちだけの昆虫を作り上げていくかのように。4階の展示室に鎮座する「グラナダ・パフォーミングアーツ・センター」と「ブザンソン芸術文化センター」の巨大模型を見て、思わずそんな風景を想像してしまった。
11月上旬にバルセロナでたまたま隈さんのレクチャーを聴くことができたのだが、その講演を聞きながら、その好奇心と予感とを、隈さんがどうやってドライブしているかが、少し分かった気がした。
レクチャーの前半は、今までの代表作を、浮世絵や間などの日本文化を並置しながら精緻に解説していく。そのパートの隈さんは、知的な文化の伝道者としての建築家である。
一転して後半には、展覧会などで制作してきた小さな茶室やパヴィリオンたちの紹介に当てられた。このパートに入って、隈さんの表情が俄然緩んでくる。説明の仕方も、個人的と言ってしまってもよいような「思い」や「面白さ」がベースになってくる。会場の雰囲気もそれに合わせて、隈さんの楽しみを共有して一喜一憂していく。空気で膨らむパビリオン(浮庵)、温度で形が変わるスペース(KXK)。そして、今回ギャラリー・間で作られた水で作る家(ウォーター・ブランチ)。
これこそが隈さんが建築に関わる本当の原点なのではないだろうか。
何か今までにないものを見てみたい。それが建築と言えるかどうかは分からないけれども、空間があり、人が関わり、場ができるようなものの作り方、現れ方を、思いつくままに試してみたい。そんな少年のような想いと好奇心とが始まりにはある。そうしてそれを素直に実現していこうとする中で、どうしても出てくる技術的な問題、素材の問題、そういう課題に対して、またもや子供のように素直に驚き、面白がり、そうしてそれらを次の予感に変えていく。講演会の後、聴衆の顔はなんだか楽しそうだった。自分たちも今晩、何か新しい茶室をひとつ考えてみようか、そんな雰囲気が共有されていた。隈さんの建物は、社会的にももちろん周到に考えられているとは思うが、その根底では、こういう共感力が大きな働きをしているのではないかと感じられた。文化も食事も歴史も異なる国々で、それでも何か共感されるもの。建築という巨大で公共的な存在が、人々にとって本当に意味のある瞬間とは、それはただ共感と予感だけだとも言えるのではないだろうか。
そうして再び今回の展覧会に合わせてTOTO出版から発行された作品集『スタディーズ・イン・オーガニック』を読み返してみた。前半の、整理され自分の歴史の中に位置づけられた作品群の解説に対して、後半部分は、解説や論理を超えて自らに言い聞かせるかのような「想い」である。いくつものまとまりきらないキーワードが提示され、その関係を模索しているかのようなリアルなテキストだ。ここでもまた、予感が提示されている。予感に形が与えられているのだ。
建築家は永遠の予感の中に生きていく。
|
|
 |
 |
|
©Nacása & Partners Inc. |
 |
|
©Nacása & Partners Inc. |
 |
|
©Nacása & Partners Inc. |
|