| アルヴァロ・シザ 特別インタビュー |
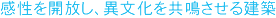 |
| インタビュアー 馬場正尊 |
 |
建築家 アルヴァロ・シザ氏が活動の拠点を構えているのはポルトガル北部の地方都市、ポルトである。人口30万人、街自体はローマ時代に基礎が築かれ、西ゴート、イスラム教の支配などさまざまな歴史のドラマを経てきた美しい街で、ユネスコの世界遺産にも指定されている。 シザ事務所はその郊外の住宅街のなかにあった。タクシーの運転手に住所を見せると「ああ、シザのところね」という顔で即座に走り出す。シザ氏がタクシーをよく使うらしく、運転手みんなが事務所の場所を知っているようなのだ。このポルトガル随一の国際的な建築家がいかにこの街に愛されているのか、その一端を伺わせるエピソードから取材は始まった。
いかにもシザ建築という白いマッシブなビルの前で車が止まる。わかりにくい小さなドアの横についた呼鈴を押すと、電気式の錠が開いた。中に入ると、低く抑えられた暗いアプローチの先に階段があり、そこにはポルトガルの強い日差しが落ちている。その濃いコントラストに一瞬眼がくらみ、早速、シザ氏特有の空間構成の洗礼を浴びた気分だ。
Openness and Echo/感性を開放し、異文化を共鳴させる
「Public and Private Architecture in Different Contexts」(直訳すると「異なる文脈のなかでの公と私の建築」)が、今回のギャラリー・間での展覧会タイトルである。そのなかには過去の作品もあれば進行中のプロジェクトも混ざっている。たくさんのシザ建築のなかで、なぜこれらが選ばれ、そこにどんなメッセージを込めようと思ったのか。そこからインタビューを始めてみた。
「現在、異なる文化の対話の機会が増えたことは、建築にとっても幸せなことです。建築は内発的に建築家の頭のなかから生まれるものではないと思っているからです。目や感性を開放すること(Openness)で文化や発想の触発が起こり(Impact of Meeting)、それらの共鳴(Echo)によって空間的な発明は生まれます。それを今回の展覧会で伝えてみたかったのです。
私は今、さまざまな土地で仕事をしています。それは創造的なことであり、建築家にとって幸せなことです。しかし、氾濫する情報に溺れるだけでは自分たちの文化を見失ってしまう。だからこそ私たちは、違和感を顕在化し、異文化を吸収することに対して、常に意識的でなければならないと思っています」
Beyond Materiality/物質性を超えて
今回の展示では、中庭で素材のインスタレーションが行われる。木、石、鉄、レンガで構成されたその空間では、シザ氏の素材に対する基本的なスタンスと感受性が率直に語られている。「Beyond Materiality」 という単語を氏は用いた。
「素材に物質性を超えた精神性のようなものを帯びさせたいと思っています。木、石、鉄、レンガ……、それら素材への感受性は重要で、建築はその使い方次第で多様な表情を見せるのです。この中庭を、それぞれの素材が呼応し合い、歌うような空間にしたいと思いました。
建築は基本的にシンプルな素材でできているものです。その土地ならではの素材を選択することもあれば、ある世界観を獲得するために異なった文脈から新しい素材を選択することも可能です。ただし外部から新しい素材を用いる時は必然性を検証し、気まぐれに用いるべきではないと考えています」
|
|
 |
 |
| ポルトの街並み。歴史地区は世界遺産にも登録されている。街の中央をドロウ川が切り裂くように流れ、その両岸は切り立った斜面。シザ氏は一貫してこの街に拠点を置き、仕事を続けている。 |
 |
 |
| アルヴァロ・シザ事務所。ポルト郊外、ドロウ川の河畔に建っている。小さな右側のドアが入口。ドアの向こうにはシザ建築らしい陰影の強いアプローチが姿を現す。 |
 |
 |
| インタビューの様子。静かだが情熱的に語りかける。 |
 |
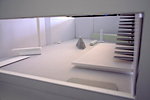 |
| 事務所内には、さまざまな模型が積まれている。ギャラリー・間の模型も発見。素材で構成された中庭の部分。 |
|