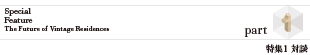
住宅を住宅として継承する
——「住宅遺産トラスト」の設立が象徴しているように、建築家の名作の継承が各所で注目されているわけですね。 安田さんも、林昌二と林雅子の自邸「私たちの家」(1955)を改修して継承し、自ら住まわれています。当事者でもある 安田さんは、名作住宅の継承をどのように感じていますか。
- 安田幸一 住宅を住宅として引き継ごうと思うと、一般的には困難も多いと感じています。この「私たちの家」や「園田高弘邸」もそうですが、モダニズムの名作といわれている住宅の多くが50年代につくられていて、そろそろ、構造や設備なども含めた物理的な寿命が突きつけられています。一般的に名作住宅の初代施主は、もちろんその住宅に対して非常に思い入れがあって、寿命がせまってきたとしても、なんとか保持していきたいと考える。しかし、世代交代の時期になり、2代目や3代目にそこまでの強い思い入れがない場合には、生活面や金銭面で無理をしてまで、寿命の近い建物を延命させることに意味はあるのか、と考えるのだと思います。相続のこととか、いろいろなお金の話もありますが、そもそも住宅を物理的にどこまで生き延びさせるか、その判断がせまられているのだと思います。人間と同じで、寿命が来たらきれいに死んでいくというのもひとつの姿だし、たまたま健康であれば、がんばってもうちょっと生きてほしいと延命させることがあってもいい。「私たちの家」はぼくらにとって特別な存在なので、少しだけは延命させることができましたけれど、ぼくらが死んだ後はどうするのか、考えていかなくてはなりません。永久住宅というのはないと思っていますから。
- 野沢 確かに、「住宅遺産トラスト」の活動においても、2代目や3代目などの後継者に無理が生じないように、今の世代の生活と過去の住宅をどうやって整合させるのか、ということはかなり考えていかなくてはならないと思っています。 安田さんのいう戦後の名作住宅は、規模制限があったこともあり、かなり小さいものが多いですから、今の生活に合わないということもあるでしょうし、逆に戦前の「加地邸」(28/遠藤新設計)などは大きすぎて、個人住宅という感じではないですよね。だからもともとの状態に必ずしも縛られなくてもよくて、既存の古い建物の価値を「ヴィンテージ」としてあらためて発見することが必要なのだと思います。またオリジナルにとらわれすぎて、昔の状態を再現しようとすると、いかにもレプリカという感じになって、すごく気持ちの悪いものになってしまうこともあります。意匠や技術、あるいは手間をかける部分への社会的なスタンダードが変わっていますから、むやみに懐古主義的に過去にさかのぼるのはスマートではない。
- 安田 そうですよね。こういう住宅を引き継ごうと思ったら、寒いままでいいのか、お湯が出なくてもいいのか、などといった非常にシンプルなことを一つひとつ解決していかなくてはいけません。だから、ある程度は自由に創造していく、ということが継承の秘訣だと思います。従来の設備のままだと電気代がすごいことになりますし、過去の仕様を職人に頼むと大変なコストになる、などといったリアルな懐具合との兼ね合いもあるはずです。
>> 住宅遺産トラストがかかわった住宅 − 園田高弘邸
>> 住宅遺産トラストがかかわった住宅 − 加地邸
>> 住宅遺産トラストがかかわった住宅 − 代田の町家






