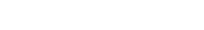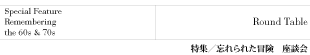
- 長谷川逸子 このあいだ「建築家として一番楽しかったのはいつでしたか」と学生に聞かれて、あらためてふり返ったのですが、「ひとりで小住宅を設計していたとき」と答えたのですね。ひとりでつくっているときは、建材の製品カタログなんてまったく手元にありませんでしたし、必要としませんでした。小住宅には今のように商品が入り込んでいなかったので、キッチンやテーブルまでも大工たちと一緒につくりました。公共建築をつくるときになって初めて、吸音板などを知ったほどです。小住宅は合板やボード類、フローリング、コンクリートでつくっていましたから、それだけ拘束されず自由に発想できたように思います。
——今はディテールの意味が昔よりも大きいように思います。
- 長谷川 豪 どうでしょうか。当時は技術的に複雑なことができないぶん、今よりもシンプルに建築をつくれたというのはあるかもしれません。当時もディテールはもちろんあったと思うのですが、今回取り上げられている住宅(11軒)は、ディテールをはずしても残るものですよね。長谷川逸子さんがおっしゃったように住宅として破綻しているものはありませんし、「冒険」といっても、何か危ういディテールにしたり、住宅から何かの条件をはずして成立させるようなラジカルさではなかったと思います。建築に純粋に向きあえた時代なのだと思います。
- 長谷川逸子 そうですね、今はどうでしょうか。
- 長谷川 豪 当時との違いとしては、住宅というものが、もはや一般化できなくなっているというのは大きいと思います。ライフスタイルが多様化して、個性的な暮らし方を求めるクライアントがたくさんいます。また、これだけ情報があふれているので、たとえば、住宅の性能をとても気にされる人が増えていたりする。基本的にクライアントが住宅に興味をもって勉強するのはよいことだと思いますが。
- 長谷川逸子 ものすごい情報があるなかで、若い建築家につくってもらいたい人はいつもいらっしゃるのね。
——自分の考えが理解される、ひとりのクライアントに出会えればいい、という人もいます。
- 長谷川 豪 それだけではさびしいですね。
- 北山 当時はみんな、プロトタイプをつくることをねらっていたのではないでしょうか。特殊解をつくることを楽しんでいたのではなく、「これからの都市住宅はこれだ」というマニフェストを掲げていたように思います。
- 長谷川逸子
 「住宅としての原型をつくろう」と、どこかで考えていたでしょうね。
「住宅としての原型をつくろう」と、どこかで考えていたでしょうね。
- 北山 そして、そのマニフェストが社会に向けられていたように思います。今は独り言のようで、写真をうまく撮ってメディアにのせられれば建築家になれるかもしれない、というゲームをしているかのようです。
- 長谷川逸子 今は、建築家に社会性を求めていない時代なのでしょうね。当時は、建築家も、社会性を意識して活動していたように思います。今はまったく要望されていない感じすらしています。
- 長谷川 豪 見えにくいかもしれませんが、今の時代の社会性はあると思いますよ。
- 北山 若い世代の代表としては、そうだよね(笑)。
- 長谷川 豪 やはり当時と比べると住宅の社会性が一枚岩ではなくなったということでしょうか。また、たとえば環境問題を気にするなど、クライアントも住宅の社会性を気にするようになったように思います。形を変えながらも、社会からの制約はあります。ただ、それが複雑で見えにくいものになっているのではないでしょうか。