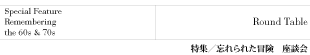
——60年代は、まだ戦後の匂いが残っていた時期ですね。住宅を設計する際に、関連することはありましたか。
- 長谷川逸子 そうですね、住宅は極度のローコストで建てることが求められました。75年の「緑ヶ丘の住宅」でも、工事費は1000万円くらいだったと思います。小住宅をつくるのにも住宅金融公庫の融資は必ず受けていました。その頃住宅は生活の場であるだけではなく、人の集まる交流の場でもありました。今の若い建築家がつくる住宅を見ると、同じ「ローコストの小住宅」とはいっても、その頃つくったものとはまったく違うように感じます。今は「限界バラック」と名付けてつくられているようです。私たちの頃はローコストでも、きちんとしたライフスタイルを提案していました。今、建築家が住宅で実現している「新しい冒険」という芸術性は、〈建築は芸術〉と篠原先生が考えたこととは異なります。ローコストで小さくても、生活に支障をきたすようなものはつくらせてもらえませんでしたし、そうした冒険はしていませんでした。
- 北山 たぶん当時は戦後の民主化で土地をもてるようになり、高度成長期を過ぎて、一軒家に希望がもたれていた時代です。その一方で、若いクライアントはお金を借りてつくるので、切実な要求がありました。要望が多かったので建築家も切実につくらざるをえない。当時の住宅は、ある種の限界点を探るようにつくられていたため、強いものになっているのではないでしょうか。同時に、何か思想が建物に入っていなければ「建築」とはなりませんでしたし、それを要求する批評家もいました。今は、アートオブジェクトのようにつくるために、あえてローコストでつくったりする。それがひとつの作風になっているかのようです。
- 長谷川逸子
 若い建築家たちの日本の住宅は海外でも話題になっています。先日ロンドンでレクチャーをしたのですが、今の建築家住宅に触れて「日本は建築家に寛容ですね」という見方を多く聞かされました。ロンドンでは「住むことの原点」がしっかりとしていないと、住宅をつくることができないからです。日本ではどのような人がクライアントなのか、ともよく聞かれます。私自身はよくわからないので、そうしたときは、「都市で自由に生きようとする若い家族がいると想像します」と答えているのですが。
若い建築家たちの日本の住宅は海外でも話題になっています。先日ロンドンでレクチャーをしたのですが、今の建築家住宅に触れて「日本は建築家に寛容ですね」という見方を多く聞かされました。ロンドンでは「住むことの原点」がしっかりとしていないと、住宅をつくることができないからです。日本ではどのような人がクライアントなのか、ともよく聞かれます。私自身はよくわからないので、そうしたときは、「都市で自由に生きようとする若い家族がいると想像します」と答えているのですが。
- 北山 この時代は、建築家とクライアントは戦っているかのようでしたね。
- 長谷川逸子 クライアントには、すごく苦労させられた記憶があります。貪欲な要望が次々と出てくるので、「そんなにいろんな要望とイメージがあるのなら、私はしばらく何もしないでおこう」と、「ガランドウ」や「長い距離」というテーマを立てることになったのです。要望に応じて進めるとやり直してばかりなので、1年ほどは議論を繰り返し、相手が要望を出しきり落ち着いた頃、ガランドウの住宅を提案するんです。私の設計したある住宅で、当時10代だった娘さんが最近のインタビューに答えて、「玄関からリビングを通って家族や来客に挨拶してからでないと自分の部屋には行けなかった。建築家には、自分の部屋に直接出入りできるように何度も直談判したのだけれど叶わなかった」と。両親の考えですが、今でも根にもっていました(笑)。
- 北山 クライアントにとっては、建築家から教育される意味合いもあったでしょう。それは必要なプロセスだと思います。







