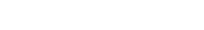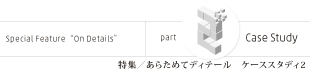
このような全体の大きな構成、つまり基壇があり、その上のあふれるばかりの緑の中央に多面体が存在し、前者が日常、後者が非日常の空間を内側に抱えているという構成の考え方が、部分の、そしてディテールの隅々にまで浸透している。
たとえば基壇を形成する擁壁は、薄い石張りではなく、あくまでも分厚い堅固な石積みであることが追求されている。中国産の緑色スレートの割肌を小端積みとし、コーナーのところでは石の厚みをしっかりと表し、開口部の上端はコンクリートの水平材を積んだ形としている。ガレージのシャッターの縦枠は、通常であれば石壁を欠き込んで設けられるところだが、ここでは石壁からわずかに離して鉄骨を立て、壁の連続性が保たれている。このような配慮を重ねて、純粋な基壇としての表現が得られている。
内部に入ると、外壁とみなされるところは中国産緑色スレートの割肌、内壁とみなされるところはセメント樹脂左官仕上げ、家具的な扱いのところは木質と、平面上では1枚の壁ないし間仕切りであるに変わりがなくても、位置や役割によって、素材もディテールも明瞭な差異がつけられている。
差異化というと、形や光や色といった視覚的なそれが思い浮かぶ。確かにこの住宅でも形や光はもちろん、色についても繊細な配慮がなされている。たとえば、主室の台所側の木の壁は明るく、そこから少し奥まった台所への入り口扉の木は、同じ素材だがわずかに暗色に塗装されている。コンパクトな空間の中で、奥行き感を生み出すための配慮である。2階の天井は三角形の多面で構成されているが、白から黒へ、面ごとにモノクロームの異なる階調で塗装され、面のシャープネスが強調されている。
視覚的な差異化はもちろん単独であるのではない。触感も同時に考慮されている。割肌の石の荒々しさ、左官の壁のわずかな粗さ、木の出隅の角張り、テーブルトップの微細に波打つ木目、ソファの人肌のようなスウェード。加えて、足裏の触感も変化する。目を閉じていても、手触り、足触りで場所の特定が容易にできる。テクスチャーの豊饒な路程。
こうした視覚、触覚への多様な働きかけは、もちろん別個にあるわけではない。ないまぜになって総合的に作用するのである。そのプロセスのなかで、個々の部位の形状やディテールの仕組みは、すーっと背後に遠のいてゆき、いつの間にか消える。「黙せよ」と言う横河さんの声が聞こえる。
>> 「弘中邸」の断面詳細図を見る
>> 「弘中邸」の平面図を見る