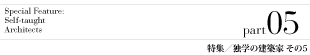
異なるキャリアと
発想の結節
文/伊藤公文
住宅をつくる環境は、年々、不自由になる一方だ。職人の技量、素材、法規や条例、工業製品と同等の精度を求めるクライアントなど。いろいろ考え合わせると既製の部材をごく一般的な技術で組み上げ、さっさと終わらせる方向になびかざるをえない現状がある。こうした現状に断固として反旗を翻すラジカルな住宅。それが小石川の急な崖地に立つ建築面積58㎡弱の「礫明」である。
 「礫明」は親子二代の建築家の自邸。父の通正が言う。「一枚の壁の仕上げを10年考えてみる。その楽しみを味わえるのが建築家の特権で、白井晟一も自邸『虚白庵』(1970)の壁をラスモルタルのまま放置していたではないか」。その実行を阻んだのが融資実行から1年以内の竣工を義務づける住宅融資制度の仕組みだった。そこで彼らは構造体と生活のために必要な最小限の部位だけをつくりあげ、それ以外は「何も決めない」を原則とした。可能な限り完成から遠ざけ、進行形の状態にしておく。とはいえ進行形が貧相に見えてしまうのはよしとしていない。きわめつけは壁の下地材の石膏ボードで、ピンカクのボードを選び、慎重に割り付け、ビス止めの位置とピッチを正確に定めている。寸分の隙もない息づまるような仕上がり。それが進行形ゆえの仮設的な様相に溶け込んで違和感がない。茶室に通じるといえようか。
「礫明」は親子二代の建築家の自邸。父の通正が言う。「一枚の壁の仕上げを10年考えてみる。その楽しみを味わえるのが建築家の特権で、白井晟一も自邸『虚白庵』(1970)の壁をラスモルタルのまま放置していたではないか」。その実行を阻んだのが融資実行から1年以内の竣工を義務づける住宅融資制度の仕組みだった。そこで彼らは構造体と生活のために必要な最小限の部位だけをつくりあげ、それ以外は「何も決めない」を原則とした。可能な限り完成から遠ざけ、進行形の状態にしておく。とはいえ進行形が貧相に見えてしまうのはよしとしていない。きわめつけは壁の下地材の石膏ボードで、ピンカクのボードを選び、慎重に割り付け、ビス止めの位置とピッチを正確に定めている。寸分の隙もない息づまるような仕上がり。それが進行形ゆえの仮設的な様相に溶け込んで違和感がない。茶室に通じるといえようか。
アプローチの生い茂る植栽は通正の探究の成果だろう。1階コンクリートの窓際の床を下げて地下へのあかりとりを兼ねる仕掛けは琢磨の発想か。「礫明」には、ふたりの異なるキャリアと発想が切り結び、緊張感が漲(みなぎ)りながらも、ひとつの枠に納まろうとしない自由な感覚が横溢(おういつ)している。工事期間は10年と琢磨は言うが、おそらくは永遠に未完成の作品として手が入れられつづけるのだろう。それも熟成に至る道ではなく、試行錯誤を繰り返すジグザグの道が選ばれるにちがいない。そして「礫明」から反旗が降ろされることは絶対にないだろう。
>>「映水庵」
>>「礫明 第一期」の図面を見る






