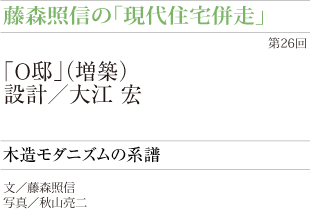“大江宏のデビュー作、それも未発表の住宅がある”と編集者から聞いたとき、ふたつ返事で取り上げることにしたものの、不安があった。
大江宏は、丹下健三、浜口隆一と東京大学建築学科の同期で、卒業年に因んで「昭和十三年組」と呼ばれ、日本の近代建築史に大きな足跡を残している。
卒業後すぐ文部省に入り、さらに三菱地所に転じ、1953年以後は法政大学のプロフェッサーアーキテクトとして教育と設計に尽力しているが、私が知る実作は54年の名作「東洋英和女学院小学部」以後のものばかりで、卒業後16年間、文部省での39年の「国史館案」を除くと、どんな仕事をしていたのか思い浮かばない。
そんな歴史家の頭の中に“卒業直後に手がけた住宅”が飛び込んできたら、不安になって当然だろう。
不安はふたつ。実務経験の乏しい段階の仕事で、果たして紹介に値するかどうか。丹下の向こうを張って独自の戦後デザインを展開した大江宏らしいかどうか。
ふたつの不安を胸にO邸を訪れた。外観をざっと見ただけでは、外装材が改造されており不安はむしろ高まるが、戸口に立ち昔のままのドアまわりを見てひと息つく。左手上のドア灯まわりは明らかにモダニストの手になり、堀口捨己の「小出邸」(25)を思い出す。
中に入り、まず玄関。右手壁には飾り棚状の板がはまり、上部には数寄屋をしのばせる明かり取り。狭いなかにあれこれの工夫と造形を詰め込み、空間としては混乱しているが、これぞデビュー作の証。やりたいことが多すぎて収拾がつかない。
踏み込みを通っていよいよ主室。主室といっても居間、食堂ではなく、書斎と応接間を指すのは、このひと続きの部屋こそ大江の担当した増築部分となるからだ。
大江のデビュー作は、何人かのデビュー作がそうであるように、施主と建築家の若き日の経歴のからみのなかから生まれた。
大串純夫は、大正最初の年(12)、東京に生まれ、大正期を通して中・高を成蹊学園で送り、36年、東大の美術史を出て、美術研究所(現・東京文化財研究所)に入り、気鋭の日本美術史研究者として歩み始める。そして、39年に結婚。滝の川の家を現地に移して妻の成との新婚生活を送ることになり、学者にふさわしい書斎と応接間と玄関の増築を大江に頼んだ。
大江は13(大正2)年に生まれ、中・高を成蹊で送り、38年に大学を終え、文部省に入っている。中・高・大、そして文部省まで共に過ごした青年建築家が、卒業の翌年、若き美術史家のためにした増築ということになる。
>> 「O邸」の平面図を見る