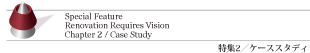
この家の建築的なこだわりは光と影のなかにある。とはいえこの美しい写真のなかにそのこだわりが写っているかどうかを問うなら、写っていないとしかいいようがない。一枚のスチールフォトには写らない。確かに高い完成度が写真から見える。が、この空間の建築的おもしろさのポイントは人が移動しながら、動いていくことで初めて感じる光と影(陰)の変化だ。
陰から光のなかへ、光のなかから陰のなかへ。そこを菊地さんは示そうとしている。玄関扉を開けたところの陰の空間。室内へ入ったところで人は大きな光に包まれる。ここの変化が菊地さんが試みたところ。「どんな順序で風景を見せるかを考える」と言う。
菊地さんは2住戸ともに、南北にのみ窓を大きくあけて東西を塞ぐことで、このワンルーム空間を光にあふれる場に変化させていった。東西の窓は隣家の陰で暗かった。光が入らない窓は暗さを強調するという。南の窓をひとつにし、北の窓もひとつにすることで、光を感じさせる。光が入る窓は光のために。
光と影(陰)、ガラスの透明性と反射の関係。独特の感性を感じる。それを意識化したきっかけを聞いてみた。一連の決定を菊地さんは自分自身の体験の記憶のなかから割り出しているという。「経験、体験、その記憶の定着」だと言う。先の〝水面に落ちた葉っぱ〟がいい例だ。
経験、体験を積み重ね、それを記憶化し、率直に設計に映し込む。常識的な扱い、思い込みをしない。話はじつに具体的で、抽象に逃げない人が菊地さんだ。
「柱の強度は抱きついて揺らしてみる。これぐらいだと自分の身体で大丈夫な柱かどうかは感じ取れる」と。
築40年の家はすでに改修を経てきている。ここまで生きてきた家。補強はするけれど、柱梁に金具を組み合わせたりする気はない。揺れることで力が抜け伝わると信じている。消した東西の窓もあえて窓枠・建具には触っていない。内側に構造用合板を張って塞いでいるだけ。屋根も雨もりのない現状をそのまま保存している。
「問題のないところは触らない」が原則だという。逆に問題を増やしてしまうから。ただ、1階窓ガラスの内側の柱1本だけは太い。3寸角の柱が心配で周辺を巻き、ゆがみも合わせて補修した。
小さなリノベーションに注ぎ込まれたエネルギーを思うとき、この家は幸せだ。後10年、この家が生き延びてくれればと祈っているという。




